�������x���K
�����o�c�����ȁ@�R��@�~
�E���̈ӗ~�������o���d�g�݂Â���ɂ���
�͂��߂�
�@�����A���{�̎����̂͏Z���j�[�Y�̑��l���A���q����A�J���l���������̎Љ���ω��ɂ��A�Ɩ��ʂ̑����Ƒ����ɒ��ʂ��Ă���B
�@���̈���ŁA�Ɩ���S���E�����͕K�������Ɩ��ʂ̑��������݂ɑΉ����đ����ƂȂ���̂ł͂Ȃ��B�V���s���ɂƂ�ƕ���17�N4��1����ŕ���22�N3��31���܂ł�8.1�p�[�Z���g���ƂȂ錩���݂ł���B�܂�Ɩ��ʂ������������ŐE�����͌�������킯�ł���A�E���̕��S���͂��ꂾ���������ƂɂȂ�B
�@���������ɂ����ẮA�ݐЂ��Ă���E���ЂƂ�ЂƂ�̋ΘJ�ӗ~���ő���ɂЂ������A�E���ւ̐ϋɓI�֗^�𑣐i���Ă������Ƃ��d�v�ɂȂ�B�\�Z�̂悤�Ȕ�l�I�����Ɣ�r�����ꍇ�A�E���Ƃ����l�I�����̓����Ƃ��āA�l�I�����ɂ́u�ӎ��v�����邱�Ƃ���������B���Ȃ킿�E���{�l�̂��C�̓x�����ɉ����đg�D�ւ̍v���̓x�����ɑ傫�ȈႢ���o�Ă���̂ł���B
�@�E���̈ӗ~�������o�����߂̕��@�̈�Ƃ��āA�{���|�[�g�ł͑g�D�̖ڕW���L�𒆐S�ɘ_���邱�ƂƂ���B
�P�|�P�D�u�ׂ̐l�̎d����������Ȃ��v�\�g�D�ڕW�̋��L����}��ɂ́H
�l�I�����Ǘ��̎��_���炷��ƁA�g�D�̂Ȃ��Ől�̔z�u��Ɩ����S�̃����⃀�_������Ƃ������Ƃ́A�����̗L�����p���ł��Ă��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B�L�����p�ł��Ă��Ȃ��̂ł���A�g�D�ڕW�ɏƂ炵���킹�āA�l�̔z�u��Ɩ����S���ĕҐ�����K�v������B
���Ƃ��A�g�D�̂Ȃ��ł̐l�̔z�u��Ɩ����S�Ƀ��_�⃀��������ƁA����̐E���ɂ̂ݎd�����W�܂邱�ƂɂȂ�B�����E����ŏ��莞�ԊO�J���ʁi�����钴�j�ɑ傫�ȕ肪����ꍇ�Ȃǂ�����ɂ�����B�g�D�S�̂̋@�\���l����A�ꕔ�̐E���ɕ��S���W�����邱�Ƃ͖]�܂������Ƃł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ疳�p�Ȕ敾�ƕs���Ƃ����̐E���ɗ^���邱�Ƃł���A�܂����S�݂͎̕����̔�����I�ȗ��p�ł��邩��ł���B����ɁA�d���ɂ��Ă̏�g�D���ŋ��L����Ă��Ȃ��\��������A���̏ꍇ�ɂ͏d��Ȍ��ʂ������炷�����E���̂̌������E���ɔF������Ă��Ȃ�������A�ꕔ�̐E���ɂ͔F������Ă��Ă��A���̐E���Ə���L����Ă��Ȃ������肷��\��������B
�����A���{�̍s���@�ւ̑g�D�`�Ԃ́A��X�\���u�啔����`�v�Ɩ��Â��Ă���悤�ɁA�W�c�Ŏd���Ɏ��g�݁A�������L���₷���`�ԂɂȂ��Ă���͂��ł���i��X�\�A2006�j�B���Ȃ킿�u�@�����́i���������K����́j���������́A�ǁA�ہA�W�Ƃ����P�ʑg�D�ɗ^���A�A���������̋K���͊T���I�ł���A�B�E���́A���̂悤�ȋǁA�ہA�W�ɏ������A�C������������ԓI�ɂ͈ꏊ�i�����j�Ŏ�������悤�ȑg�D�`�ԁi��X�\�A2006�j�v�ł���B
�@���������āA�u�E���͉ۂ�W�ɏ������A�ꏊ�Ŏd�������邪�A�ۂ�W�̔C����K�X���S���݂��ɋ��͂��J�o�[���������Ƃ��\�ɂȂ��Ă���B�i�����j�啔����`�̏ꍇ�́A�E�����E���l�ɒ��ڔz�������̂łȂ��A�ۂ�W�Ɋ��蓖�Ă��Ă��邽�߁A�ۂ�W�S�̂ŏ���̊����܂łɎd�����Ԃɍ��킹�Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����A�ۈ��̈�l�̎d�����Ԃɍ���Ȃ���Α��̐E������`��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�ꏊ�Ŗ���������킹�Ďd�������Ă��邽�ߒm���U��͂ł��Ȃ��i��X�\�A2006�j�v�͂��ł���B
�@�Ƃ��낪�A�u�啔����`�v�Ƃ̑Δ䃂�f���ł��鉢�Ắu����`�v�I�����A���Ȃ킿�u�ׂ̌��̐E�����������Ă��邩������Ȃ����A�܂�������Ȃ��Ă������̎d���ɂ͎x��͂Ȃ��B�܂�A�����̐E���Ƃ��Ė��肳�ꂽ�d���ȊO�̎d���ɂ͌������o���Ȃ����A�o���Ȃ��i��X�\�A2006�j�v���̂悤�Ɍ����錻�ۂ����{�ł������邱�Ƃ�����B
�@���Ȃ킿�A�����E��ŋΖ����Ă���E���ǂ����ł����Ă��A�݂��ɂǂ�Ȏd�������Ă���̂�������Ȃ��Ƃ������Ƃ�����킯�ł���B���킹�̐E���ł����Ă��A����͏���Ζ����ԓ��ł͎d�����I��炸�c�Ƃ��K�v�ł���̂ɁA�����͒莞�ɋA���Ƃ������A���o�����X�ȏ�Ԃ������I�ɑ����Ă���E�������i�\1�j�B
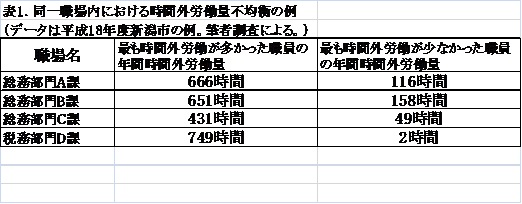
�@�E��̍\���P�ʂł���u�ہi���j�v����т��̉��ʒP�ʂł���u�W�i�ǁA�O���[�v�j�v�̋Ɩ��ړI�A�ړI���s�̂��߂̕��@�A�e�W�̘A�g�̐����i�ȉ��A�Ɩ��~�b�V�����Ƃ����j���\�����S���ɂ���ċ��L����Ă��Ȃ��ꍇ��A�Ɩ��~�b�V�����𐋍s����i�K�ɂ�����i������_�ɂ��Ă̈ӌ������E��苤�L���s�\���ł���ꍇ�A�����I�t�B�X�ɂ���҂ǂ����u�ׂ̐l����������Ă���̂�������Ȃ��v�Ƃ��������Ƃ����肤��B
�@�\�������Ɩ��~�b�V���������L���邽�߂̎d�g�݂������Ă���ꍇ�A�E������������Ă����̂�������Ȃ��Ƃ������Ԃ������A�e�l������Ȕ��f�œ����o�����ƂɂȂ�B���̏ꍇ�Ǘ��҂��܂��A�\��������������Ă���̂��I�m�ɔc�����邱�Ƃ�����ɂȂ�A�E���ԂɋƖ��z���̃A���o�����X�������Ă��F���ł��Ȃ��A�܂��K�X�Ĕz�����s���Ȃǂ̏C�����s�����Ƃ��ł��Ȃ��B
����͑g�D�ɂƂ��đ傫�ȃR�X�g�v���ƂȂ肤����̂ł���A�܂��@�\�s�S�̌����ƂȂ���̂ł�����B�Ǘ��҂ƍ\�����̊ԂŋƖ��~�b�V�����ɂ��Ă̗������H������Ă���ꍇ�A�g�D�̋@�\�s�S�����ԊO�Ζ��ʂ̕s�ύt�Ƃ��Č���邱�Ƃ͑傢�ɂ��肤��B
�@�܂��A�Ɩ��~�b�V�������s���m�ł���ꍇ�A�����}����炸�Ɍ����̍H���Ɏ�肩����悤�Ȃ��̂ł��邩��A�����̎g�����Ƀ��_�⃀�����邢�͏d���������A�s�������������Ȃ��̂ƂȂ邽�߁A�s�K�v�Ɏd�����c��オ�邱�ƂɂȂ�B
�@����ɁA�������������i���ԁA�J�́j�𓊂����d�������Ӗ��Ȃ��̂ł�������A�E����̑��̋Ɩ��Ƌ����E�Η�������̂ł������肷�邱�Ƃ����肤��B�L���Ȏ�����Q��Ȃ����߂ɂ́A�S�̖ڕW�Ɖ��ʖڕW����Ȃ�Ɩ��~�b�V�������Ǘ��҂ƍ\���������L���A�~�b�V�������s�̉ߒ��ŃR�~���j�P�[�V���������킵�A�O���C���������Ă������Ƃ��K�v�ł���B
�@�ł́A�g�D���ŋƖ��~�b�V�����̋��L����}�邽�߂ɂ͂ǂ�������悢���B��̉����@�Ƃ��đg�D���̃R�~���j�P�[�V�����𑣐i����Ƃ������@������B�����o�[�̃R�~���j�P�[�V������ʂ��āA�g�D�̉ۑ������v���Z�X���m�ۂ��A�ۑ苤�L��}��Ƃ������̂ł���B
�u�ڕW�Ǘ��V�X�e���v�ƌĂ����@�́A�g�D�����o�[�̑Θb��ʂ��āA�g�D�ڕW�i��ʖڕW�j�ƌl�ڕW�i���ʖڕW�j�̓������͂���V�X�e���ł���A�Ɩ��~�b�V�����̋��L�����l���邤���ő傢�ɎQ�l�ɂȂ�B�ȉ����̉\���ɂ��čl�@���邱�ƂƂ���B
�P�|�Q�D�ڕW�Ǘ��V�X�e��
�ڕW�Ǘ��V�X�e���Ƃ́A�g�D�ڕW�ɓ����\�Ȍl�ڕW��ݒ肵�A�l�͎���ݒ肵���ڕW�Ɍ������Ďd����i�߂邱�ƂɂȂ�B�ڕW�̘A���ɂ���āA�l�̖ڕW�Ƒg�D�̖ڕW�����т��Ă���A����ɂ���ĐE���̎��含�������o�����Ƃ��ł���A�Ƃ������̂ł���B[1]
�@�ڕW�Ǘ��V�X�e���̂悢�Ƃ���́A���僌�x���̑g�D�ڕW�ƐE���l�̖ڕW�̐ݒ�ɓ�����A�S���҂ƊǗ��҂Ƃ��c�_���d�˂Ă��݂��[��������Őݒ���s�����Ƃ��ł���_�ł���B���̍�Ƃɂ��A���̑g�D�������Ă���d���_�����邱�Ƃ��ł���_�ł���B����ɂ��g�D���u����Ă��錻��܂��������ŁA�d���̕K�v���̓x������D�揇�ʂ��ӎ����Ď�̑I�����邱�Ƃ��\�ɂȂ�B�ڕW�ݒ�̂��߂̖ʒk��ʂ��āA�Ǘ��҂ƒS���҂Ƃ̊ԂŐE�ꂪ���ʂ��Ă�����̐o���Ƌ��L���\�ɂȂ�B
�܂��A����[�����������ŖڕW�ݒ���s�����̂ł��邱�Ƃ���A�ڕW�����猈�߂��Ƃ����ӔC����g�D�ڕW�����ւ̎Q��ӎ������܂�邱�ƂɂȂ�B���������ӔC����Q��ӎ��̓��`�x�[�V��������v���Ƃ��Ȃ�B
�@�ڕW�Ǘ��V�X�e�����@�\���邩�ǂ����́A�ڕW�ݒ�i�K�ɂ����ĊǗ��҂ƒS���҂Ƃ̊ԂŁA������Ƌc�_���Ȃ��ꂽ���ǂ����A�����Ĕ[�����������ŖڕW�ݒ���s���Ă��邩�ǂ����ɂ������Ă���Ƃ����Ă悢�B
�P�|�R�D�u�ڕW�Ǘ��ɂ����эl�ہv�Ɓu�R���s�e���V�[�ɂ��\�͍l�ہv�@�\�@�ݘa�c�s�ɂ�����ڕW�Ǘ��V�X�e���̎���
�@�g�D�ڕW�ƐE���l�̖ڕW�̓�����}�鎎�݂ł���ڕW�Ǘ��V�X�e������т��̑��̎d�|����l���V�X�e���ɑg�ݍ���ł��鎩���̂�����A�l�I�����Ǘ��E�l�ވ琬�̂�������l����ۂɂ����ւ�L�v�ł���B����玩���̂̂��������[j1] ���āA�ݘa�c�s�̎�����ȉ����Ă������ƂƂ������B
�@�u�ݘa�c�s�l�ވ琬��{���j�v�ɂ��A�u����܂łɂ��l�ވ琬�ɂ��ẮA�E�����C�̏[����K�ޓK���̔z�u�̂��߂̎��Ȑ\�����x�A�������吧�A�W���u���[�e�[�V�����Ȃǂ���������A�e�����̂Ől���E���C�S���ɂ���ėl�X�Ȏ��g�݂��Ȃ���āv�������̂́A�u�l�����x��l�ވ琬�ɐ������Ƃ������z���s�\���ł�������A�l���Ɋւ��邱�Ƃ́u����v�Ƃ����������ˑR�Ƃ��Ďc���Ă��邽�߁A�l���Ǘ��̒��S�ƂȂ鏸�C�A�����A�z�u�ɂ�����鐧�x�₻�̉^�p�ɂ��ẮA�������\�N�ԂقƂ�lj��v����Ȃ������v�Ƃ����B����������́A�u�ݘa�c�s�ɂ͍��A�ǂ̂悤�Ȑl�ނ��K�v�Ȃ̂��B���̂��߂ɂ́A�E���̔\�͊J�����ǂ̂悤�ɂ���̂��B����A�ǂ̂悤�Ȑl�ނ��̗p���Ă����̂��B�܂��A�E�����ǂ̂悤�Ɋ��p���A�ӗ~�������o���A�ӎ����v�Ƒg�D�̊��������͂����Ă����̂��B�����m�ɂ���������݂̐l�������x�����v���A�헪�I�E�����I�Ȑl�����x�Ƃ��čč\�z�v���邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ����B[2]
�@�ݘa�c�s���l���E�l�ވ琬�V�X�e���̒��S�ɐ����Ă���̂́A�u�ڕW�Ǘ��ɂ����эl�ہv�Ɓu�R���s�e���V�[�ɂ��\�͍l�ہv�ł���B
�@�u�ڕW�Ǘ��ɂ����эl�ہv����ɏq�ׂ��ڕW�Ǘ��V�X�e���ł���B�ݘa�c�s�ɂ����ẮA�ڕW�Ǘ��͌l�̎��т��l�ۂ���ړI�̂ق��ɁA�ڕW�Ǘ����g�D�}�l�W�����g�����コ���鐫���������Ƃɒ��ڂ��Ă���B���Ȃ킿�A�ڕW�Ǘ��ɂ��g�D���ŖڕW�����L����A�܂��������Ϗ����E���̎��含�������o�����Ƃɂ���đg�D�ƌl�̎��͂��ő���Ɉ����o�����Ƃ�_���Ƃ��Ă���̂ł���B[3]
�@���������āA�ڕW�ݒ肨��ю��{�̉ߒ��ɂ����āA�u�E��~�[�e�B���O�v��u�ʒk�v�Ƃ������ނ̑Θb��@�����p���āA�E����R�~���j�P�[�V�������\���ɂ͂��邱�Ƃ��d�����Ă���B�u�E��~�[�e�B���O�v�Ɓu�ʒk�v�́A��i�ƕ����Ԃ⓯���ԂŎd���ɂ��Ă̍l��������o�������A�ӌ��𑊌��������ł���A�d���̎��H��ʂ��Ă̑��݊w�K�������Ƃ��Ă��ʒu�t�����Ă���B
�@�����A�u�R���s�e���V�[�ɂ��\�͍l�ہv�́A�l�ވ琬�̎��_����v�����l�ې��x�ł���A�u���l�E�ڕW�����L���d���ɂ�肪���������A��������������A�l�ɕ]�������i�F�߂���j�������������ł���\�͊J���̂��߂̃c�[���v���R���Z�v�g�Ƃ��Ă���B[4]
�@�u�R���s�e���V�[�v�Ƃ́A���ꂼ��̐E���ɕK�v�Ȕ\�͂��`�������̂ł���A��ʓI�ɂ͐E�����ƂɃn�C�E�p�t�H�[�}�[��I�яo���A�ނ�i�܂��͔ޏ���j�̍s�������ɋ��ʂ���L�[�E�t�@�N�^�[��ʐڂ�ώ@���璊�o����B���̂����ŁA�e�E���𐋍s���A�D�Ɛт������邽�߂ɕK�v�ȃR���s�e���V�[���܂Ƃ߂����̂��u�R���s�e���V�[�E���f���v�Ƃ����B[5]
�@�ݘa�c�s�̏ꍇ�A�u�R���s�e���V�[�v�����Ƃɍl�ۊ���쐬���Ă���B���̍l�ۊ�ɂ��A��ꎟ�l�ێ҂Ƃ��Ė{�l���������g���l�ۂ���i�{�l�l�ہj�B�E���{�l�ɂƂ��čl�ۊ�́A����u�����d�������邽�߂ɕK�v�ȍs���Ƃ��̒���_�v����̓I�Ɏ������u�\�͊J���c�[���v�̖��������ʂ������ƂɂȂ�B
�@���łɏq�ׂ��Ƃ���A�ݘa�c�s�ɂ����āA�u�R���s�e���V�[�ɂ��\�͍l�ہv�͐l�ވ琬�̎��_����v���Ă��邽�߁A�{�l�ւ̍l�ۂ̃t�B�[�h�E�o�b�N���d�����Ă���B��ꎟ�l�ہi�{�l�l�ہj���o�āA��l�ہA��O���l�ۂ��ςނƁA��i����{�l�ɑ��čl�ۃV�[�g���ԋp�����i�\�Q�j�B���Ȃ킿�A�l�ی��ʂ�{�l�ɑ��ĊJ�����邱�ƂŁA�{�l�l�ۂƑ�l�ہA��O���l�ۂƂ��r���邱�ƂŁA�u���������Ă��鎩���v�Ɓu���l�����Ă��鎩���v�Ƃ̈Ⴂ��F�����A���Ȃ̔\�͊J���̉ۑ蔭���𑣐i����˂炢������̂ł���B
�@�{�l�ւ̍l�ۂ̃t�B�[�h�E�o�b�N�͏�i�ƕ����Ƃ̖ʒk�ɂ��s����B���̖ʒk�͑g�D���R�~���j�P�[�V�����̋@��ł���A�ʒk��ʂ��Ė{�l�ւ̍l�ۃt�B�[�h�E�o�b�N�ɉ����A�g�D�ڕW��g�D�������Ă���ۑ�ɂ��Ă̈ӌ������Ə�L���͂����D�̋@��ł�����B
�\2�D�{�l�ɕԋp�����\�͍l�ۃV�[�g��
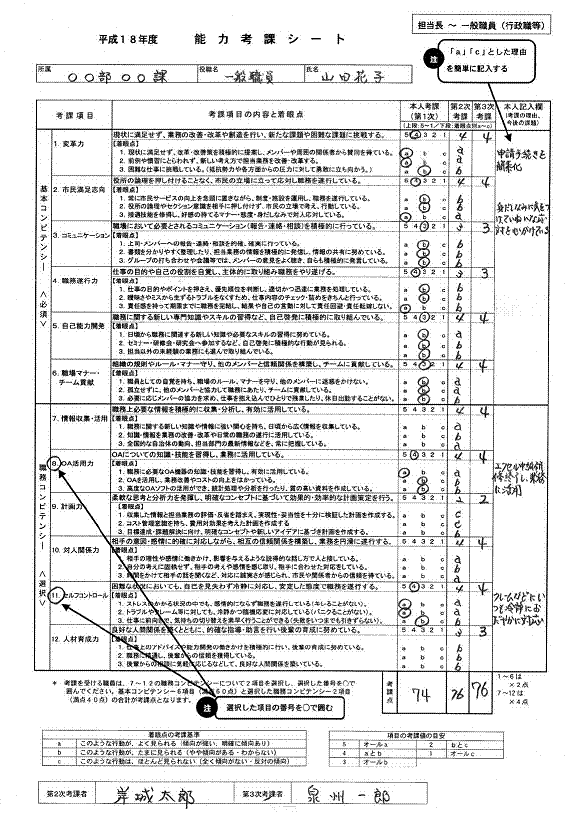
�}�P�D�\�͍l�ۃt�B�[�h�E�o�b�N�̗���
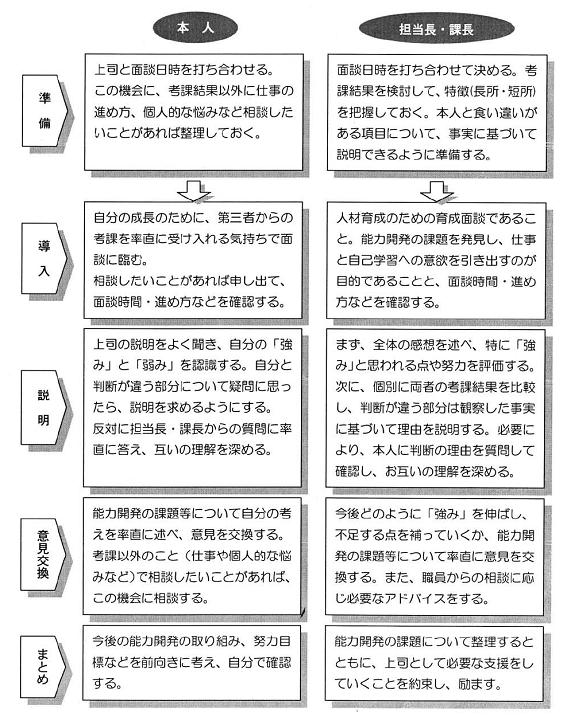
�@�ݘa�c�s�l�ވ琬���j����̔w�i�ɂ́A�ߔN�̘J���҂̈ӎ��̕ω�������B���Ȃ킿�A�Љ�̉��l�ς����l�����A�����̓K���ɍ���Ȃ��d������������A�����̓K���E�\�͂�����d�����������A���Ȏ������邱�Ƃɉ��l�����o���u�d���l�v�u�����E���̊Ԃɂ��Z�����Ă��Ă���̂��Ƃ����B���������āA�E���̈ӗ~�������o���A�\�͂������o�����߁A�����̐E���̈ӎ��ɑΉ������u���d���A�\�͂�L���v�l�����x�E�^�p�ւƓ]�����͂���̂��Ƃ����B[6]
�@�Љ���̕ω��ɔ����E���̈ӎ����ϗe���Ă���B�ω��ɑΉ����邽�߂̊ݘa�c�s�̎��g�݂͂����ւ��[���B����̓W�J�����҂����B
�܂Ƃ�
�����̂ɂƂ��āA�E���͂����Ƃ���{�I�ł��肩�d�v�Ȏ����ł���B�l�I���������p�ł��Ă��邩�ǂ����ŁA�����̂̃T�[�r�X�̕i���ɍ��ق�������͂��ł���B�E�������X�Ȃ���d���Ȃ��Ɏ��g��ł���ꍇ�ƁA�ӗ~�I�Ɏ��g��ł���ꍇ�ł͎�v�҂ł���Z���̖����x�͑S���قȂ�B
�E���̈ӗ~�������o�����߂̎d�g�݂��\�z����ۏd�v�Ȃ̂́A�E���̈ӎ��̕ω��܂��������ŁA�g�D�̖ڕW�m�����A�g�D�ڕW�ƌl�̖ڕW�Ƃ��\�Ȍ���߂Â��Ă������Ƃł���B�d�g�݂̍\�z�ɓ������ẮA�����I�Ȏ���Ől�I������L�����p���鎋�_���������Ȃ��Ƃ����悤�B
�Q�l����
���эN�i�w����l�I�����Ǘ��x�����o�ώЁA2003
��X�\�w���̃V�X�e���x������w�o�ʼn�A2006
����_��Y�A���������w�l���Ǘ�����x���{�o�ϐV���ЁA2002
�㓡�q�v�w���C��b�u���Q�@���Ȍ[���x�Y�ƘJ���������A1985