�������x���K���|�[�g�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����o�c�����ȁE�˓c��C�u
����V�Ԕ�s��Ւn���p�Ɍ���n���ҍ��ӌ`���̕������Ɖۑ�
�͂��߂�
�@����ɂ����āA�n���҂ɂ�鍇�ӌ`���́A�~���ȐՒn���p�𐄐i���邽�߂̍ŏd�v�ȗv�f�̈�ł���B���������āA���Y�����̂́A�Ւn���p�v������肷��ہA�I�m�ɒn���҂̗��p�ӌ���c�����Ă����K�v������B
�{�N�[���ł́A�X��p�s�ɏœ_�Ă�B���݁A�X��p�s�ł́A���V�Ԕ�s��Ւn���p�ɍۂ��āA�n���҂̈ӌ���c�����邽�߂ɗl�X�Ȓ����Ɩ���W�J���Ă���B�{�e�ł́A���ɒn���҂�ΏۂƂ����A���P�[�g�������ʂ͂��A�n���҂��������Ւn���p�̂������T�邱�Ƃ��_���ł���B
���V�Ԕ�s��͌����ŗB��A��K�͕ԊҐՒn�Ɏw�肳��Ă���A���̗��p��@�́A����̉���S���̊�n�ԊҐՒn�ɂ��ĎQ�l�ɂȂ���̂Ƃ��Ē��ڂ��W�߂Ă���B�܂��A���̌����ɂ����Ă��A�n���҂̎��_���瓯��s��̐Ւn���p�ɂ�����_�_���A��ʓI�ȃf�[�^��p���Đ������������Ƃ́A�L�v�ł���ƍl����B
�ӌ������̖ړI
�X��p�s�ł́A����15�N�x���Ɂu�X��p�s�s�s�}�X�^�[�v�����v�����肳��A�����ŁA�X��p�s�y�щ��ꌧ�ɂ��A����16�N�x����3���N�v��ŁA�u���V�Ԕ�s��Ւn���p��{���j�v�̂Ƃ�܂Ƃ߂��s���Ă���B�����̍���ɓ������ẮA���L�n���唼���߂镁�V�Ԕ�s��̒n���҈ӌ��̔c�����A�d�v�ł���Ɗm�F����Ă���B
����܂ŁA���V�Ԕ�s��̒n���ғ��ɑ����g�݂Ƃ��ẮA����13�N�x�ɂ́A�n���ғ��ւ̏���ӌ��c���̕��@�A���ӌ`�������̗��O�A�i�K���Ƃ̖ڕW�����߂��u���V�Ԕ�s��W�n���ғ��ӌ��c���S�̌v��v�����肳�ꂽ�B�����āA����14�N�x���u���V�Ԕ�s��Ւn���p�Ɋւ���ӌ�����[1]�v�����{����Ă���B
�{�����̖ړI�́A�e��v��̍���ɍۂ��āA�l�����ׂ��n���҂̐���������Ă�����E�ۑ蓙�m�ɂ��A�v��֔��f��������ƌ����ۑ�����ƂƂ��ɁA����̍��ӌ`�������̓K�����E�������Ɍ�������b�����Ƃ��邱�Ƃɂ���B�@
�ӌ������̕����i����15�N�x�E��K�͒����R�p�Ւn�����p���i�����EN=1729�j
�P�j�҂̑���
�@�҂�3/4�ȏ�i77.3���j���X��p�s�����Z�҂ł���B���ʂɊւ��ẮA�j������7���A��������3���ł���A�҂̕��ϔN��͖�60�A60�Έȏ�̉҂�56�����߂�B����āA4���ȏ�i43.6���j�����E�ł���B�Ȃ��A�҂̖�7�����n���ɉ������Ă���[2]�B
�O���t�P�����ė~�����B����̒����ŗ��ӂ��ׂ��́A���ʁE�N��ɕ肪�����Ă���A���ɍ���҂��������Ƃł���B���V�Ԕ�s��̕Ԋ҂͌���ς݂ł��邪�A���̋�̓I�Ȏ����͂��܂���������Ă��炸�A�ŒZ�ł�15�N��ł���B�߂������ɒn��̐�������\�z����邱�Ƃ���A��N�w�̒n���҂⍂��n���҂̉Ƒ����̈ӌ��c���ɂ��͂����Ă����K�v������B
�O���t�P�@�N��
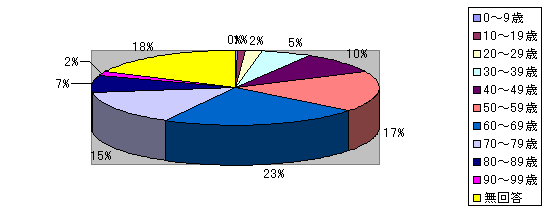
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���L����R�p�n�ʐςɂ��ẮA���L�K�͂ɕ��U����������̂́A�u1000�u�ȏ�3,000�u�����v�Ƃ̉��ő��ł������B�܂��A�ߔN�x�����Ɣ�r�����ꍇ�A500�u�����̏��L�҂��������Ă���B���R�Ƃ��ẮA��K�͓y�n�̏��L�҂╡���y�n�̏��L�҂ɂ����āA�����Ȃǂɂ��n���҈�l������̏��L�ʐς��������Ă��邽�߂��ƍl������B
��N�Ԃ̌R�p�n���ɂ��ẮA�u300���~�����v�̉��ł������A�S�̂�6���i���������ƑS�̂�8����ɒB����j�����B�N�ԑ������ɐ�߂�n���̊����Ƃ��ẮA�S�̓I�ɉ͕��U���Ă��邪�A�N��ʂɌ����ꍇ�A50�Έȏ�ɂ��ẮA�N�オ�����Ȃ�ɂ�đ������ɐ�߂銄���������Ȃ�X���ɂ���B
�Ȃ��A�J���͐���ɂ����閳�E�̊����́A�u30�Α�O��9.1���v�A�u30�Α�㔼7.4���v�A�u40�`54��6.1���v�ł���A�������S���Ɨ��i����14�N�x�E���ꌧ�����j���������X���ɂ������B�������ɐ�߂�n���̊���������قǍ����Ȃ��Ƃ͂����A�n�������ƘJ���ӗ~�̐��ނ͖��W�ł͂Ȃ��悤�ł���B
�O���t�Q�@�N�ԑ������ɐ�߂�n���̊���
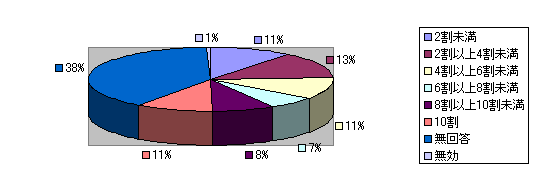
�Q�j�y�n���p�̈ӌ��ɂ���
�@�y�n���p�Ɋւ���W�v���ʁi�O���t3�j�Ƃ��ẮA������ꐔ�Ƃ��������Ō���Ɓu���ȏZ��v���ł������A�����Łu�\��Ȃ��v�ƂȂ��Ă���B�܂��A�����邽�߂̓y�n���p�Ƃ��ẮA�u���ݏZ��v���ő��ƂȂ��Ă���B
�S�̓I�ȉƖʐς̊W����́A���L�ʐς̏������n��قǁu���ȏZ��v���A�傫���n��قǁu�y�n���݁v��u���ƃr���v�����Ă���X���ɂ���B�����A�����ɐ�߂�n�������ʂɌ���ƁA�n�������������Ȃ�ɏ]���āA�u�y�n���݁v�̉�������X���ɂ���B�@
�����̂��Ƃ���A���p���@�����o���Ȃ��n������Ȃ��Ȃ����ʁA�n���ւ̈ˑ��x�������n��́A�ԊҌ���n�����l�̌������������ƍl���Ă���ƌ����悤�B
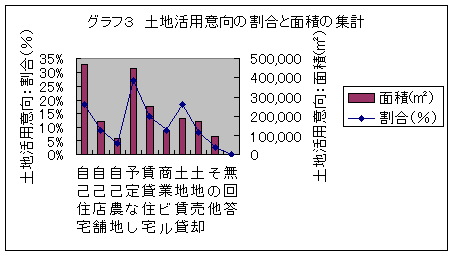
�Ȃ��A�y�n�i�R�p�n�j���ݒn���u�킩��Ȃ��v��I�������҂́A���Ɣ�r���āu�y�n���p�v�̈ӌ������ɋ����X����������B�y�n���p�\��̒n��́A�R�p�n���̂��̂ւ̊S���Ⴍ�A�Ւn���p�ɑ��ď��ɓI�ł���ƍl������B
�@
�y�n���p�̕��@�i�O���t�S�Q�Ɓj�ɂ��āA�u�����̕��S��w�����Ă��A�S�Ď����œy�n���p���s�������v�Ƃ����́A26.7���ł���B�����܂߂��c��̐����́A73.3���ɂȂ�B�܂�A�y�n���p�ɂ��Č��i�K�ŁA�u�����œy�n���p���s�������v�Ƃ��������ӎv�\�������Ă���n�傪�A4���̂P�ɉ߂��Ȃ��Ɖ��߂ł���B���ہA13.9���������邽�߂̓y�n���p���l���Ă��Ȃ��B�c���36.6�����g�D�A�����͕������̃O���[�v�ɂ�銈�p���l���Ă���B���������āA���͂���Ւn���p�v�悪�o���オ������A����̒n���҂��A����Ɏ^������\���������ƌ�����̂ł͂Ȃ����B
�@�܂��A�y�n���p�̂��߂̎x���Ƃ��ẮA�u���K�ʁv�Ƃ̉��ő��ł���A�S�̂̔����߂��ɒB�����B�����ŁA�u���ʁv�A�u�����E������v�̎d�g�݁v�Ƃ̉��A����3�������߂��B�t�ɁA�u�x���s�v�v�Ɠ������n��́A�P���ȉ��Ƃ��Ȃ菭�Ȃ����߁A�قƂ�ǂ̉҂����炩�̎x������]���Ă���ƍl������B�s���ɑ���n��̊��҂́A��r�I�傫���Ƒ����邱�Ƃ��ł���B
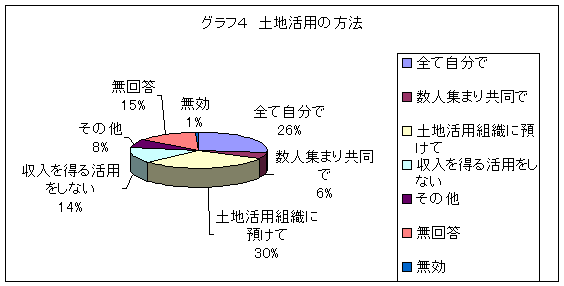
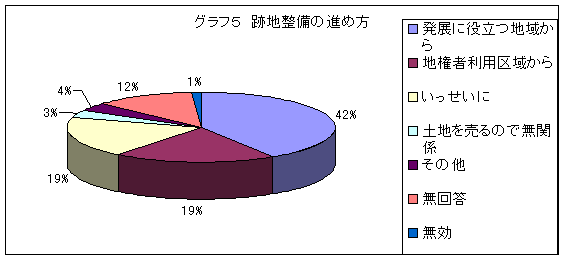
�@
�n���҂̌v����ւ̊ւ���
�@�Ւn�����̐i�ߕ��i�O���t�T�Q�Ɓj�Ɋւ��ẮA�u�܂��̔��W�ɖ𗧂n�悩��v�Ƃ̉�4�����ƍő��ł���A�u�n���҂����ȗ��p�����悩��v�Ɓu�S�Ă̓y�n�����������Ɂv����2�����A�قړ����ő����Ă���B�����Ɂw�Ւn�����x�̐i�ߕ��݂̂ɂ��Ē��o�E���͂����ꍇ�A�u�܂��̔��W�ɖ𗧂n�悩��v�Ƃ̉���5���ɒB����B�܂��Â���ɂ�����i�K�I�����Ɋւ��āA���x�̒n��̗����͓����Ă���ƍl������B
�����A�W�n���҂��A�Ւn���p�̌v�����ɂǂ̂悤�Ɋւ������ǂ����Ƃ�������ɑ��ẮA�u��n���҂Ƃ��ĐϋɓI�ɎQ������v�Ƃ�����17.9���A�u�A���P�[�g��������n��̍l����������Ă����Ηǂ��v�Ƃ̉�34.2���ł������B���������킹���52.1���ƂȂ�A�ߔ�������n���҂��A���������������܂��Â���ɑ��č����ӎ���L���Ă���Ɠǂݎ���B
�����A����͂ǂ��ł��낤���B���݁A�X��p�s�ł́A�n���҂���̓I�Ɍv������ƂɊւ����̕ۏ�Ƃ��āA�n���ҍ��k������I�ɊJ�Â��Ă���B�Ƃ��낪�A�A���P�[�g�W�v���ʂɂ��A�u��x���Q���������Ƃ��Ȃ��v�n�傪�A43.4���ɂ��y�ԁB�܂��A����̒n���҂��������Ƃ���A��N�w��Ώۂɂ������k����J����Ă��邪�A������̎Q��������̒n��Ɍ����Ă���ɂ���悤���B
�ԊҐՒn�̗L�����p�ɂ���āA����܂ł̌R�p�n���Ɋ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��n���҂͏��Ȃ��Ȃ��B�ԊҐՒn�͒n���Ҍl�̍��Y�ł���B����܂ō��k��ɏo�Ȃ������Ƃ̂Ȃ��n���҂́A�n���ˑ�����E�p�ł���悤�ȍ��Y�^�p��}�邽�߂ɂ��A�ꕔ�̊S�̍����n���҂�s���ɔC������ɂ���̂ł͂Ȃ��A�ϋɓI�ɐՒn���p�v��̍���ɎQ�悵�Ă����ׂ����B����A�s���ɂ����ẮA����A�n���Ҋe�l�̐Ւn���p�ɑ���Q���ӎ������߂邱�Ƃ��ۑ�ƂȂ�B
�ߋ��ɉ���ł́A�n���҂���̂ƂȂ��đg�D���ꂽ�u�����g���v�ɂ���āA�y�n��搮�����s�������Ƃ���������[3]�B�n���Ҏ哱�ł܂��Â��肪�i�߂��A�s���̓T�|�[�g���ɓO�����D��Ƃ����悤�B��K�͐Ւn�ƂȂ镁�V�Ԕ�s��̏ꍇ�A���p�p�r������ɂ킽��A���Ƃ̋K�͂͑傫���Ȃ���̂́A�n���Ҏ�̂̑g�D�I�Șg�g�݂���������Ƃ����_�ŁA�X��p�s���������鉿�l�͏\���ɂ���͂����B����ɂ��ẮA����̃��|�[�g�ŏڏq���邱�ƂƂ������B
�y�Q�l�����E�����z
�X��p�s�u���V�Ԕ�s��Ւn���p�Ɋւ���ӌ������v2003�E2004�N�x��
�X��p�s�u���̂��̂܂��Â���\���V�Ԕ�s��W�n���ғ��ӌ��c���S�̌v��\�v2002
�X��p�s�z�[���y�[�W�ihttp://www.city.ginowan.okinawa.jp/�j
���ԑגj�w����o�ς̌��z�ƌ����x���{�o�ϕ]�_�ЁA1998