自治制度演習レポート 塚田大海志
「沖縄における軍用地料にみる地権者問題」
はじめに
在日米軍基地の75%が沖縄に集中し、その面積は、沖縄本島の20%を占める。市街化が進み、用地確保が困難になりつつある本島・中南部地域における基地返還跡地の利用は、沖縄全体の振興開発に重要性を持つ。
返還に関わる問題の一つとして、地権者の存在が挙げられる。沖縄の米軍基地は、沖縄戦直後の占領に加えて、新規接収を繰り返しながら形成されてきた。その補償として、地権者は、日本政府から高水準の軍用地料を受け取っている。そのため、地権者にとって基地の返還は、安定性のある継続収入を失うことを意味する。一方、関係自治体には、跡地利用を進める際、地権者のみならず、それ以外の市民も納得できるような、公共性を備えた計画策定が求められている。
本クールでは、地権者の受け取る軍用地料の問題を扱う。現行の制度が設置された経緯を概観するとともに、返還を見据え、沖縄における地権者のあり方を問い直すことが狙いである。その上で、地権者の自立を促すような、地料問題の解決策を模索したい。
沖縄の米軍基地の特徴
日米安保条約では、米軍の使用する土地は「提供施設」と総称され、日本政府が国有地を提供する形態を取るのが基本である。民有地域の場合は、それを国が買い上げて提供している。だが、本土の米軍基地の大半が、戦前の旧日本軍の基地をそのまま使用してきた。その結果、本土の場合、87.5%が国有地であり、民・公有地は12.5%に過ぎない[1]。
一方、沖縄の場合は、国有地は34.1%、市町村有地が29.2%、県有地が3.5%と、全体の3分の2が民・公有地となっている。特に、本島・中部地域においては、民有地が75.5%を占める[2]。これは、沖縄の米軍基地が、旧日本軍の使用した区域に止まらず、かつての土地闘争[3]に見られるような、米軍による民・公有地の新規接収が各地で行われた背景の違いを示している。
軍用地料制度創設の背景
沖縄戦後、沖縄を占領した米軍は、住民を16ヶ所の収容所に集めて隔離生活を強いた。1945年10月頃から、住民は元々暮らしていた集落に帰ることを許されたものの、沖縄本島の10数%に相当する用地は、すでに軍用地として確保されていた。これが、沖縄における軍用地接収の第一段階である。なお、1952年4月のサンフランシスコ講和条約までは、地料の支払いは一切なかった。米軍は、戦場または占領地の継続状態にある軍用地の使用は、国際法上当然に与えられた権利であるとし、「陸戦の法規慣例に関する条約(ヘーグ陸戦法規)」を地料未払いの根拠としていた。
講和条約発効後の沖縄では、軍用地料を巡る問題が、争点としてクローズアップされ始めた。そこで、USCAR(米国民政府)は、毎年賃借料を支払う代わりに、土地代金に相当する額を一括して支払う方が得策であるとの観点から、一括払いの計画を発表した。しかし、提示された額があまりにも低かったため[4]、ほとんどの住民から反対された。また、この問題を重視した立法院も1954年4月、「軍用対処理に関する請願決議」を全会一致で採決した。この決議の中で要請された4項目は、『軍用地問題に関する四原則[5]』として、その後の沖縄における基地闘争の基本原則となった。
「請願決議」を下に、行政府・立法府・市町村長会・市町村議会議長会・軍用地主連合会の五者は、「五者協議会」を結成し、以後、現地米軍と折衝を重ねていった。しかし、何らの解決策を見出せず、沖縄の代表が先の「四原則」を掲げて渡米した。その結果、一括払いの一時的な中止と調査団の沖縄への派遣、土地接収を最小限に止めることが決まった。
1956年6月、ようやく引き出した米国議会の調査団(プライス団長)の来沖に期待を寄せた沖縄住民だが、その報告書(プライス勧告)の内容は、沖縄に核基地を建設する方針を承認して、地料を上げ過ぎないように戒めるものであった。これに県民は猛反発し、各地で住民大会や四原則貫徹県民大会が開催され、プライス勧告反対闘争は、沖縄全域へと拡大した。いわゆる、「島ぐるみ闘争」である。
島ぐるみ闘争の成果として、1959年1月に「土地賃借安定法」及び「アメリカ合衆国が賃借する土地の借賃の前払いに関する立法」の二つが制定され、同年2月には、布令20号「賃借権の取得について」が公布された。これにより、軍用地の取得、地代の評価、その支払い方についての制度的な確立が図られたと言える。
表1を見ればわかるように、それまで問題外の水準であった地料は、当初の提示額の6倍となり、地主要求の80%を満たしていることがわかる。また、実質上の買取を意味する一括払いは取り下げられ、5年を限度とする前払いも可能になった。
表1 軍用地料の引き上げ経過 (軍票1B円=3日本円)
|
年次 |
総額(B円) |
指標1 |
指標2 |
指標3 |
|
1952年4月分~1953年6月分 (1953年度として一年分に換算) |
137,446,312 117,811,128 |
100 |
|
|
|
1956年に沖縄地区工兵隊再評価した額 |
357,313,530 |
303 |
100 |
|
|
1959年度に改定された額 |
716,212,495 |
608 |
200 |
80 |
|
1956年の査定に反発して地主が要求した額 |
891,089,482 |
|
249 |
100 |
(沖縄国際大学公開講座Ⅳ『沖縄の基地問題』より引用)
軍用地料制度の現状
1972年5月、沖縄は日本復帰を果す。それに伴って、1959年より引き上げられた地料の水準は、さらに飛躍した。米軍が地主の了解を得ることなく、強制的に使用してきた軍用地は、沖縄が日本の法体系に組み入れたことで、日本政府との契約が必要になったからである。それまで返還を要求してきた地主や自治体には、契約に応じない者もあり、復帰時点で契約を済ませることはできなかった。そのため、未契約地主を説得する有効な手段として、軍用地料の引き上げが実施された。また、それだけではなく、地主からの同意を取り付けるための嵩上げ措置もなされた[6]。その結果、59年の21億円が、復帰時には126億円と、一気に4倍にまで引き上げられた(表2参照)。
表2 復帰時の軍用地引き上げ
|
年度 |
総額 |
指数 |
|
1972年度(71年7月1日~72年5月14日、321日間) |
31億円 |
100 |
|
1972年度(72年5月15日~73年3月31日、321日間) |
126億円 |
407 |
|
他に、見舞金25億円、協力謝金10億円等を含めた額 |
190億円 |
613 |
(来間泰男『沖縄経済の幻想と現実』より引用)
軍用地料は1972年度の126億円から、2001年度には766億円(米軍基地751億円、自衛隊基地98億円)へと伸びている。復帰時より、さらに6倍の飛躍を遂げたことになる。
グラフ1を見て欲しい。米軍施設面積が揺るやかな減少を辿っているにもかかわらず、軍用地料は、経済状況の影響を全く受けず、右肩上がりで推移しているのが読み取れよう。
高水準の軍用地料の背景には、人口・産業が集中する本島中南部に7割を超す民有地があり、軍用地料が宅地並みの評価を受けていることが挙げられる。復帰前は、10年据え置きだった地料は、復帰後、日本政府によって毎年支払われることになった。以降、那覇防衛施設局が、県内の土地価格の変動率調査や生産農業所得、材木価格等の統計資料を用いて土地の評価を行い、地主会との間で、単価交渉が行われている。交渉は、原則的には施設局職員が単価算定に当たっての考え方を説明する形で進められるが、地主会側からの要請・要望等を加味しながら最終的に決定される。また、算定は、取引事例比較法に従って、当該地が最有効利用された場合の水準で決定される。これに加え、復帰時の嵩上げ措置が慣例化したことも相まって、地料が下がることはない。最低で据え置きだという。
なお、半数以上の地主は年額100万円以下だが、中には年額1億円超の地料を受け取る者も数名いるという(表3参照)。
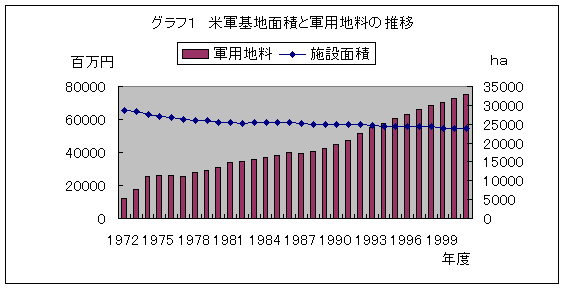
防衛施設局の資料(2002年8月24日取得)より筆者作成
表3 2001年度における軍用地料の支払額別所有者数(自衛隊分も含む)
|
金 額 |
割 合 |
所有者数 |
|
100万円未満 |
52.5% |
19,266人 |
|
100万円以上~200万円未満 |
20.9% |
7,682人 |
|
200万円以上~300万円未満 |
9.1% |
3,344人 |
|
300万円以上~400万円未満 |
5.3% |
1,933人 |
|
400万円以上~500万円未満 |
3.2% |
1,164人 |
|
500万円以上 |
9.0% |
3,305人 |
|
合 計 |
100.0% |
36,694人 |
那覇防衛施設局資料(2002年8月24日取得)
地主にも自立が求められている
沖縄戦以来、苦渋の生活を余儀なくされてきた軍用地主であるが、復帰を境にして状況は一変した。高額の軍用地料は、勤労意欲を減退させ、ぜいたくと豪遊の日々を過ごす者も少なくない。今日では、地主にとって軍用地は、打出の小槌と化している。それ故、若年層の雇用問題に拍車を掛けるばかりか、軍用地主を狙った詐欺や、親族間の相続争いが後を絶たない。
何よりも問題視すべきは、SACO合意の呼び水となった95年の「10・21県民総決起大会」に、土地連(県軍用地等地主連合会)が不参加を表明したことだろう。これまで、日本政府が軍用地料を確実に引き上げていったのは、強制接収への償いと日米安保体制への貢献度に対する感謝の想いからである。他方、沖縄に対して政府は、中央の財源に依存しない、「自立」した沖縄を求めてきた。それは、平和な県民生活を取り戻すことと並んで、沖縄が達成すべき課題であり続けている。経済振興を諮る上で、広大な平地を有する米軍基地は、重要な土地資源に他ならない。
2002年度より実施中である沖縄振興計画には、振興施策の一つとして「駐留軍用地跡地利用の推進」が挙げられている。また、都市計画法第三条・第二項には、住民の責務として「都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的[7]を達成するため行う措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなければならない」とある。基地返還が県民多数の悲願であるにもかかわらず、返還それ自体を拒むようでは、まちづくりの視点において、土地連に公共性を唱える資格はない。
そろそろ、軍用地主にも「沖縄の自立」に貢献してもらう時期が来ているようである。
返還を見据えて
現在の地料水準に見合った収入さえ確保できれば、地権者は容易に返還を受け入れるだろう。だが、資本主義国である日本では、政府が返還後の地主の生活を補償することなど認められない。加えて、既存の都市計画の区画整理事業手法では、全ての地権者の要求に対応できるだけの換地は、技術的に不可能である。それならば、土地の持つ財産性を確保しつつ、運用において地権者の主体的な判断を可能にするような、より柔軟性のある制度を構築することに焦点を置くべきではないか。
これに関して、沖縄国際大学の来間泰男教授が興味深い研究を行っているので、以下に紹介することで、本稿の結びとしたい。
「手順としては、次のようなことが考えられる。全ての対象(民有)地を公共で買い上げる。地籍の確定はせず、これまでの軍用地料を「軍用地料を受け取ることのできる債権」とみなして処分する。その一部は債券の形にしてもいい。住宅や貸し住宅の用地を求める地主には、買戻し特権として、この債券を引き渡す。商業用地に付いても希望があれば、同様に扱う。しかし、土地はいったん全てを公共で買い上げる。一つのねらいは地籍の確定作業を省略して、その利害調整のためのエネルギーと時間を省略することにある。そして、跡利用についても公共主導で進めるということである。あたかも真っ白な台紙に好きなように絵を描くことを可能にすることである[8]」。
なお、同教授によれば、買い上げ価格は、現在の地料水準を基礎に決定される。また、買戻しのための債券を希望する地主には、通常の減歩率を適用し、特に商業用地の買戻しであれば、それより高い減歩率を適用して、予めその分を差し引いておくという。
債券であるから譲渡が可能となり、従前に比べて流動性を持った資産となる。加えて、減歩率が差し引かれるので、地主は決して優遇された状況にはない。不動産にこだわらず、債権化するという来間教授の視点は、公共性を有した街づくりを推進するにあたって、十分に検討する価値があるだろう。
一方で、普天間飛行場のような大規模跡地における財源の問題や、買い上げに応じない地主への対応など、まだまだ研究の余地はある。これについては、今後の課題として取り組みたい。
参考文献
沖縄県『沖縄の米軍基地』2003
沖縄県『沖縄の米軍基地及び自衛隊基地(統計資料集)』2003
沖縄国際大学公開講座Ⅳ『沖縄の基地問題』ボーダーインク、1997
来間泰男『沖縄経済の幻想と現実』日本経済評論社、1998
防衛施設庁『防衛施設庁関係法令集』1991年度版
那覇防衛施設局広報「はいさい」各号
その他、関係機関で取得した資料