�����̃}�l�W�����g�c�[���Ƃ��Ă̍s���]���̂�����ɂ���
�������x���KB�@2006.10.26
�����o�c�����ȁ@�c�� �ƕF
�͂��߂�
�n�������̂ł́A�\�Z�𒆐S�Ƃ����s�����^�c�̒��ŁA�ǂꂾ���̗\�Z��E���𓊓������̂��A�ǂꂾ���̂��Ƃ����{�����̂��ɂ��ċc�_���邱�Ƃ������B�������A�Z���̎��_���猩��A�����ɁA�ǂꂾ���̐��ʂ��������̂����d�v�ł���B�Ⴆ�A���H�̌��݂ɂ����ẮA�\�Z���g���ĘJ�͂Ǝ��ނ𓊓����H�����s���B�����ē��H���������A�Z�������p����B�Z���̗��ꂩ�猩��ƁA���ւ����サ�����Ƃ��d�v�ł���A�����ē��H�̊������̂��d�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��B
��ʂɁA�s���]��[1]�ɂ����ẮA�����{��A���Ƃ��A�C���v�b�g�iInput, �����j���A�E�g�v�b�g�iOutput, ���ʁj���A�E�g�J���iOutcome, ���ʁj�Ƃ�����A�̗���łƂ炦�A�A�E�g�J���Ƃ����T�O���d������B��قǂ̓��H�̌��݂̏ꍇ�ɂ����ẮA�u�J�͂⎑�ށv���C���v�b�g�A�u���H�̊����v���A�E�g�v�b�g�A�u���ւ̌���v���A�E�g�J���ƂȂ�B�s���]���@[2]��O���ꍀ�ł́A����̌��ʂɂ��āu����Ɋ�Â����{���A���͎��{���悤�Ƃ��Ă���s����̈�A�̍s�ׂ����������y�юЉ�o�ςɋy�ڂ��A���͋y�ڂ����Ƃ������܂��e���v�ƒ�`���Ă���B�����ȍs���]���ǂ́A���́u�e���v���A�E�g�J���ɓ�����Ƃ��Ă���B
�A�E�g�J���́A�s���̊����̌��ʁA����������Љ�o�ςɋy�ڂ���鉽�炩�̕ω���e���Ƃ��āA��̓I�ɂ́A�s���T�[�r�X�ɑ��閞���x�A�u�K��̎�u�ɂ��m����Z�\�̌���A�������ꂽ���҂̋~�����A�J���r�㍑�ɂ����鋳�琅���i�������A�A�w���j�A��C�A�����A�n���̉����x�Ȃǂ̎w�W�ɂ��\���ł���B
����A�A�E�g�v�b�g�̎w�W�́A�A�E�g�J���̎w�W�ȊO�̂��́A�܂�s���̊������̂��̂�s�������ɂ����ꂽ���m��T�[�r�X���̂��̂Ȃǂł���B��̓I�ɂ́A���Ƃ̎��{�����A��c�̊J�Ð��A�u�K���W����̊J�ÉA�������̎x�������A�p���t���b�g�̔z�z���Ȃǂ̎w�W������ɓ�����B
�������A�{�Ȃ̍l�����ɂ��A�����Ȃ̒�`��A�E�g�v�b�g�̎w�W�ɕ��ނ������̂��A�E�g�J���̎w�W�Ƃ��ėp����P�[�X������B�����Ȋw�Ȃł́A���S�������y�я�Q�������̎x�������ɂ��āA�w�Z�ɂ����鎀�����̂̔��������������ނː��m�Ɏ����A�w�Z�̈��S�m�ۂ̏�\�����̂Ƃ��āA�A�E�g�J���̎w�W�ɕ��ނ��Ă���B
�܂��A�_�ѐ��Y�Ȃł́A��Ђ����{�ݓ��̕����ɌW����Ԃɂ��āA�����w�͂̌��ʁA�ǂꂾ���Z���Ԃɍ������T�[�r�X���邱�Ƃ��ł������Ƃ������ʂ�\�����̂Ƃ��āA�A�E�g�J���̎w�W�Ɉʒu�Â��Ă���B�����̎Љ�ɂ́A�A�E�g�v�b�g�̎w�W�ƃA�E�g�J���̎w�W�Ƃ������ɋ敪���邱�Ƃ�����ł��銈�������݂��Ă���B
�s���]���ɂ����ẮA���Ƃ̌��ʂɂ��đ���܂��͕��͂��A���̎ړx�ɏƂ炵�ċq�ϓI�Ȕ��f���s���A�V���Ȋ�旧�Ă₻��Ɋ�Â����{��I�m�ɍs�����ƂɎ�����������B�܂��A�Z���ɑ�������ӔC�i�A�J�E���^�r���e�B�j���ʂ������߂ɂ��A�s���]���͗L���Ȏ�i�ƂȂ��Ă���B�Z���̐M���邽�߂ɂ́A�n�������̂�����ڎw���ĉ������悤�Ƃ��Ă���̂��A�����Ăǂꂾ���̐��ʂ������炵���̂��ɂ��āA�����I�ɐ������Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł���B
�������Ȃ���A�����Ȃ��ݒu�����u�����^�Љ�ɑΉ������n���s���g�D�^�c�̍��V�Ɋւ��錤����v���Ƃ�܂Ƃ߂��ŏI��[3]�ł́A�n�������̂̍s���]���ɂ��āA�s���]���̓������̂͒����ɐi��ł��邪�A�K�������{���̎�|�ɉ����ėL���ɋ@�\���Ă���Ƃ͂����Ȃ���������ƕ��͂��Ă���B���́A�s���]�����x�̓����̎�|�ɍ���Ȃ�����������̂��A�A�E�g�J���Ƃ����w�W�ɒ��ڂ��A���̌����ɔ��肽���B
��1�� �n�������̂̍s���]���̌���Ɖۑ�
��1�� �n�������̂ɂ������g��
�����Ȃ�2006�N4���Ɍ��\������������[4]�ɂ��A���挧������46�s���{���A14���ߎw��s�s�i���ׂĂ̐��ߎw��s�s�j���s���]�������{���A���j�s�ł�87���A����s�ł�90���̎��{���ƂȂ��Ă���B���̓��A���ʂ̊��p���@�ł́A�u�\�Z�v���⍸��Ɋ��p�v���Ă���c�̂̔䗦���s���{��98���i�a�̎R��������45�s���{���j�A���ߎw��s�s100���A���j�s�\�Z97���A����s92���ł���B�ŋ߂̌X���Ƃ��ẮA�]�����ʂɁu�Z���ӌ��f������d�g�݁v��������Ă��鎩���̂��������A�s���{��59���A���ߎw��s�s64���A���j�s33���A����s21���̒c�̂ƂȂ��Ă���B
�Ȃ��A���挧�̕ЎR�P���m���́A�O�H�����������̃C���^�r���[�ɂ����āA�s���]�������{���Ȃ����R�ɂ��āA���̂悤�ɘb���Ă���[5]�B
�u�{���̍s���]���́A���̐����������Ɠ_�����āA�ŋ��̎g�����Ƃ��Ăӂ��킵�����ǂ����A�D�揇�ʂ��ԈႦ�Ă��Ȃ����ǂ������`�F�b�N���Ȃ��Ă͂����܂���B����͖��N�\�Z�Ґ��ł���Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ɁA�قƂ�ǂ̒n�������̂ŁA���̓_����ӂ��Ă���̂ł��B�V�[�����O�Ƃ����̂�����܂�����A���������Ȃ��ő��ʋK����������Ă���Ƃ��B���挧�́A�\�Z�œ_����������Ƃ��܂��傤�Ƃ������ƂŁA�������Ƃ͈�{���S���`�F�b�N���Ȃ����A����ɂł������s���Ȃ����Ǝw�����Ă��܂��B����ł��ꂪ�K�v���K�v�łȂ����A���ʂ����邩�Ȃ����Ƃ����̂�������悤�ɂ��Ă���̂ł��B�c��ɂ��č��ψ��ɂ��_���𗊂݂܂��B�{���ŋ��̎g�������`�F�b�N����X�e�b�v������������̂ɁA�����̎����̂͂�����Ƃ���Ă��Ȃ��̂ł���B�s���]�������Ȃ�A���_�ɂ������Ēm���͍������ǂ���g���Ė��ʂȂ��̂�r������A���������V�X�e���ɂ��ׂ��ł��B��Ԃ̍s���]���́A�\�Z�̍���ߒ��A�R�c����ꂾ�Ǝv���܂��B������O��I�ɂ��ׂ����Ǝv���܂��B������c��̐l�B���\�Z�R�c�̎��ɁA�s���]���̎�@������Ƃ����̂Ȃ�A���͑�^���ł��B�v
�{���A�ŋ��̎g�������`�F�b�N����\�Z�Ґ��ȂǂŁA�c��̎�ɂ���ēO��I�ɕ]�����s���̂ł���ΈӖ��͂���B�������A���̍s���]���͂���u���萷��v�ł��邽�߁A�]���̈Ӗ����Ȃ��Ƃ������Ƃł���B
��2�� �u�����^�Љ�ɑΉ������n���s���g�D�^�c�̍��V�Ɋւ��錤����v��
2005�N3���̑�2�� �u�����^�Љ�ɑΉ������n���s���g�D�^�c�̍��V�Ɋւ��錤����v�ŏI���̒��ł́A�����̍s���]���̌���ɂ��āA���̂悤�ɋL����Ă���B
�u�n�������̂̍s���]���ɂ��āA���ƒS���ێ��g�̉��l���f�Ɉˋ������]���ɑ���M�����̌��@�A�c��Ȑ��̎������Ƃ�]���ΏۂƂ��邱�Ƃɂ��A�������đS�̂̑̌n�̒��ł̈ʒu�Â��A�D�揇�ʂ����f���ɂ����Ȃ邱�ƂȂǂ���A���x�����̈Ӑ}�Ƃ͗����ɁA�]�����ʂ��\�Z��g�D�E�l���Ǘ��Ȃǂ̍s���̈ӎv����̒��j�ɂ����ď\���Ɋ��p���ꂸ�A����̈ӎ����v��{��E���Ƃ̉��P�̃c�[���Ƃ��Ă��L���ɋ@�\���Ă��Ȃ����Ƃ������A���̌��ʁA�]�����ʂ��}�l�W�����g�ɂ����Ċ��p���ꂸ�A�s���]�����s�����Ǝ��̂����ȖړI�����A�S���҂̕��S�����肪�������ƂɂȂ����Ă���B�v
�܂��A�u�s���]���̕������k������قǁA���̌��ʂ͐��I�œ���A���A�c��Ȃ��̂ƂȂ�A�Z����c���ɂƂ��ĕ�����ɂ������̂ƂȂ邱�Ƃ������B�}�l�W�����g�c�[���Ƃ��ėL���ɋ@�\���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�s���]�����̂��d�����ꂸ�A�Z���ɑ�������ӔC���ʂ����c�[���Ƃ��Ă̋@�\���s�\���ƂȂ炴��Ȃ��B�v�Ƃ����͂��Ă���B
�s���]���Ƃ����d�g�݂��K�ɉ^�p����Ă��Ȃ����Ƃɂ��A���ۂɂ��̌��ʂ���������Ă��Ȃ�����łȂ��A�u�A�J�E���^�r���e�B�̃W�����}�v[6]�Ƃ������錻�ۂ������Ă���B�S���̎����̂ɂ����āA��g���n�߂�ɂ͎n�߂����A�������{���Ă݂�ƁA�l�X�Ȗ�������Ă���Ƃ��낪�����̂ł���B
��3�� �s���]���̎O�̖ړI
���ł́A�s���]���̖ړI�ɂ��āA�u�s���̎{��A�������Ƃ̐��ʂȂǂ��q�ϓI��Ɋ�Â��Ĕc�����A�s�f�Ɍ������d�g�݂�ʂ��āA�p���I�Ɏ{��A�������Ƃ����P���A���ʒB���ɗL���Ȏ{��Ȃǂɏd�_�I�����ʓI�Ɍo�c�����i�\�Z�E�萔�j��z�����邱�ƂɎ�����ƂƂ��ɁA�Z���ɑ������ӔC���ʂ����A�������̍����s�����������邱�Ƃ���|�Ƃ��ē����������̂ł���v�ƋL���Ă���B
�����ł́APlan�i�v��j�|Do�i���{�j�|Check�i�]���j�|Action�i���P�s���j�Ƃ���������PDCA�T�C�N���ɂ��}�l�W�����g��ʂ��Ď{������P���A�����I�A���ʓI�Ȏ{��ւ̏d�_���Ɏ����鐬�ʎu���^�����^�c����������ƂƂ��ɁA�Z���ւ̐����ӔC���ʂ������Ƃ��ړI�ł���B�Ȃ��A���̐����]���̖ړI�́A�u�����ɑ���s���̐����ӔC���ʂ������Ɓv�A�u�����{�ʂ̌����I�Ŏ��̍����s�����������邱�Ɓv�A�u�����̎��_�ɗ����A���ʏd���̍s�����������邱�Ɓv�Ɛ�������Ă���[7]�A�ڎw���Ƃ���͂قړ����ƌ����Ă悢�B
��2�� ���ʎu���̍s���^�c
��1�� �O�d���������ƕ]���V�X�e���̈Ӑ}
�����̂ւ̍s���]���̓����́A1995�N�̎O�d���̎������ƕ]���V�X�e���Ɏn�܂�B���̍ہA�����O�d���̖k�쐳���m���́A�������ƕ]�����u����₩�^���Ƃ����w�����ҋN�_�x�̍s���^�c�v�̈�Ƃ��āA�\�Z���x���v��v��Â���A����ɂ̓A�J�E���^�r���e�B�Ɋ֘A�Â��Ă���B�u����₩�v�̓T�[�r�X�A�킩��₷���A���C�A���v�̓��������Ƃ��Ă���ꂽ���̂ł���B���̎��A�]���V�X�e���̐^�̂˂炢�́A�g�D���y�̉��v�A���Ȃ킿�E���̈ӎ����v��ڎw�����̂ł������B�]�������邱�ƂȂ���A�����̎d���̎d���̂���悤�����������߂̓���Ƃ��Ă̈Ӗ�����������A����܂ł͍l�������Ȃ��������Ƃ��l���n�߂�Ƃ������Ƃ��A�]�������̌��\�A�\�Z�Ґ��ߒ��̌��\�ւƑ����A����ɐi������g�D�����o���A�q�G�����L�[�̑Ŕj�A�c����s����ł��j�낤�Ƃ����C���Z���e�B�u�Ɍ��т����̂ł���[8]�B
��2�� �A�E�g�J���u���̎����̉^�c
�@�]���i�v���O�����]���j�ɂ����ẮA�܂��A����A�{��̖ړI�Ƃ��̎�i�Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă��鎖�ƂƂ̊W��}�����Đ�������B����̓��W�b�N���f���ƌĂ�A�X�̎��Ƃ��ǂ̂悤�Ɋ֘A�������āA�ŏI�I�ɖڎw���ׂ����ʂɌ��т��Ă������Ƃ����o�H��͎��I�Ɏ��������̂ł���B�Ⴆ�A����r�㍑�Ŏ�������30�����P���邽�߂ɏ��w�Z���݂Ƃ��̉^�c���s���ꍇ�̃C���v�b�g�i�����j�|�A�E�g�v�b�g�i���ʁj�|�A�E�g�J���i���ʁj�̊W���������W�b�N���f���́A�}�P�̂Ƃ���ł���B
�y�}�P�z
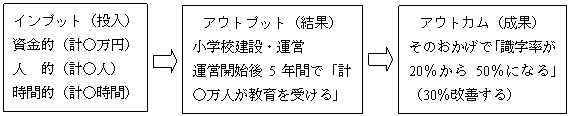
�o�T�F���@�c���A���X�@�� (2004)�����Ƃɍ쐬
�C���v�b�g�Ƃ��āA�����I�i�v�����~�j�A�l�I�i�v���l�j�A���ԓI�i�v�����ԁj�Ȃǂ̃v���O�������{�̂��߂ɓ�������鎑������������A�A�E�g�v�b�g�Ƃ��āA�^�c�J�n��5�N�Ōv�����l���������Ƃ������ƂɂȂ���A�A�E�g�J���Ƃ��āA��������20������50���ɂȂ�i30�����P����j�Ƃ������ʂ������炷�̂ł���[9]�B
��3�� �A�E�g�J���u���ɂ��ړI�̖��m��
�����Ō������ɂ��čl����B�������́A�ʏ�A�C���v�b�g�i�����j�̗ʂƁA�A�E�g�v�b�g�i���ʁj�Ƃ̔䗦�i�A�E�g�v�b�g���C���v�b�g�j�ɂ���Ď������B���̎x�o�z�Ɛ��Y����T�[�r�X�Ƃ̊W�������P�ʔ�p�䗦�́A����܂ōL���g�p����Ă����B�������A���̎w�W�̖��_�́A���Y����T�[�r�X�̎��𗎂Ƃ����ƂŐ��l�����P���邱�Ƃ����蓾�邱�Ƃɂ���[10]�B
�Ⴆ�A�u�։��v���O���������Z���i�i���ҁj�ЂƂ肠����̔�p�v�́A�������̎w�W�ł���B���̏ꍇ�A���Ƃ����ʂƂ��ċ։��������サ�Ȃ��Ă��A�ЂƂ肠����ɔ�₳���C���v�b�g�̗ʂ����Ȃ��Ȃ�Ό������͌��シ��B
����ŁA�u�։��v���O�����������ʁA�։������Z���i�i���ҁj�ЂƂ肠����̔�p�v�́A�A�E�g�J����p�����������̎w�W�ł���B���Y����T�[�r�X�̎��𗎂Ƃ����ƂȂ��A�������������A��萳�m�Ȏw�W����ɓ���邱�Ƃ��ł���B
���݁A���߂��Ă���A���邢�͊e�n�œ������i�߂��Ă���s���]���ɂ́u�s�������̌��ʁA�Z������݂āA�����ɐ��ʁi�A�E�g�J���j�������������v�A�u����ꂽ�\�Z�E�����Ȃǂ̍s�������̂��ƂŁA�����ɏZ���ɂƂ��Ă��悢�����T�[�r�X����Ă��邩�v�Ƃ��������_���d�v�ł���B����͌��t��ς��Ă����A���̂��߂ɍs���]���Ɏ��g�ނ��A���̖ړI�m�ɂ��邱�Ƃł���[11]�B�A�E�g�J���������u�����邱�Ƃɂ���āA���̐���A�{��A���Ƃ̖ړI�����m�ɂȂ��Ă���B
�����ɁA���������A�E�g�J���ő��肷�邱�Ƃɂ��A�A�E�g�J������Ɏ����邱�Ƃ̂Ȃ��{��A���Ƃ͂��������K�v�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B�ނ��Ȏ{��⎖�Ƃ�p�~�A�x�~���邱�Ƃɍs���]���Ƃ����d�g�݂��g���闝�R�������ɂ���B
��4�� �A�E�g�J���u���ɂ��n�������ӎ�
�A�E�g�J���́A���N����S�A����A�ٗp�A�����A���������ȂǁA�Z���̏�Ԃ̂��Ƃ��w���B�����čs���T�[�r�X�̒ɂ����ẮA�ŏI�I�ɂ��̃T�[�r�X�����Z���̖����x���A�E�g�J���ƂȂ낤�B�A�E�g�J�����u�����A�Nj����邱�Ƃɂ��A�u���������Z�������͂ǂ̂悤�ɒB�������̂��v�A�u�Z���̍K���Ƃ͉����v�Ƃ��������ɑ������邱�ƂɂȂ�B
�����L���ɂȂ�ɂ�āA���̖L��������S�̖L���������߂鎞��Ɉڂ�ς���Ă����B�����āA����܂Œn��P�ʂ�Ƒ��P�ʂŕ������������K���▞�����A�l�P�ʂɈڂ�ς��悤�ɂȂ�A�������߂��鉿�l�ς͋ɂ߂đ��l�����Ă���B�K���▞���́A�Ƒ���F�l���ǂ��ł���Ō�͌l�̖��ƂȂ�B���̂��Ƃ܂���A�s���T�[�r�X�́A�Z���̃j�[�Y�ɉ����āA�Z�����g�̈ӎu�ƐӔC�ɂ�鎩��I�ȑI���Ɋ�Â�����邱�Ƃ��{���̂�����ł��낤�B
���@92���ɋK�肷��u�n�������̖{�|�v�́A��ʂɁu�c�̎����v�Ɓu�Z�������v�̓�̗v�f����Ȃ�Ƃ���Ă���B�n���������������邽�߂ɂ́A������Ɨ������c�̂�݂��A���̒c�̂̌����ƐӔC�ɂ����Ēn��̍s������������u�c�̎����v���K�v�s���ȗv�f�ł���B�������Ȃ���A������Ɨ������n��c�̂ł��鎩���̂����݂��Ă��A�u�Z�������v�̗��O�ɑ���A���Y�c�̂̐�����s���ւ̏Z���̎Q���E�Q�悪�\���ɍs���Ȃ���A�Z���̂��߂̒n���s���̎����͍���ł���[12]�B
�A�E�g�J�����u������s���]���̎�����ʂ��āA�����̐E���́A�����ɍ�����Ɨ������n��c�̂ł��鎩���̂����݂��c�̎����̌������т��Ă��A�Z���̃j�[�Y���\���ɔc���ł��Ȃ���A�Z���̂��߂̍s���̎����͍���ł���A�c�̎����ƂƂ��ɁA�Ԃ̗��ւƂȂ��ďZ���������@�\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ���������B�A�E�g�J���̌�����ŗD��ɍl���A�Z���̎��_�ɗ����A����̎{��A���Ƃ����߂邱�Ƃɂ���āA�n�������̖{�|���l���邫�������ƂȂ�̂ł���B
����ɁA�s���]���̑ΏۂƂȂ�{��A���Ƃ̍����ɍ��ɕ⏕�����܂܂�Ă���ꍇ�A�����̐E���́A�⏕���x�̕s��������������B�Z���̑��l�ȃj�[�Y�̗v���ƍ��̑S���ꗥ�ȕ⏕���x�Ƃ́A�����ΏՓ˂��A���I�ɂȂ肪���ȃ��[���̂��ƁA������Ɨ������n��c�̂Ƃ��Ă̒c�̎����̌������т����ƂƂ͉����A�Ƃ������Ƃ�����邩��ł���B�A�E�g�J�����u�����邱�Ƃɂ��A�n�������̈ӎ��������Ȃ�̂ł���B
��3�� �A�E�g�J���̌��E
��1�� �A�E�g�J���𑪒肷�邱�Ƃ̌��E
�A�E�g�J���u���E�d���́A�s���]���ɂ����ċɂ߂ďd�v�ł��邪�A�A�E�g�J���w�W�̑���͗e�Ղł͂Ȃ��B�Ⴆ�A�A�E�g�J���͑z��o���邪�A���l�ł͕\���Ȃ��ꍇ������B�����̂̓d�q���A���i�߂邱�Ƃɂ���čs�������̌�������}�鎖�Ƃ̏ꍇ�A�A�E�g�J���͖��m�����A����ڑ���肾�Ă͓���B���̂悤�ȏꍇ�A���ʂ̈ꕔ�ł����Ă����l�ő�����̂��w�W������i�Ⴆ�A����̒����葱���ɗv���鎞�ԂȂǁj�A���Ƃ̑Ώێ҂�ΏۂƂ���A���P�[�g���s���i�E���A���P�[�g�����{���ċƖ��ɂ�����IT���p�x��₤�j�ȂǁA���ʂ���ł��A�E�g�J���𑪂�H�v���K�v�ƂȂ�[13]�B
�܂��A�A�E�g�J������������̂Ɏ��Ԃ�������ꍇ������B�Ⴆ�n�[�h���ƁA���H��{�݂����݂���A��搮�����s���Ƃ����������Ԃ�v���鎖�ƂŁA�{���̃A�E�g�J�����Z���I�ɂ͌v���ł��Ȃ����̂�����B���̂悤�Ȏ��Ƃ̏ꍇ�A�H���̏I���܂Ŗ{���̐��ʂ𑪂邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁A�N�x���ƂɎ��Ƃ̕]�����s���ꍇ�A���炩�̍H�v���K�v�ł���B�H���ɔ��������A���邢�͎{�݂Ȃǂ����������p����邱�Ƃ̔F�m�x����ғx�ő�p����ȂǏZ��������\�����炩�̎w�W���K�v�ł���B
����ɁA�A�E�g�J���͑Ó����ɂ����ăA�E�g�v�b�g��������̂́A�M�����ɂ����Ă͗���Ă��邱�Ƃ�����B�Ⴆ�A���H���ݎ��Ƃ̏ꍇ�A�A�E�g�v�b�g�Ƃ��āu���H�{�s�����L�����v�A�A�E�g�J���Ƃ��āu�ג��ւ̏��v���ԁv���l���Ă݂�B�A�E�g�J���̑Ó����ɂ��Ă͖��Ȃ����A���v���Ԃ̌v���͎��ԑсi�ʋΎ��ԑт�����ȊO���j��j���i�������x�����j�A�V��i�D�V���J�V���j�Ȃǂɂ��قȂ��Ă��邽�߁A�M�����ɖ�肪�����B���������āA�A�E�g�J���w�W�ɂ͐M�����ɖ�肪���邱�Ƃɗ��ӂ��A�w�W�쐬�ɂ�����f�[�^���W�Ȃǂ̎�@�ɂ����ӂ��K�v������[14]�B
��2�� �A�E�g�J���ƃA�E�g�v�b�g�̈��ʊW����̌��E
�����{��A���Ƃ���͈��̐��ʂ������邪�A���̐��ʂ̂��ׂĂ��g�D�̊����ɂ����̂Ƃ͌����Ȃ����Ƃ���A�A�E�g�v�b�g�ƃA�E�g�J���Ƃ̈��ʊW�𖾂炩�ɂ��邱�ƂɌ��E������B�Ⴆ�A���T�[�r�X��1000�l�̗v���҂ɏT3��̃T�[�r�X���s���Ƃ���B���̃T�[�r�X�i�A�E�g�v�b�g�j����������̂ɕK�v�ȃz�[���w���p�[�͉��l�ł���Ƃ��A���{�݂̋K�͉͂������Ȃǂ͌v�Z�\�ŁA�K�v�ȗ\�Z�z���Z��ł���B�Ƃ��낪�A�Q������V�l��2�����炷�i�A�E�g�J���j���߁A�K�v�ȃz�[���w���p�[�͉��l�ł���Ƃ��A���{�݂̋K�͉͂������Ȃǂ͍����I�ɎZ�肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ�[15]�B
�܂��A��������_�Ō�ʎ��̂�3���N���Ă����Ƃ��낪�A�J�[�u�~���[��ݒu������������1�����N���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��������ꍇ�A���̌����_�ɂƂ��ăJ�[�u�~���[��ݒu�������ƂɌ��ʂ��������Ƃ������ƂɂȂ邩������Ȃ��B�������A����ŁA���̒n��̏��w�Z�ň��S���炪�d�_�I�ɍs���Ă����Ƃ������Ƃł���A���̂ǂ���̌��ʂ��オ�������Ƃ������Ƃ𐄑�����͓̂���B��ʎ��̂́A���̐��i��A�����I�Ɋm���߂�悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ�����ł���B�A�E�g�v�b�g�ƃA�E�g�J���̊W�͂���قNJȒP�ɂ͌��т��Ȃ��̂ł���[16]�B
��3�� �A�E�g�J�����݂̗D�揇�ʐݒ�̌��E
�s���T�[�r�X�́A����̌���ꂽ�ړI��W�c�ɓ��������^�c���s�����Ƃ�����B���̂��߁A�����s���{��̗̈�Ԃő�������A�E�g�J����Nj����邱�Ƃ���������B
�Ⴆ�A�H��U�v�ɂ��Y�ƐU����𐄐i����ƁA����ŁA�������̈����ɂ�������U�����A�������̌���Ƃ����悤�ȕʂ̃A�E�g�J���Ƒ��Η�����B���邢�́A�ǍD�ȏZ����𑣐i���邽�߂ɑ�n������i�߂�A�_�n��R�т̊J�����K�v�ƂȂ�A�_�Ƃ̐U����R�їΒn�̕ی�̂悤�ȕʂ̃A�E�g�J���ƑΗ�����[17]�B�قȂ�̈�Ԃł̃A�E�g�J���̗D�揇�ʂ�ݒ肷��K�v�ɔ�����̂ł���B
�]���́A�قȂ�̈�Ԃł̗D�揇�ʂ̐ݒ���s�����Ƃ�����B���W�b�N���f�����A���̉��l�̎����Ɍ�������i�Ƃ��č\������A���̍���Ɉ��̗��O�≿�l�������Ă��邽�߂ł���B�قȂ�̈�Ԃ̗D�揇�ʂ̐ݒ�́A�قȂ鉿�l�̊Ԃ̃E�G�C�g�t�������Ă���B���̍�Ƃ́A�q�ϐ��������獂�߂��Ƃ��Ă������ł�����̂ł͂Ȃ��B��ʓI�Ȍ����Ƃ��āA�u�]���v�́u�ӎv����v�ɑ�ւ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���ɁA���l�ς̑Η�����������Ƃ����@�\�́A�����ŗL�̗̈�Ɉʒu������̂ł���A������]���̋q�ϐ������߂��Ƃ��Ă��s�\�ł���[18]�B
��4�� �A�E�g�J���̌��E�Ɛ����ӔC�̓O��Ƃ̕s�e�a��
�����ӔC�i�A�J�E���^�r���e�B�j�Ƃ́A����������ƌo�c�҂Ȃǎ����̎���҂͊�Ɗ����ɂ����鎑���Ǘ��̐ӔC�����A���̗��s���q�ϓI�ɐ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����`���E�ӔC�̂��Ƃł���[19]�B�����J�ⓧ�����ȂǂƊ֘A���Ďg���邪�A����I�ȈႢ�́A�u�ӔC�v�Ƃ����v�f�������Ă��邩�ǂ����ł���B
�����J�ⓧ���������߂�ꍇ�́A�������ɂ���A�m�点�邱�Ƃɏd�_���u����Ă���B���Q�W�҂����߂�������J����A���邢�͓���̗����E�Ƃɂ���l���������������A��{�I�Ɋ�������B
�����������ӔC�̏ꍇ�́A���������łȂ��A���ʂɂ��ĐӔC�����Ƃ܂ŋ��߂���B���e�I�ɕs�\���Ȑ��������s�킸�A���ʓI�ɋ��K�I�ȑ����⑹�Q��^������A���_�I�ȃ_���[�W��^�����肵���ꍇ�A����������K�v������ƍl������B
���݁A�����̂̍����́A����߂Č������ɂ���B�i�}�Q�j
���R�A�����ӔC�̓O�ꂪ���߂��A�s���]���̍X�Ȃ�O�ꂪ���߂��Ă���B���͐��x�̌����A�w�W�E�f�[�^�̒~�ρA�A���P�[�g�����Ȃǂ��v������A���ۂɁA��i�I�Ȏ����̂ł́A�D�搫��]��������g��[20]�▞���x���̂��̂𑪒肷����g��[21]�Ȃǂ����{����Ă���B
�y�}�Q�z
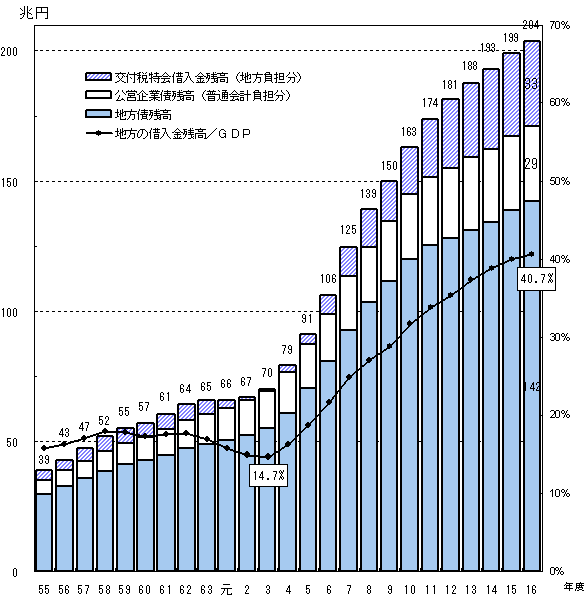
�o�T�F�n�������̎ؓ����c���̏i�����ȃz�[���y�[�W���j
�������Ȃ���A���x�̍����]�����s���ɂ́A����ɔ�����p�Ǝ��Ԃ��K�v�ɂȂ�B�����ɁA���I�ȕ��͂��K�v�ƂȂ邪�A�����̎����̂ł́A�]���ɌW��m�����K�������E���͏��Ȃ��B�����ӔC��O�ꂷ�邱�Ƃ��K�v�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł��邪�A������������w�i�ɁA���ԓI�E�\�Z�I�ɂ�������A�s�\���ȕ]���ɂȂ炴��Ȃ��̂�����ł���B
�܂��A�s���]���̕������k���������قǁA���̌��ʂ͐��I�œ���A���A�c��Ȃ��̂ƂȂ�A�Z���ɂƂ��ĕ�����ɂ������̂ƂȂ邱�Ƃ������B���I�Ȓ�����E���͂́A���R�A�K�v�Ȃ��Ƃł͂��邪�A���ƂɂƂ��ėL�Ӌ`�ȏ��́A�K�������Z�����������₷�����̂ł͂Ȃ��B�����ӔC���ʂ������߂ɂ́A������₷���������쐬����w�͂����߂���B�����āA�����̎����̂ɂ����āA�S���I�ɕ]�������{���A�S����̐E�����]���\�̍쐬�ɒǂ��邱�ƂɂȂ�B���ʂƂ��āA�s���]�����s�����Ǝ��̂����ȖړI�����A�S���҂̕��S�����肪�������ƂɂȂ����Ă���B
��4�� �����̐E�����ȃ}�l�W�����g�c�[���Ƃ��Ă̍s���]���̊��p
�s���]���̖ړI�́A�u���ʏd���̍s�����������邱�Ɓv�u�s���̐����ӔC���ʂ������Ɓv�u�����I�Ŏ��̍����s�����������邱�Ɓv�ł���B��������s�����̎��_�ɗ������\���ƂȂ��Ă���B�Z���̎��_�ɗ�����ڂ��A�Z���̗��ꂩ�猩�������Ƃɂ��A�s���]���������̐E������̃}�l�W�����g�c�[���Ƃ��Ċ��p���邱�Ƃ��Ă������B
��1�� �u���ʂ��d������v����u�Z���������d���������𑣂��v�c�[���Ƃ��Ă̊��p
�A�E�g�J���ƃA�E�g�v�b�g�Ƃ̈��ʊW����肷�邱�Ƃɂ͌��E������B�A�E�g�J���ɉe�����y�ڂ��v�������ɑ������݂��邩��ł���B�X�̎���͂���A���܂��܂ȏZ�������▯�Ԋ������A�E�g�J���ɉe����^���Ă��邱�Ƃ��킩��B�����̂ƏZ���A���ԂȂǂ����͂��Ȃ���ΖڕW���B���ł��Ȃ����R�������ɂ���B
�Ⴆ�A���N�̔�s�h�~��ɂ�����[�����ƂƂ��āA�p���t���b�g��|�X�^�[���쐬����ꍇ�A�ڕW�Ƃ��ׂ��̓p���t���b�g�̍쐬�����ł͂Ȃ��A��s�̌��������炷�Ƃ����A�E�g�J���ł���B�A�E�g�J�����ӎ������c�_���o�āA���N��s����̓I�Ɍ��炷���߂ɂ́A�Ⴆ��NPO�ƘA�g������s�h�~�v���O�����Ɏ��g�ނƂ�������̓I���Ƃ̒��z�����܂�Ă���[22]�B
�܂��A�a�̉����̓A�E�g�J���ł��邪�A�����ʋȂǂ̖��Ԃ�Z���̋��͂��Ȃ��ƒB���ł��Ȃ��B�a�̉�����ڎw���Ƃ��A����������ΐӔC�������̂ɋy�Ԃ��Ƃ���ŏ����珑���Ȃ��Ƃ����悤�ȓ`���I�Ȕ��z�����邪�A�����̂��ӔC�����ĂȂ����Ƃ͈�؏����Ȃ��Ƃ������z�ł́A�܂��߂Ɏ��Ԃ��킩�낤�Ƃ��Ă���̂��ǂ����A���ӂ̂ق����ނ���^��ꂩ�˂Ȃ�[23]�B
�X���̐���}�[�P�e�B���O�ψ���ł́A�V�F�A�h�E�A�E�g�J���ishared outcome�j�Ƃ����l�������̗p���Ă���B����́u�����ŒB�����ׂ����ʖڕW�v�Ɖ�����A���܂��܂Ȗ��Ԏ�̂̊������ŏI���ʂɉe����^���邱�Ƃ���A�ŏI���ʖڕW��B�����邽�߂ɂ́A�s���Ɩ��Ԏ�̂̑o���̊������s�����Ƃ���l�����ł���B���ɒ��ڂ��ׂ��́A���̍l�������u�������S�l�v�Ƃ������l�ɂ܂ŕ\���Ă��邱�Ƃł���B�@�l�E�ƒ�A�ANPO�E�s���c�́E�R�~���j�e�B�E������A�B��ƁE�_�����J�g�A�C�w�Z�A�D���̑��A�E�s�����A�F���A�G���̔��҂ŁA�ڕW�ƂȂ�A�E�g�J���S���A�Q���E�����𑣂��A����ɘA�g���Ēn����o�c���邱�Ƃ��u�����Ă���[24]�B
�����ŁA�]����Ƃɍۂ��A�W����Z���▯�ԂȂǂ��������݁A�ϋɓI�Ɉӌ����f���A�����E�Q��^�ŕ]�����s�����Ƃ��Ă���B�]���������쐬����ہA�Z���▯�Ԃ̕��Ɉꏏ�ɍ�Ƃɉ�����Ă��炤�̂ł���B��������A�Q��E�����������Ƃɂ��W�҂̐����X�g���[�g�ɐ��荞�ނ��Ƃ��\�ł���A�܂��Z���▯�Ԃ̎��_����̉��P��Ă����҂ł���B���W�b�N���f���ɂ��Ă��A�����̂̊��������łȂ��A�Z���▯�Ԃ̊������܂߂āA�W�҂��������č쐬���A���ʂ����F���������Ƃ��ł��A���R�ɃV�F�A�h�E�A�E�g�J���̈ӎ����萶����ɈႢ�Ȃ��B
��2�� �u�����ӔC���ʂ����v����u���������ߑI���𑣂��v�c�[���Ƃ��Ă̊��p
�A�E�g�J���̑���ɂ͌��E������B�����āA������������w�i�ɁA���ԓI�E�\�Z�I�Ȑ��傫���A�s�\���ȕ��͂ɂȂ炴��Ȃ��̂�����ł���B���̂悤�ȏŁA�s�\�������\���������Ȃ��܂܁A�]����Ƃ��i�߂A���_�����݉������A������傫�Ȗ�肪�����錋�ʂɂȂ��鋰�ꂪ����B�����āA�������ĕ]�����ʂɑ���Z���̐M�������Ȃ��邱�ƂɂȂ�B
���݂̎����̂̍s���]���̃z�[���y�[�W������ƁA�{��E���ƂɌW��]�����ʂ̈ꗗ�\�̌f�ځA���Ƃ̔p�~�〈�����̌����̌��\�Ƃ��������ʂ̌��\�ɂƂǂ܂�ꍇ�������B�]���̔��f��⌋�ʂɎ���v���Z�X�́A���\����Ă��Ȃ����Ƃ������̂ł���B
�Ⴆ�A�H��U�v�ɂ��Y�ƐU����ɂ��ĕ]������ꍇ�A�������̈����Ƃ����悤�ȕʂ̉e����������̂́A�Y�ƐU���Ƃ��������b�g�Ɛ����������Ƃ����f�����b�g�Ƃ̔�r�ɂ�蔻�f�����ꍇ�����낤�B�������Ȃ���A���Ƃ𐄐i����Y�ƐU�����ǂ̕]���ł́A�f�����b�g�ƂȂ鐶���������Ƃ����w�W�̔c���͕s�\���Ȃ��̂ɂȂ炴��Ȃ��B���̌��ʁA���f�ɏd�v�ȏ���\���ꂸ�A���_�E���_�����m�ɂȂ炸�A�Z���̗����A�I���ɂ����т��Ȃ����ƂɂȂ�B
���̏ꍇ�A�������̕ۑS��S��������ۑS���ǂ��]���ɉ���邱�Ƃɂ���āA�]���̕s�\�������J�o�[���邱�Ƃ��ł���B�����āA�����I�ŃI�[�v���ȕ]�����\�ƂȂ�B��t�́u��Â����ɓ�����A�K�Ȑ������s���A��Â���҂̗�����悤�w�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ�[25]�v�Ƃ���Ă���B������C���t�H�[���h�R���Z���g�ł���B
���̍l��������{�ɁA�s���]���ɂ����Ă��A�ň��̎��Ԃ��z�肵�A�s�\�������܂߂ĕ�݉B�������\���A��̓I�ɒ��J�ɐ������A�Z���̗������ŗD��ɂ���c�[���Ƃ��čs���]�������p����K�v������B�]����Ƃɍۂ��A���l�ς��قȂ�A�܂��͉��l�ς��Η����镔�ǂ̐E���̎Q��E�������x�[�X�ɁA�����ăf�����b�g�����邱�Ƃm�ɂ��邱�Ƃ��Ă���B
��3�� �u�����I�Ŏ��̍����s���v����u�o�ϓI�ʼn��l����s���v�c�[���Ƃ��Ă̊��p
�s���]���ɌW�钲���╪�͂̐��x���グ�邱�Ƃ͓��R�K�v�ł���B�������A���̌����⎿���A�E�g�J���w�W�Ƃ��Đݒ肷�邱�Ƃ́A�����I�ɂ͑�ϓ���B�]�����x�[�X�Ƃ������P������z�肷��A�T�[�r�X�̐������ǂ̒��x�ɐݒ肷��̂��A���l�ς̈Ⴂ�ɂ���Ĕ��f��������邩��ł���B�}�l�W�����g�T�C�N�����ɂ́A�ڕW�ݒ肪��ł��邱�Ƃ͗e�Ղɗ����ł���B�������A���E����A�E�g�J���w�W�ɂ��ڕW�ݒ肷�邱�Ƃ́A���肷�邱�ƈȏ�ɍ���ȍ�ƂƂȂ�B
���̂悤�Ȃ��Ƃ��c�_���Ă���Ԃɂ��A����͓����Ă���B�N�Ɉ�x�̕]���ł́A���݂̑�������̗���ɒǂ������A���Ƃ����x�̍����q�ϓI�ȕ��͂��\�ł������Ƃ��Ă����ǁA���X�ω�����Z���̃j�[�Y�ɉ������Ȃ��B�����āA����̃��`�x�[�V������������B���ɁA��U�]�������{��ɂ����ẮA���̕]�����������E�Œ艻���Ă��܂��A�R�X�g�k���̈ӎ������@���A�����{��̊g�[�Ɍ��т��₷���Ȃ�[26]�B�A�E�g�J���̌���ɂ��āA�萫�I�ɕ\���ł��Ă���ʓI�w�W�ŕ\���͓̂���B
���������āA�s���]�����}�l�W�����g�c�[���Ƃ��ċ@�\�����邽�߂ɂ́A�s���T�[�r�X��M�����A�m�����̍����w�W�ŕ]�����邱�Ƃ��挈�ƍl����B���̂��߁A�o�ϐ��ɂ��āA�R���g���[���\�������\�ȃA�E�g�v�b�g�̎w�W�ŕ\�����邱�Ƃ��A�܂��]���̑����ł���B���̎��A���̎w�W�݂̂�Nj�����ƁA�T�[�r�X�̎��̒ቺ�������炷�댯������B���̂��߁A�T�[�r�X�������߁A��Ƀ`�F�b�N���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̎����̂�ގ��������ԃT�[�r�X�ANPO�����ȂǂƂ̃T�[�r�X���x���̔�r�A�s���o�c�i�����㊈���̌��A�T�[�r�X���p�҂̐��̐ϋɓI�c���Ȃǂ�ʂ��āA�T�[�r�X���x���̌����s�����Ƃ��K�v�ł���B�]����Ƃɍۂ��A���痝���\�Ȏw�W���e���ʂ���W�߁A�����Ő������邱�Ƃ��ł���͈͂ŕ]���������쐬���邱�Ƃ��Ă���B
�]���́A�����܂Ŏ����̒S���҂Ƃ����u�l�v���s���Ă���B�����������ł��Ȃ��w�W�͎g�����ɂȂ�Ȃ��B�Z������̐M���Ǝ����̒S���҂̃������̉ɂ��߂ɁA�����̒S���҂̐������x����s���]���V�X�e�����K�v�ł���B
������
�m�o�l�iNew Public Management�F�V�����o�c�j�ɂ����v���i�މp���A�j���[�W�[�����h�A�I�[�X�g�����A�A�k�A�����J�Ȃǂł́A�]���w�W�Ƃ��āA�A�E�g�J���ƃA�E�g�v�b�g�̂ǂ�����d������̂��Ƃ����e���̗���ɂ���āA���̓K�p�͗l�X�ł���B�������A������̍��ɂ����Ă��A�A�E�g�v�b�g�͐���̎��s�ʂł̕]���ł���A���T�[�r�X���Y����ɋ߂�����̕]���w�W�ł���̂ɑ��A�A�E�g�J���͐���̌��ʂɑ���]���ł���A�������旧�Ă����ʋ@�ւ̕]���w�W�ł���[27]�B
���{�̎����̂̏ꍇ���A�A�E�g�J���w�W�Ɋ�Â��s���]���́A�������Ƃ�����ʂ̎{���x���Ŏ��{��������Ó����͍����B����́A�����ӂf���č쐬���A�����ɂ͓��R�����I�ȗv�f�������Ă悢����ł���[28]�B�S���҂��A�A�E�g�J���w�W�Ɋ�Â��s���]�����A���x��ۂ��s�����Ƃ́A�Z�p�I�ɂ������I�ɂ�����ł���B
�܂��A���ׂĂ̎��Ƃ�]�����邱�Ƃ́A�]���R�X�g��傫���㏸������B�ł�����萸�x�����߂邱�Ƃ����߂��邪�A�]���R�X�g�Ɛ��x�̓g���[�h�I�t�̊W�ɂ��邩��ł���[29]�B�]�����x�̉^�p�ɓ�����A�]���Ώۂ�I���̏�A�W�����Ď��{���邱�Ƃ��]�܂����B�������邱�Ƃɂ��A�����E���͂̐��x����荂�߂邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�Z����NPO�A���Ƃ̐��ƁA�]���̐��ƂȂǂɂ��O���ψ����݂��A��c��S�Č��J�̂��Ƃňψ���]���Ώۂ�I������A�]���Ώۂ̑I���ɍۂ��A�����̜̂��ӓI�ȉ^�p�������邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
�Ȃ��A�c���č��̊��p���L���Ȏ�i�ł���B�����E���͂ɌW��E����z�u���A���I�E�W���I�Ɏ��g�ނ��Ƃɂ��A�]���̋q�ϐ��Ɛ��x�����߂邱�Ƃ��ł���B�E���ɂƂ��Ă��]���̐��m�����K���ł���Ƃ��������ʂ�����A���̌�̐��s�ɂ����Ă����̌o���͑����ɖ��ɗ��ɈႢ�Ȃ��B
�Ō�ɁA�]�����Ƃ̑I�����邱�Ƃ́A�Z���̊S�̍�������A�Ⴆ�A�ЊQ�����������Ƃ��̖h�Б�A��t�s�������ƂȂ��Ă���Έ�Ñ�A�����߂��ۑ�ł�������ȂǁA���̎��X�ɒ��ڂ���Ă���{������]�����邱�Ƃ��\�ɂ���B���̂��Ƃ́A�}�X�R�~���̒��ڂ��W�߂邱�Ƃ��ł��A�ŏI�I�ɁA�]���̖ڕW�����m�ɂȂ�B�]�����O���̖ڂɐG��A�Z���̊S���W�߂邱�Ƃ��ł���A�E���̎��o����ɑ����A�����̎d���̎d���̂���悤�����������߂̓���Ƃ������_�ɗ����Ԃ邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���������āA�����܂ŏZ���ɐg�߂ł킩��₷�����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B
[1] �k�쐳�� (2003). �g�O�d�����v8�N�̋O���h
[2] �n���[�EP�E�n�g���[ (2004). �g�����]�������h �i���G�A���^��q��j, ���m�o�ϐV���
[3] �R�J���u (2006). �g�����]���̎��H�Ƃ��̉ۑ��h, �G���[
[4] ���@�c���A���X�@�� (2004). �g��������Łu�����]���v�̗��_�ƋZ�@�h, ����o��
[5] ����B��A�c����q (2001). �g�s���]���n���h�u�b�N�h, ���m�o�ϐV���
[6] �R�c���� (2004). �g�����̍s���]���w�W�̈Ӌ`�ƌ��E�h, ����������2004. 9
[7] ����@�� (1999). �g�킩��₷�������̂̐����]���h, �w�z���[
[8] �R�{�@�� (2000). �g�����̌o�c�Ɛ����]���|���ɓI�ڋq��`���z����NPM���|�h, ���l�̗F��
[9] ��Z䵎l�Y (2002). �g�p�u���b�N�E�}�l�W�����g�\�헪�s���ւ̗��_�Ǝ��H�\�h, ���{�]�_��
[10] �c粚��� (2005). �g�����Ȓ��ɂ����鐭���]���̌���Ɖۑ�\���҂Ǝ��]�̃X�p�C�������z���ā\�h, ����`���x���̂��߂̐����]��, ��2�͑�1��, ���������J���@�\
[11] ��R�M��A�Ɋ֗F�L (2003). �g�����̍Đ��헪�h, ���{�]�_��
[12] ��R�M�� (1998). �g�u�s���]���v�̎����h, NTT�o��
[13] �E�c�D�j (2005). �g���{�^�����]���Ƃ��Ă̎������ƕ]���h, ���{�]�_��
[14] �F��L�q (2005). �g�m�o�l�Ɛ����]���`�s�����̌��ꂩ��l����`�h, ���傤����
[15] ��@�[�Y (2006). �g�����ŒB�����ׂ����ʖڕW�i�V�F�A�h�E�A�E�g�J���j�h, �u�o�c�����v�֓W�J����s���]��, �A�ڑ�12��, �����K�o�i���X2006. 4
[16] �O�H������y��. �v�d�a�G�� �����̃`�����l�� 2003�N2���� Vol.47, (http://www.internetclub.ne.jp/MRIKAI/region/NO47/Rtoku/Rtoku02.html), 2006.10.26�擾
[17] �����ȍs���]����. �u�A�E�g�J���w�W�ƃA�E�g�v�b�g�w�W�̕��ނ̍l�����v, (http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/pdf/021205_3_02_s15.pdf), 2006.10.26�擾
[18] �n���Z�c�́u�n����������̏��Ɋւ��钲�������v�̒��Ԃ܂Ƃ߇U, 2003�N3��, (http://www.bunken.nga.gr.jp/kenkyuusitu/kenkyukai/cyukanmatome2/mokuji.html), 2006.10.26�擾