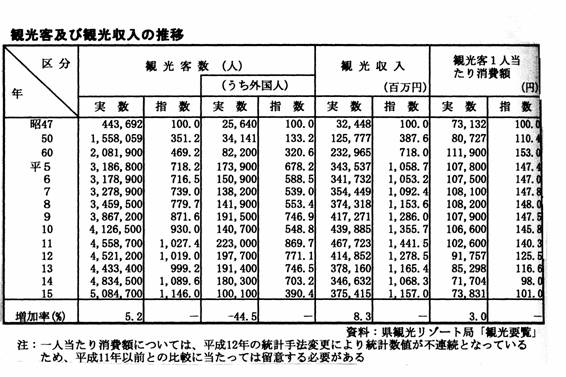�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@2005/07/22
�������x���K�i�Ж؏~�����j
�Q�O�O�T�N�x��P�Z���X�^�[��R�N�[����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʏ�@���F
���ꎩ���B�̍����E�o�ϖ��̌���
�P�A�͂��߂�
�u�n��̎����v�_�c��W�J����ۂɁA�ł��d�v�Ș_�_�́A�o�ς̖��ł���B�s�������S���Đ����ł���o�ϓI��Ղɂ��āA����i��O�N�[���j�́A�����������B���ɑ��N�[���őS�̑���������ɎO�_�̌o�ϓI�Ȓ����Ă����B����́A
�@�D�h�C�c�̋����ł̓����ƁA�B�ԕ��t�����ɂ�������Ղ̈���
�A�D����B�̎s���ɂ������I�Ȓn��Y�Ƃ̑n���i�R���Z�v�g�́u�����v�j
�B�D���������J���ɂ���t�����c�̊J���i�k�C���c���i����Ƃ��āj
�@�̎O�_�ł���B����́̕A���̎O�_�ɁA�V�������̓�_�������Č������s�������B
�C�D�݉��ČR��n�̒n���⏞���
�D�D��p����̒��ړ����̌���Ɖ������ׂ��ۑ�B
|
�Q�A�C�ݓ��ČR��n�̕⏞��� �@�ݓ��ČR��n��75�����A���ꌧ�ɏW�����Ă��錻����ߏd�ȕ��S���ƍ����S�̂��F�����Ă��Ă���B�������A���N������⒆���Ƒ�p�ْ̋����͂��߂Ƃ��铌�A�W�A�����̌R���͍\���ɕω�������܂ł͉���̕ČR��n�̒����͕ς��Ȃ��Ɛ����ł���B���ݐi�W�����҂���Ă���ČR��n�̖{�y�ւ̈ړ]�A�Ⴆ�Ε��V�Ԋ�n������KC�P�R�O�����@�̎R�����⍑��n�̉��������H�����ɔ����ړ]�A���邢�͎��q��������n�ւ̈ړ]���������ς܂���Ă��A�ˑR�Ƃ��Ďc��s�ύt�ɑ��鐭�{����̕⏞�͌������˂Ȃ�Ȃ��B�B�ւ̈ڍs����A�ČR��n�̑������c��\�����ɂ߂đ傫������ł���B �@����̐U���J���́A��㎵��N�̖{�y���A�ȗ�����U���J�����ʑ[�u�@���̉���J���O�@�≫�ꕜ�A���ʑ[�u�Ɋւ���@���Ői�߂��Ă����B���̂܂Ƃߖ��͉���J�����ō�N�x�́A��R�O�O�O���~�B���A��̗v�͂V���U�O�O�O���~�i�U���J����j�ɏ��B���H�⋴���A�w�Z�{�݂Ȃǂ̃C���t�������͖{�y���݂ɂȂ����B���̐U���J���̍l�����́A���A���ɑ傫�Ȋi���̂����������{�y���݂̌o�ϐ����ɂł��邾�������߂Â��悤�Ƃ������̂��B �������A����͊�n���S�ւ̕⏞�ł͂Ȃ��B����A���ׂ�����錧�Ȃǂɏ������ꂽ�u�����U���v�Ɠ������z�ł���B�������ē��{�Ƃ������S�̂̈��S�̂��߂ɔw�����Ă���ߏd���S�ւ̌��Ԃ�Ƃ������i�ł͂Ȃ��B���ʑ[�u�̒��̊�n��t����60���~��������x���B�ݓ��ČR��n�̕��S���銄����l����l������Ɋ��Z����ƁA1�Q�R�O�ł���B���̗]��ɂ��傫�ȍ��́A����̍ĕҌ�̎��Z�ł���B��������ʂȕ��S���������Ă��鉫��B�ɂ́A ���ʂ̒n�ʂ⌠�����^�����đR��ׂ��ł���B �@�Ⴆ�A���݂̉��ꌧ�̒n���Ŗ�Q�R�O���~�̌��Ƃ������Ă������̂ł͂Ȃ����B���k�Ĉ�ے�����S�ۏ�ے����C�������{�s�v���i���N�x���{�����Ȕ��u�t�����S�ۏ�_�j�́A���̖��ɂ��āu�V���U�O�O�O���~�Ƃ����A���Ƃ̌o�ϋK�͂ɔ�ׂ�Β�z�ōς܂��Ă�����̂́A���Ĉ��ۑ̐������邩�炾�B���̑̐��ێ��ׂ̈ɍ����S�̂̐ŕ��S���͖\�_�ł͂Ȃ��B�v�Əq�ׂĉ���̉ߏd�ȕ��S�ɕ⏞���l����ׂ����ƒ�N���Ă���B ������l�A�}���N�狳���́A�u����̐l�́A��n��݂��Ă���Ƃ����l���ŁA�͂�����Ƒ��v�v�Z�����āA���{�ɗv�����ׂ����B�l���ǂ�����B�v����ł̓��h���o��������A�u�j���[�X�Q�R�v�ł��A����Ɏv�������������J��Ԃ���鎁�Ƃ́A���̊��x���ԑg�ɓo�����Ă������������Ƃ�����A�����Ɏ��ɂ��̂悤�Ɍ���ꂽ�B ���A�ȍ~�̎O�\�O�N�Ԃɓ��ʑ[�u���u�����Ă��A����͂̈�l������̌��������͑S���̂V�O���������Ȃ��A���Ɨ��͂U����Ő��ڂ��Ă���B��n�W������P�T�O�O���~����ꎟ�Y�Ƃ̑����Y�z��葽�����������ŁA���Ɏx�o����n����t�œ��̈ˑ������́A���悻�W�O���ɒB����B��͂�A�U���J���̗\�Z�ȊO�̕⏞���K�v���B �R�D�A�\a.����B�s���ɂ������I�Ȓn��Y�Ƃ̑n���i�R���Z�v�g�͖����j�F�ό� �@�������ɁA���A�ȗ������z�̉�����\�Z����������A�Y�Ƃ̈琬�ƕی�Ɂw���A���ʑ[�u�x���@�\���Ă����B�r�[���Y�ƁA�Z�����g�����A�A���Y�Ƃɑ�\�������̂ł���B�T�g�E�L�r��p�C�i�b�v���Ȃǂ̔_�Ƃ��ی���Ă����B�������A���A�㒘���������������Ă����̂͊ό����]�[�g�Y�ƂƖ������Ƃ��錒�N�H�i�Y�Ƃł���B�X��ʂ̊C�ݐ��ɂ́A���A�Ȍ㑽���̃z�e�������n���A�C�����݂̂Ȃ炸�A�_�C�r���O�A�T�[�t�B���A�p���O���C�_�[�A�E�C���h�T�[�t�B�����C�m���W���[�̃��b�J�̗l����悵�Ă��Ă���B����A�����\�N�̌X���́A��������ȂǓs�s���ł̃T�����[�}���������I�����l�B�̕v�w�𒆐S�Ƃ�������ւ̈ڏZ�ł���B�ނ�� �@�z�e���̗��n�ɂ��A�V����y���ޕv�w�ɂ����{�̕⏕���͈�ؖ����B����́A����̎��C�Ȃǂ̎��R���}�����Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B1972�N�̕��A�̍ۂ�70���l�����Ȃ������ό��q���́A��N500���l��˔j�����B�ό�������B�̃��[�f�B���O�Y�Ƃł��邱�Ƃ́A�����܂ł��Ȃ��B�V�����������Ƃ��ẮA❶�C�O����̊ό��q�𑝂₷���ƁB❷�O���[���c�[���Y���E�G�R�c�[���Y���Ȃǎ��R��̌^�ό��̊J���B❸�����Љ�̔w�i�ɂ���w�����x�A�w�ƐH�����x�𒆐S�ɂ��������؍^�ό��̊J���B❹���^�C�A�[��̐����n�Ƃ��Ăۗ̕{�n��̊J�������l������B �@�����̕������������ۑ�Ƃ��ẮA�P�D�ό��y�Y�i�̌��Y�䗦�̌���B�Q�D�ɏے�����錒�N�H�i�Q�̌����̈��苟���A���Y�̐��̊m���B�R�D�n�����s�ЂȂǂɂ�闷�s��揤�i�̊J���Ȃǂ���������i�n���ւ̎��v���オ��Ȃ��A�{�y�G�[�W�F���g�ɂ��p�b�N���s�́A�i�������̈גn���ւ̌o�ό��ʂ����Ȃ��j�B�������A��{�I�ɂ͍����B��̈��M�ыC��ƁA�X��ʂ̃��[�t�Ɉ͂܂ꂽ�C�l�́A�ł��D�ꂽ�ό������ł���A�������Đl�H�̊J���s�ׂ������ɗ}���ł��邩���A�ό����]�[�g�n�Ƃ��Ă̏d�v�ȃE�C�[�N�|�C���g�ł��낤�B�܂�A���ꏔ���̓��X�ƁA�������芪�����R�����̂܂c�����Ƃ��A�X�Ȃ鉫��ό��̔��W�̋ߓ����Ƃ������Ɏv����B���E�ő�̎s��Ƃ����钆���́A�q��ւłQ���Ԃ̋����ł���A��p�͂P���Ԃł���B�������A���̗��s��ɂ͒��ڂ��ׂ��C�l���]�[�g�͂Ȃ��B���`���܂߂āA�U�q�v���[���e�[�V���������ׂ��s��́A�����߂��ɖ����Ă���B �X�ɁA������ɉ�����A���s��̃E�G�C�g���������[���b�p�s�ꂩ����A�ŋ߉��ꂪ���ڂ���Ă����B���{�Ƃ������ɂ���Ƃ������S���ƁA�����̓��ׂ́A���[���b�p�l�̒����؍^�ό��n�Ƃ��Ă̏����ɂ��Ȃ��Ƃ���A���̃R�e�[�W�^�h���{�݂̐����́A�Ƒ�����݂Œ����̉ċx�x�ɂ����}�ł���B
3-���D���̌��N�H�i�Y�� �@���{���A��O�\�O�N���o�߂������ꂾ���A���{�̒n��J������ɏK���悤�ɁA����̌o�ϐU���������Ƃ̖{�y����̗U�v�𒆐S�ɍl�����Ă����B�������A�ČR�������̗������{����ɐ��܂ꂽ�����A�r�[���A�����A�p�C�i�b�v���ʋl�A���|�A�����A�d�́A�q��A�����������Y�Ƃ̗��n�́A�w�ǂȂ������Ƃ�����B�`������A���D���͐�O����̂��̂����A���ǁA���{���{�����A��O�\�O�N�Ԃɓ����������������́A���H�ȂǎЉ�{�̐����ɂ́A���ʂ����������A��Ƃ̑n�o�ɂ́A���т��Ă��Ȃ������B���̂悤�Ȓ��A���{���{�����ꌧ���w�ǒ��ڂ��Ă��Ȃ������Y�Ƃ����𒆐S�Ƃ��錒�N�H�i�Y�Ƃł���B������ȂǁA���ɍ����s��Œm���Ă��鏤�i�����邪�A����ȊO�ɂ��O���o�̗l�ɖ{�y�������H�i���[�J�[�����̌��\�ɒ��ڂ��A�����̌������Ő������͂����ď��i�������������B�O���o�́A�C�O�ݏZ�̓��{�l�s��𒆐S�ɊC�O�s��ł̈ʒu���߂Ă��Ă���B�܂��A�����M�͍����ŎY������̂Ǝ�ނ��قȂ�B����́A�X��ʐΊD��̏�ɂł����y�낪��{�I�ɓy�n���`�����Ă��邽�߁A�J���V�E�����������̂ƁA���M�тɉ��ꂪ���邽�߂ɑ��z�����������A���ɒ�����āA�����M�̌��\����蔭���ł���ɂȂ��Ă���B��Ȍ��\�͌����ቺ���i�ł��邪�A�����͂��Ƃ��A�\�E�����͂��ߓ��H�������Ƃ����؍��s��ŏ���҂̐l�C���W�߂ėA�o���g�債�Ă���B �@�������A�����̉���B�̑�\�I�ȏ��i�̉\�����߂Ă���̂́A�R����p�����u�������v�Ɓu��h�v�ł��낤�B�������̎��k���k�����ɂ́u�t�R�C�_���v�ƌĂ�鐬�����ܗL����Ă��邪�A�ŋߓ�J�N�ԂŌ����҂̌������i�W���A�݊��ƈݒ�ᇁA�����Ăg�h�u �Ɍ��ʂ����邱�Ƃ������ꂽ�B����זE���t�R�C�_������ݍ���ŏ��ł�����Ƃ����̂��B���̐����́A�V�w�������̂悤�ɉߔM�����Ă����ł��Ȃ������������A�܂��i�����������̂悤�ɐ������Ċ����������Ƃ��ēX���Ŕ̔����A����҂�����œ��𒍂����ƂŌ���ɖ߂����Ƃ��ł���B���M���Ă��A���������Ă��t�R�C�_���͎��ł��Ȃ��B���̂������́A���E�ł͓쑾���m�Ɖ����k���Ƃ��Đ��炵�Ă���A����������a�̎R���Ƌ��������邱�Ƃ͂Ȃ��A�܂���������B�̏B���Y�ɂȂ�B ���̎��_�̔w�i�ɂ͍ŋ߁u���[��[�v�Ƃ������������{�y�ł��蒅������Z���A������Y�ł͂Ȃ���������{��A���邢�͈��ł����Y�Əo�ׂ��͂��܂�A���ꂩ��̔��M���i���A�s��ŋ�����Ԃ�\�o�����Ă��邱�Ƃɂ���B�������A���{���̏��i�\�����u��邲�[��[�v�������肷��B���������ʌ�̎s���������Ƃ͊�������A������Ԃł́A���Y�҂͏��X�߂������낤�B�����悤�Ȏ���ł͖k�C���Y�́u���ꂻ�v���p�Y�́u���ꍕ���v������B��p�Y�̍����̏ꍇ�A�i�����܂������قȂ�u�ԓ��v�������ł���A�Ɠ��̖��ƌ��\���������i�������j�Ƃ́A�قȂ�̂ł���B�����̉���u�[���́A�i�C�̒���������钆�ŁA ���{���̊�Ƃɗގ����i�̐��Y�Ǝs��J���𑣂����ʂɂȂ��Ă���B �@���ꂪ�A���{�̈ꕔ�Ƃ��ĔF������Ă��Ă��錋�ʂ��Ƃ������邪�A����̐��Y�҂◬�ʋƎҁA���邢�͍s���́A�u�����h�̊m�����}���ׂ��ł��낤�B�����ɉ���B�Ƃ��ẮA�s��헪�{���̑̐������Ȃ���A���{����C�O�Ƃ̋����ɏ����c��Ȃ��B�B�ɂȂ����Ƃ��� �����I�ȎY�Ƃ̈琬�ƁA�s��J���ɂ����ƁA�͂𒍂��ׂ��ł͂Ȃ����B |