第1章 住民投票の制度と現在
1.1 住民投票の定義と現状 -地域の自己決定権-
住民投票は、地方自治あるいは地域の自己決定権を鮮明に表現したものとして大きな注目を集め、1996年以降全国各地で実施されている。ここでいう住民投票とは、「特定の政策についての採否を決するに際し、地域住民による投票の多数意志を尊重する義務を課すことを目的として、住民の直接請求あるいは議員や首長の提案により提出され、成立した条例に基づき実施されるもの」と定義する[1]。
住民投票条例は、82年7月に制定した高知県窪川町(原子力発電所設置の是非)を皮切りに、現在有する地方公共団体数は13、条例数は14にのぼっており(97年11月14日に条例を廃止した高知県日高村を含む)、すでに25年近い歴史を有する。
96年が住民投票元年といわれているが、96年8月4日に実施した新潟県西蒲原郡巻町では、原子力発電所建設の是非をめぐって実施され、その結果は国のエネルギー政策との深刻な対立を引き起こした。また、翌月には沖縄県が日米地域協定の見直しと米軍基地の整理縮小の是非を問うために実施、その結果は国家の安全保障政策の見直しを中央政府に迫ることとなった。さらに、翌97年6月22日には岐阜県可児郡御嵩町で実施され、町内の産業廃棄物処理施設建設の是非を決しただけでなく、国の廃棄物行政さらには大量消費社会のあり方を問い直すものとなった。
これら住民投票をめぐる一連の動きは、今後の地方政治のあり方、中央と地方の政府間関係、都市部と農村部の関係、政治参加ひいては民主主義のあり方に再検討を促している。
なぜ地域は住民投票を選択したのか、だれが住民投票を推進したのか、住民投票が中央政府の決定にも影響を与えるのはなぜか、そして、今後、住民投票は地域自治を進める上で効果的な手法となりうるのか、日本と海外の事例を研究しながら新たな政策を提言する。
1.2 憲法、地方自治法と住民投票制度の関係 -住民投票条例の必要性―
住民投票を実施するためには、住民投票条例を制定しなければならない。日本の地方自治法には、特定の争点の是非について直接住民が選択を行う住民投票制度が用意されていないからである。
しかし、だからといって、有権者が候補者の選択ではなく、政策などの是非を選択する直接投票制度自体は、日本の政治制度にまったく規定されていないわけではない。国政レベルでは、憲法改正のためには国民投票を実施して過半数の同意を得なければならず(憲法96条)、また、特定の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のためには、その地方公共団体での住民投票により過半数の賛成を得なければならない(憲法95条)として、それぞれ国民投票や住民投票を制度化している。
また、地方レベルでも、直接請求制度に関連して、議会の解散、議員や首長の解職を求める直接請求が成立した後で、その是非を問う住民投票制度は規定されている(地方自治法76条など)。
しかし、以上のものが例外的に用意されているだけであって、それ以外の争点を対象とした住民(国民)投票制度=レファレンダムは制度化されていない。それゆえ、住民投票を実施したいと考える場合には、住民投票条例を制定することが要求されてくるのである。
1.3 住民投票は誰が求めているか -多数を占める住民からの直接請求-
では実際に住民投票を求めて、住民投票条例案を提案しているのは誰であろうか。それは、表に見られるとおり、直接請求により住民であることが明らかである。
表 1住民投票条例の提案者別成立率および成立の内訳[2]
|
1979-2002年 |
直接請求 |
首長提案 |
議員提案 |
総数 |
|
提案数 |
139 |
22 |
30 |
191 |
|
成立数 |
10 |
17 |
12 |
39 |
|
成立率 |
7.2% |
77.3% |
40.0% |
20.4% |
|
内訳 |
||||
|
1982年 |
|
1 |
|
窪川町 |
|
1988年 |
1 |
|
|
米子市 |
|
1993年 |
|
1 |
1 |
南島町等 |
|
1995年 |
1 |
1 |
4 |
串間市等 |
|
1996年 |
1 |
|
1 |
日高町等 |
|
1997年 |
3 |
1 |
|
箕面市等 |
|
1998年 |
1 |
3 |
|
小長井町等 |
|
1999年 |
|
|
1 |
徳島市 |
|
2000年 |
|
3 |
1 |
高浜町等 |
|
2001年 |
2 |
2 |
1 |
刈羽村等 |
|
2002年 |
1 |
5 |
3 |
米原町等 |
第2章 住民投票が求められる理由
2.1 住民投票条例が成立しているパターン
2002年現在、初めて住民投票が行われた96年の新潟県巻町以来、広島県府中町に至るまで、15の自治体で住民投票が行われている。この15例を見てみると、投票条例が成立したパターンを3つに分類することができる。
①Aパターン -三者一致の場合-
そのうち最多の9件、全体の6割を占めるパターンは、首長・議会・住民の三者が一致して住民投票の実施に賛成しているものである。このパターンは、2つに分けることができる。
1つは、投票の実施だけでなく、争点についても三者が一致したスタンスをとるものである。争点はいずれも迷惑施設であり、その設置反対を投票結果としてアピールするために三者が一致して条例を成立させているのがその特徴であり、住民投票に期待される機能のうち、自治体・住民の意思を投票結果としてアピールするための投票である。
もう1つは、自治体内で意見が割れている問題の解決のために、三者が住民投票の実施に賛成したパターンである。争点としては、合併や迷惑施設の問題がある。いずれも自治体内で意見が割れており、三者が一致してその解決手段として住民投票を求めたものであった。この場合は、自治体内部で対立の見られる問題に決着をつけることを目的にしている。
②Bパターン -首長対議会・住民の場合-
次に、住民投票に反対する首長と、投票に賛成する議会・住民グループが対立したパターンである。この事例では、産業廃棄物処理場に反対する議会・住民グループと処理場を必要とする首長が対立したものや、合併に積極的な議会・住民グループと合併に消極的な首長が対立したものがある。
このパターンでは、条例を議決する議会が賛成する以上、首長が反対しても基本的に条例は可決する。首長は再議に付すことができるが、実際に行使された例は5件だけである。住民投票に期待される首長と議会が対立する問題に決着をつける機能が果たされている。
③Cパターン -首長・議会対住民の場合-
最後のパターンは、首長・議会がともに住民投票に反対して、投票を求める住民グループと対立したものである。このパターンで住民投票が実施できた事例は4つで、いずれもリコールが可能な有権者の三分の一以上の署名数を集めて条例や解職を直接請求するなど、住民がいわば力技で条例の成立を勝ち取っている。しかし、これだけの署名が得られない場合など、多くは否決されて住民投票まで届かなかった自治体が多数ある。
表 2住民投票条例が可決したパターンと効果
|
首長・議会・住民の関係 |
争点 |
目的 |
効果・機能 |
|
①三者が住民投票の実施に賛成 |
争点への意見が一致 |
アピール |
意思の表示 |
|
②同上 |
自治体内で意見が対立 |
問題解決 |
争点に結論 |
|
首長反対、議会・住民賛成 |
首長と議会が対立 |
問題解決 |
対立に決着 |
|
首長・議会反対、住民要求 |
首長・議会と住民が対立 |
問題解決 |
政策の統制 |
2.2 投票結果が語るもの
①高い絶対得票率
住民投票は投票率が高いだけでなく、ドイツの州民立法制度の可決用件とされる絶対得票率が高いところに特徴がある。絶対得票率とは全有権者数の意思を示す率で、ドイツでは25%~33%の絶対得票率を課している。
一方、日本の住民投票条例では「50%条項」を設け、投票率が有権者の2分の1以上なければ開票しないという規定を設ける場合がある[3]。こうした成立要件は諸外国には珍しく、低投票率の場合は少数派が結果的に投票結果を制する危険性をもたらし、高投票率の場合は投票の不成立を図る戦術(ボイコット戦術)を促すことにもなる。こうした理由からドイツでは絶対得票率を成立要件に採用している。
2002年までに日本で行われた住民投票の15事例では、全ての投票においてドイツが課す絶対得票率を超えている。
②機能不全に陥っている議会
絶対得票率がもっとも高いのは、首長・議会・住民の三者が賛成し実施されたパターンA①であり、特に意思の表示、アピールを目的としたものである[4]。
この絶対得票率の高さが浮き彫りにしている地方自治の問題点がある。それは、ある意味ではもともと投票によって確かめるまでもなかった民意が、そこには存在していたということである[5]。それをあらためて住民投票を制度化して訴えなければならなかったほど、現行制度上は、地元自治体・住民の発言権が弱いことも物語っている。
特に、投票実例が多い産業廃棄物処理場の設置は、厚生労働大臣が法定受託事務として都道府県知事に委任しているものだが、知事の裁量が乏しく、基本的には厚生労働省が定めた基準を満たしていれば、許可が出されるため、地元の市町村や住民の関与は制度化されておらず、その発言権は法的に保障されていない。そのため、住民投票の実施が求められたのである。したがって、この種の住民投票は、それ以前に、住民の声を反映させることのできる手続きと住民への説明責任が果たされる体制への改善を行うべき課題である。
また、この種の争点で指摘される批判は、住民投票が地域のエゴの手段となる、というものである。反面、住民投票には多数者の専制、少数者への不利益の押し付け手段という批判もある。しかし、地域エゴも多数者の専制も、議会による決定であれば無条件に免れるわけではない。その意味では、調整役を担うべき議会の機能不全に他ならない。
住民投票の制度化以前に、自治体・住民の発言の強化、さらには議会の機能強化の必要性を読み取る必要がある。もし議会の機能が回復されれば、パターンAを目的とした住民投票の必要はなくなるのである。
③住民参加制度の未整備
パターンA①に次ぐ絶対得票率の高さを見せていたのが、パターンCに属する4例である。4例は、巻町への原子力発電所建設、名護市への米軍へリポート基地建設、徳島市の吉野川可動堰建設、刈羽村への原子力発電所におけるプルサーマル計画、である。これらは、いずれも首長と議会が「民意」の名の下に受け入れられようとしていたものであったが、住民投票は、実はそれが民意ではなかったことを明らかにしている。
今までも住民投票条例が直接請求されたにもかかわらず、その請求案の生殺与奪の権利を握る首長、そして議会によって、否決されてきた事例が数多くあるが、首長や議会の意思と住民の意思に食い違いが生じていたことが十分考えられる。
首長という人を選択する選挙は、常に単一争点で争われるものではなく、むしろ諸争点を踏まえての総合的な選択が行われている。その結果、個別の政策については、議会の決定と民意との間にねじれが生じる場合もあり、その解消を図る手段がないというのが現状の問題点である。唯一、残されている手段はリコール制度になるが、署名の収集など非常に難しく、失敗に終わるケースも多い。また、議会議員選挙が行われても勢力が変わらないことが多く、単一の争点を目的とした民意の反映方法が待たれるのである。
パターンCは、首長や議会のスチュワードシップやアカウンタビリティである応答性、説明責任の低さと、住民が民意を表現するための住民参加制度の未整備の状況を意味しているのである。
結局、直接請求では単一の争点を目的とした民意の反映が難しい。その理由は、署名収集の難しさと争点に関する情報提供が恣意的になるためである。
まず、一般的に有権者の50分の1の署名数を集まる場合、大変な労力となる。また、通常は施設建設に関する条例が制定されるのは建設が終了した後である。施設の建設後に条例の廃止を請求しても単なる建設コスト経費の無駄でしかない。建設そのものを着手前に止めるならば、事業計画の策定段階か、または設計の予算編成時点で反対しなければならない。よって、直接請求は重要案件を争うための有効な手段とはなりえないのである。
第3章 住民投票制度への歩み -住民投票条例の制定-
3.1 地方制度調査会における制度化の試み
①制度の是非をめぐる論議
住民投票の制度化の動きは、70年代に入り地方制度調査会の答申において明記されていた。そこでは、議会および長の代表制度との整合性に配慮しなければならず、あくまで代表民主政に対する補完的な制度であるとしつつも、「地方公共団体の配置分合、特定の重大な施策、事業を実施するために必要となる経費に係わる住民の特別の負担、さらには議会と長との意見が対立している特に重要な事件等について、住民投票制度を導入する必要があろう」と述べている。
この慎重な姿勢が踏み込んだ答申になるのは、2000年であった。この答申では、住民投票が住民自治の充実を図る上で重要な課題であるとし、市町村合併については、「その地域に住む住民自身の意思を問う住民投票制度の導入を図ることが適当である」と明確に言い切っている。
②改正合併特例法による制度化
戦後の日本で最も多く住民投票が行われた案件は、市町村の境界変更・合併である。延べ100件を超す住民投票が行われてきている[6]。
これまでの日本の歴史の中で、市町村合併には住民投票が制度化されてきた経緯があるが、2002年3月に成立した合併特例法には住民投票制度が規定された。これは、1965年の合併特例法において、住民発議がされても合併協議に至らない場合が多いことにかんがみ、取られた措置である。
こうした形で住民投票が制度化されたが、採用された経緯、制度の内容から見て、合併推進に偏重したバイアスを備えている。あくまで合併推進のための手段であり、住民が議論を行い、合併の可否自体を自己決定するものではなかったのである。
3.2 箕面市と高浜市の制度化論議 -市長発議型と住民発議型-
住民投票を制度化した自治体に大阪府箕面市がある。市長からの提案を受け同市議会が97年に制定した「箕面市市民参加条例」は、「市長は、市民の意思を直接問う必要があると認めるときは、市民投票を実施することができる」としており、市長発議による住民投票を規定している。
どのような場面で「市民の意思を直接問う必要」が生じるかは市長が判断することになっており、具体的には「市の存立の基礎的条件に関する行政区域・名称の変更や市町村の合併・分離、特定施策実施のための市税の課税率変更、原子力発電の誘致」などに加えて、「市議会と市長の意見が対立する重要案件や市の将来を長きにわたって拘束する事項について市民の意思が二分されるもの」などが想定されている。
この条例では、市長がその必要を認めても、手続き等を定めた実施条例を市議会に諮り制定しなければならず、結論としては投票の実施のために、別条例を必要とする。その意味で議会のチェックを受けるのがこの条例の特徴であり、そのプロセスを経ることにより、議会の権限を侵さない制度、代表民主政と住民投票の整合性を保つ制度になると考えられている。同様の条例は、長崎県小長井町、北海道ニセコ町などでも制定されている。
一方、愛知県高浜市や群馬県中里村は、そのまま住民投票が行われる手続きを定めた、いわゆる「常設型」「一般型」の住民投票条例をいちはやく制定したことで全国的に注目された。加えて、住民も投票を発議できる、という点は特徴的である。
「高浜市住民投票条例」は、市長発議、議会請求(過半数の賛成により議決)だけでなく、有権者の三分の一以上の署名によっても投票を発議できるとしている。また、対象事項として「市の権限に属さない事項」等を列挙して除外していること、投票率が50%を超えなければ不成立として開票を行わないことなども特徴となっている。
こうした箕面市と高浜市を代表として言われる住民投票のあり方を整理すれば、市長発議型の住民投票制度か、住民発議型の住民投票制度かと整理することができる。
箕面市にしても高浜市にしても、さしあたり住民投票を必要とするような政治問題を抱えているわけではない。にもかかわらず住民投票制度を設けたのは、施策形成段階から市民参加を保証することや、重要な施策について市民の意思を確認することの必要性を求めたからであり、それゆえ、その手段として住民投票の制度化を求めたのであった。
第4章 自治基本条例の制定 -住民投票制度の規定―
4.1 自治基本条例制定の進展
自治基本条例は、地方自治の本旨を実現するものとして、全国の自治体で制定や検討が活発に行われている。自治基本条例とは、他の条例や計画などの策定方針となり、自治体における基本条例としての性格を持つ。そのため、自治体運営に関する基本的な事項が網羅して規定され、住民の権利と責務、議会と行政の役割・責務を明らかにする総合条例としての性格を持たせるものとなっている。
特に、この住民の権利を実現するものとして、住民投票に関する規定を盛り込む自治体が多くみられており、練馬区企画部の練馬区自治基本条例を考える区民懇談会[7]の事務局調査によると、2006年10月末現在、全国には自治基本条例が78あるが、そのうち70の条例において、住民投票の規定を設けている(別添資料)。
住民投票規定のあり方は、一般的に住民投票に付すべき重要事項がある場合は、住民意思の総意を確認するため、首長が改めて住民投票条例を制定して行うよう規定するものとなっている。この点において箕面市型となる。しかし一方で、杉並区や中野区など、住民に限らず、議会、首長も住民投票を発議できるものとして規定しているところがみられる。これにより、箕面市型と高浜市型、さらに議会を加えた三者が住民投票を発議できることを自治の基本にすえる傾向が見られるようになったのである。
4.2 自治基本条例の意義と特徴
各自治体が制定している自治基本条例の意義は、行政のほか、住民や議会の権利と責務を規定することにみられる。また、特徴として、その権利と責務を具体的に果たすための手法が盛り込まれている。その一環として、住民投票が含まれる。
たとえば、箕面市市民参加条例では以下のように定められている。
(市民の責務)
第五条 市民は、市民参加によるまちづくりの推進について、自らの責任と役割を自覚し、積極的な参加に努めるものとする。
(市民投票の実施)
第八条 市長は、市民の意思を直接問う必要があると認めるときは、市民投票を実施することができる。
こうした例は多数見られるが、その他、練馬区では、まだ自治基本条例は制定過程にあるものの、区民懇談会の提言によると、区民は、自治を担い区政を創造する権利を有するとし、区民は自治を育むよう努める責務を提案している。
なお、直接請求によることなく自治基本条例に住民投票制度が規定される意義は大きい。
第5章 米国の地域自治と住民投票制度
5.1 日本と異なる米国の住民権限 -イニシアティブとレファレンダム-
日本と米国とは自治体制度が大きく異なる。日本では地方自治法による直接請求で住民投票条例そのものをつくらなければならない。これに対し、米国では州や自治体で法案そのものについて住民が立法を請願できる権利と、住民が表決できる権利の2つを有している。前者の権限は、住民の発案と署名で直接、立法が請願できるイニシアティブといい、後者の権限は、議会表決後の住民表決によるレファレンダムという。この二種類の制度が確立している点で日本と米国は異なる。
5.2 米国のイニシアティブと日本の直接請求制度 -議会提案、住民投票が不可能-
イニシアティブは、長や議会が打ち出したものではなく、有権者が発案したものを一定数の署名を集めることにより投票にかけようとするものであり、「住民(国民)発案」と訳される。
イニシアティブには、直接イニシアティブと間接イニシアティブの2つがある。
直接イニシアティブは、署名数が確認され請求が成立すると、議会を通さず一般有権者の住民投票にかける制度であり、その結果、提案が州政府に直接、受理されたり、否認されたりする。間接イニシアティブは請求成立後、議会が請求案をまず審議・議決するが、もし議会が否決した場合には、あらためて請求案を住民投票にかける制度である。
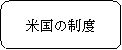
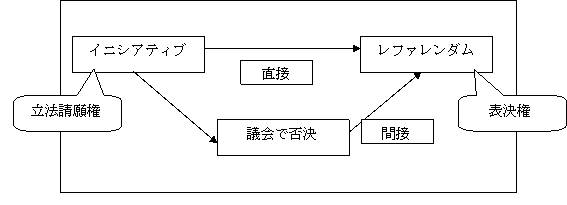
イニシアティブを選挙時に提案するには、州司法長官から請願名とその主旨を得なければならない。法令改正のための請願は前知事選挙の投票者数の5%の署名数が必要である。また州憲法改正の請願は前知事選挙の投票者数の8%の署名数が必要となる。
日本の地方自治法にはレファレンダムは規定されていないが、イニシアティブは、直接請求制度の一つとして制度化されている(地方自治法74条)。したがって、有権者はこの制度を利用して条例の制定改廃を請求することができる。しかし、日本のこの制度は、イニシアティブと比べると、中途半端なものといわざるをえない。
1947年、新憲法と同日に施行された地方自治法に盛り込まれた日本のイニシアティブ制度では、当該自治体に住所を有する有権者の50分の1以上の書面を集めることにより請求は成立する。ただし、請求が成立したところで請求案は住民投票にかけられるのではなく、首長が(請求案に賛成・反対の)意見をつけた上で、議会に提案するのであり、つまり直接イニシアティブの形になっていない。そして、議会が可決すればともかく、否決した場合には廃案になるだけであり、間接イニシアティブのようにこれを住民投票にかけることができる制度にもなっていない。結局のところ、住民は発案するだけであり、発案したものを住民投票にかけることはできないのである。こうした制度のあり方では、住民が署名を集めた努力がいとも簡単に否定されることが多く、住民の中には徒労感だけが残るともいわれている。
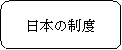
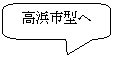
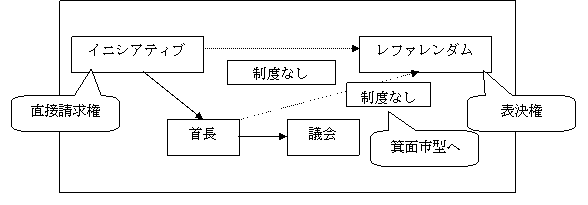
5.3 米国オレゴン州の財政制度のレファレンダム
米国では州法により、債権を発行し、借金をするときには住民投票が必要となる。たとえば、オレゴン州の州法では、目的別にどのようなボンド(債権)を、住民の何パーセントの可決で発行可能かが細かく規定されている[8]。
2006年の選挙においても、いくつかのスクール・ディストリクト(学校区)が、ボンド・メジャー(債権発行議案)を出したところ、ポートランド公立学校区[9]では可決されたが、隣の市であるビーバートン学校区では却下されている。
5.4 米国カリフォルニア州のイニシアティブとレファレンダム弊害
①廃止された間接イニシアティブ
米国カリフォルニア州のイニシアティブは1911年の特別選挙で可決され、ユタ、オレゴン、モンタナ、オクラホマ、ミズーリ、ミシガン、アーカンソー、コロラド、サウスダコタについで10番目の州制定である。このうちオレゴン州の直接イニシアティブは1902年に導入されたが、オレゴン・システムとして全米の直接イニシアティブのモデルとされている[10]。
イニシアティブは総選挙(4年ごとの大統領、上下両院、州議会、市議会の各議員、教育委員などの合同選挙)時にだけ実施されていたが、60年以降は大統領予備選挙、特別選挙としても実施されるようになった。
しかし、住民が議会に法令提案する間接イニシアティブは、1965年、利用がないことから、憲法改正委員会より廃止が提案された。翌66年11月の総選挙の際の住民投票においいて、間接イニシアティブを規定しているプロポジション1Aとともに間接イニシアティブは廃止された[11]。ただし、直接イニシアティブは存続している。
なお現在、間接イニシアティブが行われているのは、メイン、マサチューセッツ、ミシガン、ミシシッピー、ネバダ、オハイオ、ユタ、ワシントンの8州だけである[12]。
②レファレンダムの弊害とイニシアティブ・ビジネス
カリフォルニア州オレンジ郡は全米で4番目に大きく屈指の裕福な自治体であったが、1994年、郡の財務担当者が投機に失敗して多額の損失を抱えたことで有名である。そのため、チャプター・ナイン[13]による破産を申し立てたが、わずか2年後の1996年に財政再建を終了させることができた。
この破産に至った要因として、カリフォルニア州特有の背景があったといわれる。カリフォルニア州では、「プロポジション十三」という憲法で、住民投票にかけなければ増税できない強い制約がある。そのため、自治体は課税に対する住民の強い抵抗にあい、税収の確保に苦慮して投資に依存することになるというのである。1994年当時、14の郡がデリバティブに手を染めていたといわれている。課税制約が強まることにより、市場への資金調達に頼りがちとなり、地方債への依存が高まることが懸念される。
ただし、この事件以降、自治体による市場からの資金調達に対する規制は厳しくされたが、レファレンダムに対する改正等は行われていない[14]。
また、イニシアティブを行う場合、一般の住民には専門的な知識や煩雑な手続きが必要になる。さらには、署名の収集等1回のイニシアティブに500万円程度の経費がかかる。そのため、アメリカにはイニシアティブをサポートするNPOがある。また、費用についても寄付をする仕組みが設けられている。
5.5 米国における地域自治と行政組織のレファレンダム
①オレゴン州ポートランド市の行政組織レファレンダム
米国の地方自治体であるカウンティ(郡)やシティ(市)では、自治体の定めるチャーター(自治憲章)により、住民が行政組織を住民が選べるようになっている。また、州の憲法である州法で、ホーム・ルール(自治憲章)が認められている州では、それぞれの市がシティ・チャーター(市自治憲章)で行政組織を明記している。この自治憲章(チャーター)の改正は住民投票で決まる。
ポートランド市でも、自治憲章を改正すべきかを検討する自治憲章審査委員会(Charter Review Committee)が設置され、コミッショナー制の見直しが検討されたが、結果、改正議案は提出されていないという経緯がある。
②米国の地域自治
米国の政府は連邦政府から州、カウンティなど表3のように整理される。この他にも、州の中には存在するが、州に属さないトライバル・ガバメントと呼ばれる自治も存在する。
アメリカの場合は州が国であると考えたほうが分かりやすい。州政府直轄の行政単位として郡(county)があり、郡が必要最低限の行政サービスを行う。米国の地方自治体(municipality)は、ニューヨーク市やロサンゼルス市のような人口300万人を超える大都市(特別都市:chartered
cities)は例外で、一般の市(general law cities)は基本的に小さい。なお、今回の調査対象にしているオレゴン州ポートランド市は人口が約60万人で、政策提言を行う練馬区の人口70万人とほぼ同規模となっている。
一般の市は住民の社会契約により組織化(incorporate)されたもので、住民の意思決定により身の回りの行政サービス内容やレベルを決める。アメリカの人口約3億人に対し、約8万の自治体があり、その中には1000人に満たない市が約8000、数十人規模の市も存在する[15]。一方、市に属さない地域や組織化されない地域と呼ばれる郡直轄の地域(unincorporated
area)も存在する。ポートランド市はオレゴン州ムルトノマ郡に属しているが、郡の中には直轄の地域がある。また、近隣のロサンゼルスやサンフランシスコなどの大都市の周辺にもこのような地域が数多く存在する。
米国の場合、個人と個人が契約をして自治体をつくる。コミュニティに公共サービス、社会的サービスを提供する組織(NPO)が多数現れる。NPOが地域コミュニティの面倒をみる。自治体はNPOの一つであるという認識がある。日本にいうNPOと自治体は相互に補完的な関係にある。
また、地方自治体は市民全体に必要な公共財・サービスを提供する。そのサービス内容やレベルは、当然のことながら市民のニーズによって異なる。安全を重視し警察力を教化する市[16]もあれば、教育で独自性を出す市もある。全ての機能を小さな市でまかなうことができないので、一部のサービスを隣接自治体に委託したり、共同化したり、郡や州と連携したりしている。
表 3 政府分類表(1988年USセンサスから作成)
|
政府分類 |
政府数 |
政府 |
|
連邦 |
1 |
連邦政府 |
|
州 |
50 |
州政府 |
|
カウンティ(郡) |
3,042 |
地方政府 (local government) 83,166 |
|
ミニシュパリティ |
19,205 |
|
|
タウンシップ |
16,691 |
|
|
学校区 |
14,741 |
|
|
特別区 |
29,478 |
|
|
計 |
83,217 |
|
表 4 日米の政府数と階層の比較(日本は2006年3月末現在のデータで作成)
|
アメリカ |
日本 |
||
|
連邦 |
1 |
国家 |
1 |
|
州 |
50 |
都道府県 |
47 |
|
カウンティ (郡) |
3,042 |
基礎自治体(市区町村) |
1,821 |
|
ミニシュパリティ |
19,205 |
||
③米国オレゴン州における地方政府の状況
オレゴン州の政府は表5にまとめられる。カウンティと呼ばれる郡政府は、歴史的には州政府の出先機関として機能しており、郡の活動は、州憲法により認可もしくは委任されていた経緯がある。1958年、郡が自治憲章を採用することが認められ、1973年には州法によりすべての郡に条例制定権が認められた。
ミニシパリティは、いわゆる市町村と解されている。ミニシュパリティの多くが、-city,-town,-ton,-villeを付けて呼ばれる。特徴としては、①法的権威がある、②公式な組織である、③定期的に選挙される公務員がいる、④特定の地理的地域がある、⑤特定の実施機能や提供すべきサービスがある、⑥執行すべき一般的および特別の権限がある、⑦明確な公共性をもつ、⑧憲章(Charter)と呼ばれる基本法をもつ、ことである。
郡と市町村の役割分担は表6のとおりまとめられる。日本の区市町村と比較すると、日本の場合は、米国の郡と市町村の両方の役割を包含して担っており、非常に幅広く業務を行っていることが分かる。特に、水道や道路などライフラインに関する限り、日本に不要な地域はないのであるが、米国の場合は限定された地域にのみ提供されるサービスであり、日本の生活環境基盤の整備と大きく異なっている。
表 5 オレゴン州の政府数
|
政府分類 |
オレゴン州 |
|
カウンティ(郡) |
36 |
|
ミニシュパリティ |
240 |
|
広域政府[17] |
1 |
|
特別区(special district)[18] |
950 |
|
学校区(school district) |
165 |
|
計 |
1,392 |
表 6 郡と市町村の役割分担表
|
カウンティ |
ミニシュパリティ |
|
広範囲にわたる公共サービスを提供する |
一定の地域住民に公共サービスを提供する |
|
保健衛生、防犯、病院、高齢者サービス、空港、公園、図書館、土地利用、建物規制、経済開発、公共住宅、動物管理、美術館など |
消防、警察、道路管理、水道、下水道、駐車場、娯楽施設の建設許可業務、その他の社会事業、市の規定に基づいた土地利用調整など |
④米国オレゴン州の地方自治体における行政組織の類型と住民投票
行政組織の種類については、表7のとおり整理される。この中でもっとも多く採用されているのが、議会-支配人制である。この特徴は、①市議会が行政と立法の2つの機能を持つ、②市長は儀礼的存在で、市議会の議長を兼務する、③日常の行政執行のために専門職である「支配人(City
Manager)」を議会が任命する、④市長の承認のもと、支配人が部局長を任命する、というものである。
次に、市政府ではポートランド市だけが採用しているはコミッショナー制がある。これは、①選出された委員が議会機能を持つ、②市長は委員会の一員である、③市長が各委員に部局を割り当て委員は部局長を務める、④歴史的に市長が警察部門を管轄することが多い、という特徴を持つ。
三番目はメイヤー・カウンシル制である。この制度には、ストロング・メイヤーといわれる強い市長制と、そうではない弱い市長制の2つがある。強い市長制は、ムルトノマ郡ではビーバートン市が採用している唯一の市である。この制度は、もっとも日本の市町村制に近い制度である。その理由は、①公選の市長が行政部門の長である、②議会は政策決定機関である、③市長は部局の長の任命権と予算編成権を持ち、広範な拒否権を有する、という特徴にある。一方、弱い市長制には、①議長と市長に明確な区別はない、②立法、行政の区別もはっきりしない、③市長は議会の議長も務めるが、限定された予算編成権と人事権しかもたない、④市議会が予算や人事にもある程度介入する、という特徴がある[19]。
表 7 オレゴン州における行政組織の種類
|
組織の種類 |
オレゴン州 |
日本 |
|
議会-支配人制 (Council-Manager) |
2500人以上のほとんどの市政府 |
*シティ・マネージャー制 |
|
委員会制 (Commissioner) |
ムルトマ・カウンティ政府他23の郡政府 ポートランド市政府 |
|
|
議会-市長制 (Council -Mayor) |
小さな市政府 |
|
|
二元的代表制 (市長と議長の選出) |
|
日本の市区町村 |
⑤ポートランド市における行政組織のレファレンダム
ポートランド市は1913年に住民投票によって、この制度を採用しているが、ポートランドが市になったのは1851年から1913年までの間の組織形態に関する記載は見つからない。
ほとんどのアメリカの市は1900年代初めのグッド・ガバメント・ムーブメント以前はカウンシル-メイヤー制だったとの記述がある。以後、1933年、1958年にはシティ・マネージャー制、1966年にはストロング・メイヤー制にするべきといった提案書が出されたが、いずれも通っていない[20]。
日本では2004年の地方分権推進委員会の答申において、シティ・マネージャー制の導入が提起され、埼玉県志木市では構造改革特区でシティ・マネージャー制の提案が却下された経緯がある。現在の日本では、地方自治法により組織の形態が規定されているため、行政組織の種類が画一的で、自由に住民が行政組織を選べるどころか、行政組織の種類について一つのものしか知らない現状がある。
行政の効率化を住民とともに考えるために、行政組織の画一化を制度的に排すとともに、住民が行政組織を選べる仕組みを構築する必要がある。
第6章 政策提言
6.1 新日本版レファレンダムとイニシアティブの導入へ
①新日本版レファレンダム -自治基本条例の制定と住民投票制度の規定-
これまで見てきたように、住民投票条例の制定を求める住民運動、直接請求のほか、自治基本条例を制定し、地方分権時代における自治の基本を定める動きが活発化している。
自治基本条例は、分権化の進展に伴い住民参加による自立した自治体運営を行うため、住民投票に関する規定を盛り込んで制定される事例が多い。そこで、分権型社会における住民本位の自治を推進するためには、自治基本条例の制定を積極的に行うべきである。
次に、住民投票は、行政の恣意性を排除するとともに、住民による地域の自治を推進するため、住民が直接請求するまでもなく必要に応じて実施できるよう自治体の基本的な仕組みとして予め規定しておく必要がある。これによって、単一の争点であっても、住民参加のもと首長、議会と論議し、民意を反映して決定できる仕組みが構築できる。この点については、直請求による条例の制定を求める住民運動の中に、住民の意識を啓発する意義を組み取ることもできるが、実際には条例制定の提案が却下されることによる住民の疲れが見られる。むしろ、仕組みは事前に整備しておき、争点を活発に議論することが重要である。これにより、自治体としての新たなレファレンダム制度を構築することができる。
なお、手続に規定については、条例に委任してよい。また、開票の可否を判断する成立率としての投票率については、ボイコット運動などを引き起こすこともあり、設けるべきではない。ただし、絶対得票率は設定するべきである。
②新日本版イニシアティブ -住民、首長、議会の三者が発議できる住民投票-
住民投票制度については、首長が必要と認めた場合に発議できる箕面市型と、住民が発議できる高浜市型がある。これらの仕組みは、前者が米国の間接イニシアティブであり、後者が直接イニシアティブに該当している。こうした実情を踏まえ、米国と同様に両方の制度が活用できるよう統合型の住民投票条例の制定を考えるところであるが、さらに一歩進めて、議会も住民投票を発議できる三者発議型の住民投票制度を導入するべきである。
なお、米国では間接イニシアティブが廃止されている自治体もあるが、未だ存続している自治体もある。そこで、日本においては、住民からの発議は直接イニシアティブである住民投票に限定することとするが、日本にとっては新たな制度であり、杉並区や中野区の事例を踏まえ、首長や議会も住民投票を発議できる機会をあえて設けるべきである。現在、住民投票の実施されるケースとして、首長と議会の対立、首長・議会と住民の対立が住民投票の引き金になっている場合がある。こうした対立の構図から、より良い意思決定のために、首長または議会が住民投票を発議できる権利を持つことは有用である。
そこで、住民投票条例の制定に当たっては、三者が発議できるよう設計するべきである。
なお、住民が住民投票を直接請求できる署名数は、住民参加の促進と経費削減の観点から、合併特例法の住民投票、地方自治法に定める条例の制定等と同様50分の1とするべきである。
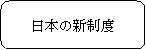
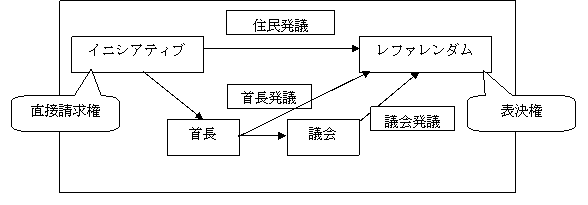
5.2 地盤としての熟慮する住民と地方自治法の改正
住民投票制度が適正に活用され、運営されるためには、熟慮する住民が地盤となる[21]。これまで住民投票が制度化されてこなかった理由として、付和雷同する住民や制度の濫用、単なる代表民主性の補完という意見がある。
特に濫用については、過去、税の廃止・軽減を求める直接請求が多くあった過去の事例の解釈による。そのため、昭和23年の自治法改正により、直接請求の対象から地方税の賦課徴収、分担金、使用料、手数料の徴収は除く措置が講じられた。一方、国民健康保険料は行政実例によると対象から除かれていない点で、矛盾が見られる。
現在、住民が熟慮するかどうかは実は議論が分かれている。住民投票はむしろ熟慮のきっかけとされることもある。
重要なことは住民の判断能力を決めつけることなく、行政として住民からの信託に答えるスチュワードシップと適時適切に情報提供を行うアカウンタビリティを果たすこと、そして住民参加の仕組み、民意を反映する仕組みを構築しておくことである。また、現在、全国各地で当たり前のように住民投票が行われる現状がある。それにより、住民が間接的に政治に参加するのではなく、直接的に参加する傾向、意識の高まりが伺える。こうした現状を踏まえ、地方自治法を昭和23年前に戻し、地方自治法第74条の直接請求における制限を撤廃する必要がある。
5.3 イニシアティブをサポートする体制
米国には専門知識や多額の経費を必要とするイニシアティブを行う住民に対し、それをサポートするためのNPOが存在する。今後、日本においてもイニシアティブが活発化することを見据え、それをサポートする専門知識を持ったNPOが必要である。
また、こうしたNPOの設立は立法や政策に関与している公務員のOBや、現在、早稲田大学公共経営研究科に見られるような政策の関する大学院の学生など、公共分野の人的資産が大いに活躍できる場として想定することができる。