市町村合併の是非に関する住民投票の意義と問題点
公共経営研究科
佐藤 邦夫(学籍番号:45032003)
(1)はじめに
議決権を有する議会の構成員である議員の私が、現在の間接民主制を覆すような直接民主制の住民投票を口にすることは、私自身変な気がする。というのは、「自分の出す結論に対して自信を持てないのか」、あるいは、「大切な決定をする自身の仕事の権利を放棄してしまうのか」等々の批判に対し、明確な反論が出来るかどうか疑問に思うからである。
私は今、岩手県胆江地区6市町村(水沢市・江刺市・前沢町・胆沢町・金ヶ崎町・衣川村)の特例法期限内(平成17年3月決定まで)の合併推進の立場で政治活動をしている。私自身としては、現実を把握するとともに将来を展望し、様々な角度から調査・研究・検討した結果、やはり合併することが胆江地区の発展の第一歩につながると判断する。
しかし、一歩下がって考えてみた時、30年後、50年後のこの地域の未来を左右する、このような真に大事な事を決定する時に、いくら住民の選挙で選出された議員であるからといって、議員だけで決定して良いものかどうか疑問に思う。
以下、市町村合併に於ける住民投票の是非と問題点について検証していく。
(2)住民投票の動き
選挙で選出された行政のトップ(首長)と議会が、有権者を代表し決定する間接民主制が日本地方自治の原則となっている。にもかかわらず最近、各地域において住民投票が行われ、また、多くの自治体において住民投票の条例制定がなされている。(さらに国においても国民投票に向けた運動もなされている)。これは住民投票により直接住民の意思を的確に反映し住民自治の実現をはかろうとする動きである。
(3) 議会制民主主義と住民投票
現行の地方自治制度は、議会制民主主義を前提として成り立っており、住民の代表として選挙で選出される議員が、首長をはじめとする行政側と議論、討論を重ね、最終的な政策を決定することになっている。にもかかわらず何故住民投票が叫ばれ実際にその住民投票が行われているのだろうか。その最も大きい要因として議会や行政に対する信頼の低下が考えられる。それを具体的にあげれば以下のようなものである。
(i) 住民の代表である議員が、議会において民意を十分に反映させるためにどれだけ深い議論をしているのか
(ii) 十分な行政情報公開がなされているのか
(iii) 政策に住民の意見を正確に反映しているのか
(iv) 住民と行政、住民と議員との間に様々な意識のずれがあるのではないか。
以上のような疑問や批判の声が住民の間で充満している。「住民が直接意見を表明する場として、住民投票を実施すべきである」という考え方から、各地で住民投票が行われているというのが実態である。
一方で、この「住民投票」に対して、大衆動員による非合理的な決定の危険性、不十分・不適切な情報提供による判断の歪みなどの危険性も指摘されている。評論家の西部邁氏は、「住民投票・国民投票は一つの巨大な感情運動になるのではないかと思う。間接民主制すらつくれない人間たちに直接民主制をうまく動かせる条件も能力も備わっているわけがない」と、住民投票に極めて懐疑的な見方をしている。
(4) 過去に行われた住民投票
(ア) 上尾市がさいたま市と合併することの可否を問う住民投票
住民投票日 2001年7月29日 投票結果 投票率 64.48% 賛成 44,700票 反対 62,382票 住民投票後の市長のコメント(抜粋) 上尾市がさいたま市と合併することの可否を問う住民投票条例に基づく全国初の合併に関する住民投票が実施され、64.48%という近年まれにみる高い投票率となったことは、市民皆さんの合併に対する関心の高さを伺い知ることが出来るものでした。この場をおかりして市民の皆さんに深く感謝致します。 私は住民投票の実施が決定された以上、その投票結果を尊重するスタントをとって参りましたが、投票率が低い場合の判断については民意の反映といえるかどうかという懸念を持っていました。 ・・・中略・・・ 最後に、今回の住民投票では、賛成・反対の個人個人による意見の違いによるしこりが残ったことも事実であろうかと思います。しかし、これも我が町“あげお”を愛するが故の議論であったと確信しております。
この住民投票の結果を踏まえて、上尾市長はさいたま市に対して最終的に合併協議の辞退を申し入れている。なお上尾市ではこの住民投票に先立って「上尾市がさいたま市と合併することの可否を住民投票に付するための条例」を定め、第一条の目的から始まる第十七条まで、細部に渡っての取り決めがなされている。
(イ) 新潟県西蒲群巻町町、巻原子力発電所建設計画の是非を問う住民投票
住民投票日 1996年8月4日 投票結果 投票率 88.29% 賛成 7,904票 反対 12,478票 住民投票後の市長のコメント 住民投票の結果を尊重し、灯心予定地を東北電力に売却はしない。従って、原発設計は不可能になる。
この巻町の住民投票実施までに至る経過においては様々な紆余曲折があった。住民投票の条例づくりの市民からの請願から始まり、住民自主管理投票、施行期限付住民投票条例の決定、さらに町長のリコール運動、町長の辞職、超低投票率の町長選挙等々。辞職した当時の町長佐藤莞爾氏は「住民投票は議会制民主主義への挑戦だ。とりわけ原発のような高度な政治的判断を要する問題には住民投票はなじまない」と語っている。
この住民投票が行われるに際して、賛成反対双方が投票日の8月4日をにらんで激しいPR合戦を繰り広げた。とりわけ東北電力社員を動員し徹底した個別訪問に加え、温泉旅行付原発視察を企画しひんしゅくを買うこともあった。
(ハ)岐阜県御嵩町、「小和沢産廃建設の是非を問う」住民投票
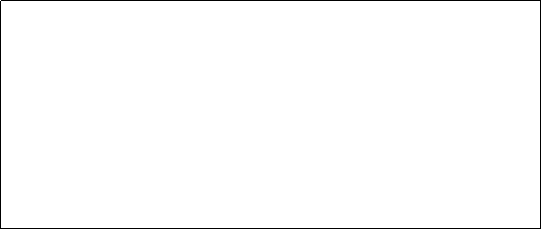 住民投票日 1997年6月22日
住民投票日 1997年6月22日
投票結果 投票率 87.5%
反対 10,373票
賛成 2,442票
住民投票後の梶原岐阜県知事のコメント
「町として長がどう判断するかだ。こちらから何かするつもりは一切ない。」
住民投票に拘束がない以上県としても投票結果を理由に、手続き上は建設を不許可に出来ない事情がある。とはいえ、政治的には御嵩町での産業廃棄物の施設の建設は無理」という見解が県庁内では支配的だと言われている。
(二)徳島市、吉野川第10稼動堰化の賛否を問う住民投票)
住民投票日 2000年1月23日 投票結果 投票率 54.995% 反対 102,759票 賛成 9,367票 住民投票後の各氏のコメント 亀井政調会長(当時) 住民の意思を無視するわけにはいかない 中山正暉建設省(当時) 稼働堰以外の選択肢も考えられる 圓藤知事 生命、財産を守ることが出来れば現計画にこだわらない
としている。圓藤知事は住民投票前には「住民投票は民意を問う一つの手段だが、あくまで間接民主制の補完である」とし、「審議委員会は住民投票と同様民意を問う手段として役割を十分果たした。さらに、住民投票を実施する必要は必ずしもない。第10堰改築は高度で専門的かつ技術的な問題を含み、住民が十分に理解した上でなければ住民投票の意味がいない」と語っていた。
(5) 問題点、留意点
住民投票の制度論に関する問題点として次のようなことが指摘されている。
(1) 十分な資料や情報にもとづく冷静かつ多面的な討議が浸透しにくく、勢い煽動家やマスコミによる大衆操作の影響を受けやすい。
(2) 住民投票の動向は、一時の情熱や偶然的要素に左右され、政策的に一貫性を欠いた予想外の結論となることが多い。
(3) たいてい、勝敗は僅差で決まり、かえって住民の間にしこりが残ることが多い。
(4) 住民投票の結果に責任を持つ者は存在しない。
(5) 住民投票でいったん事が決まってしまうと、再び住民投票にかけなければ、覆すことができないため、事態が硬直化することが考えられる。
又、実際に住民投票がおこなわれた場合には、次のような点も留意すべきであろう。
(1) 投票管理問題:誰がどのように投票管理を行うのか
(2) 有効投票率の規定と結果判定の基準値
(3) 選挙対象者をどこまでにするのか
* 20歳以上の選挙人名簿登録者
* 高校生を含む18歳以上
* 永住外国人
(6)結論
間接民主制における住民投票という直接民主制を取り入れる手法は、なるほど現時点においては、(5)で掲げたようないくつかの問題点を指摘されている。しかし(4)で示した過去の例からも判断できるとおり、法的には効力を持たない住民投票であっても、その結果が民意として行政側に確実に伝わり、結果を重視した政策へと方向転換していることが判る。すなわち、合併の是非など自治体存立の基礎的条件にかかわる基本的な選択については極めて有用であると思う。あらゆることを住民投票で決定するということではなく、重要な問題に対してのみ直接民意を問うようにし、その結果を尊重することは、民主主義の発展であり、重要であると考える。
その実施に対しては、(5)に述べた留意点も含め、付託された案件の判断に必要な正確な情報の開示、民意の形成のため十分に時間をかけた検討、討議が必要がある。
賛成、反対の意見の違いや利害関係も絡んで、投票後にしこりが残るとことは避けることは出来ないと思う。このしこりを少なくすることや和らげることが行政のトップ及び議員の責任である。
参考文献 新藤 宗幸編著 「住民投票」 ぎょうせい