自治制度演習最終レポート 2006.11.7
公共経営研究科 大平公一
テーマ「地方議会の活性化−地方議員の政策形成・条例立案について」
1.はじめに
本レポートの目的は、地方議会の活性化について考察することである。具体的には、地方議会議員の政策形成・条例立案能力の向上について考察する。2000年に地方分権一括法が施行され、制度上、自治体の自主性・自立性が向上した。分権の流れは次のステップへと移り、現在、税財源に関する三位一体の改革が進行している。このように分権が進行し、自治体にはそれぞれの地域の実情にあった政策形成・条例立案が求められている。
このような自治体に関する制度の改正により、多くの自治体が様々な取組みをしている。特に自治体における執行部、つまり地方行政は大きく変化している。ニュー・パブリックマネジメント型の行政改革の流れもあり、行政組織の改革や、職員の意識改革なども進められている。
このように地方行政が活発な改革や動きを促進させる一方、地方議会の変化が顕著に見られないように思われる。分権型社会において、住民の代表機関である地方議会は重要な役割が求められている。そこで、本レポートでは地方議会の活性化の具体的な対策として、地方議会議員の政策立案・条例立案の現状について概観し、その課題を提示したい。
2.地方分権改革と地方議会
2000年に施行された地方分権一括法によって、地方議会に関する制度が大きく改正された。本章ではその改正点の概略のについてまとめてみたい。
地方分権一括法により、機関委任事務が廃止された。この機関委任事務制度の廃止により、新たな事務区分が設計された。自治事務と法定受託事務である。機関委任事務制度の廃止と新たな事務区分の創設によって、条例制定権が拡大した。すなわち、地方議会の活動範囲が拡大した。これまで機関委任事務に関しては、自治体の首長を国の機関と位置づけ委任していた事務である。この事務に関しては、地方議会は条例を制定することができなかった。しかし、機関委任事務制度が廃止され、その多くの事務が自治体の事務である自治事務とされ、条例を制定することが可能になったのである。
また、議案提出要件と修正動議要件が議員定数の8分の1以上から12分の1以上に緩和された。
3.議員提案条例の現状
このようなに地方議会が条例を制定することができる範囲は拡大した。では、地方議会における議員提案条例の現状はどのようになっているのだろうか。
(1)都道府県議会における議員提案条例の現状
表1は、全国の都道府県議会における、議員提案条例数と首長提出条例の変化を示したものである。2001年以降、議員提出条例は増加傾向にあるが、首長提出条例に比べると少ない状況にある。また、議員提案条例の内容については、議会に関する自律規定がその大部分をしめることが指摘されている1)。
表 1
|
年 |
団体数 |
議員提案条例 |
首長提出条例 |
|
1990 |
47 |
28 |
1,825 |
|
1995 |
47 |
75 |
2,388 |
|
2000 |
47 |
74 |
4,289 |
|
2001 |
47 |
153 |
3,280 |
|
2002 |
47 |
179 |
|
出典 秋葉賢也『地方議会における議員立法』(文芸社,2001)P.15〜17
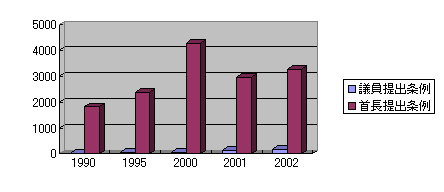
(2)市議会における議員提案条例に関する現状
表2は、全国の市議会における議員提出条例数と首長提案条例数の変化を示したものである。表2からもわかるように、市議会においても首長提案条例と比較し、議員提案条例は少ない状況にある。
表 2
|
年 |
団体数 |
議員提案条例 |
首長提案条例 |
|
1990 |
655 |
579 |
1,825 |
|
1995 |
664 |
631 |
2,388 |
|
2000 |
671 |
1,045 |
4,289 |
|
2001 |
697 |
1,020 |
2,965 |
|
2002 |
698 |
1,706 |
3,280 |
|
2003 |
686 |
999 |
21,967 |
|
2004 |
751 |
848 |
22,851 |
出典 各年の『市議会の活動に関する実態調査』(全国市議会議長会)
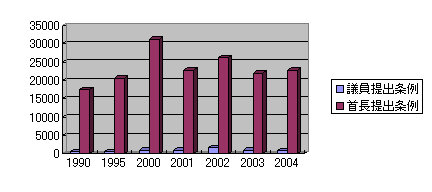
(3)町村議会における議員提案条例の現状
表3は、全国の町村議会における議員提案条数と首長提案条例数の変化を示したものである。町村議会における議員提案条例数も首長提案条例に比べ少ない状況にある。
表 3
|
年 |
団体数 |
議員提案条例 |
首長提案条例 |
|
1990 |
2,590 |
※0.2 |
※28.0 |
|
1995 |
2,571 |
※0.3 |
※22.8 |
|
2000 |
2,558 |
※0.7 |
※21.5 |
|
2001 |
2,554 |
※1.3 |
※35.0 |
|
2002 |
2,543 |
1,437 |
55,861 |
※印は1町村当たりの平均件数
出典 礒崎初仁「自治体議会の政策法務第二回 議員提案条例の状況 求められる意識改革」『月刊ガバナンス』
(3)まとめ
このような、都道府県議会・市議会・町村議会における議員提案条例は、首長提案条例に比べ極端に少ない。また、この分析から注目する点は、地方分権一括法の施行前と施行後の変化である。先にも述べたように、地方分権一括法は2000年4月に施行された。この法改正により、地方議会の条例制定権や活動範囲が広がった。しかし、各団体の地方議会において、議員提案条例数に大きな変化は見られない。
議員提案条例が少ない原因としては、次のような指摘がある2)。第1は、議会はこれまで政策形成や条例立案よりも、行政の監視に力を注いできたことである。第2は、機関委任事務などの中央集権的な法制度の下では、議会に権能が限られていたことである。第3は、議員に政策形成や条例立案に関する情報が不足しまたその能力が乏しいことである。そして、議員の政策形成や条例立案をサポートする議会事務局の体制が不十分である。
3.地方議会の役割の変化
そもそも、地方議会にはどのような役割が求められているのだろうか。地方議会には大きく二つの役割がある。一つは執行機関の監視という役割である。二つは政策形成・条例制定という役割である。地方分権が推進される中、地方議会に求められる役割について、以下で考察してみたい。
地方分権一括法が施行される以前、国と自治体の関係は中央集権体制であったと指摘されている。特に制度上、権限財源を握る国が政策を決定し、自治体はそれを施行するという構図であった。このような制度の中で地方議会に求められたのは、主に地方行政の監視という点だろう。なぜならば、地方議会の権能である条例制定権の範囲も、「国の事務」である機関委任事務には及ばなかった。そのため、条例立案よりも執行機関の監視に力が注がれていた。
しかし、地方分権改革によって、自治体の権限が増加した現在において、自治体の自主的な政策決定とその実施が求められる。このような中で、地方議会に求められる役割は、地方行政の監視と同時に、これまで以上に政策立案・条例立案が求められるだろう。
このような地方議会議員の役割が変化する中で、地方議会議員は、依然として、政策立案よりも政策審議や行政の監視・世話役相談役ということを重視していることが指摘されている3)。
このように地方議会の担う役割が変化した中で、議員提案条例を増加させ、ひいては政策形成力を向上させるためには、どのような対策が必要とされるだろうか。以下では、議員の政策形成や条例制定をサポートする議会事務局について考察する。
4.議会事務局改革に関する各団体の提言
地方六団体の中で、都道府県議会議長会と全国町村会が地方議会の活性化に関する提言の中で、議会事務局の改革について提言がある。
都道府県議会議長会に設置された都道府県議会制度研究会の報告書(改革・地方議会−さらなる前進へ向けて− 平成18年3月29日)では、「議会事務局の機能を明確化せよ」と提言している。そして改革の趣旨として、「議会事務局の機能が、単なる議会運営の補助や庶務だけでなく、議会政策提案機能、監視機能及び調査機能等を輔佐する機関であることを明確に位置付けるためにも、地方自治法第138条の規定中の「庶務」の文言を「事務」と改めるべきである」としている。
また、全国町村議長会の『分権時代に対応した新たな町村議会の活性化方策−最終報告− 平成18年5月』では、3つの提言をしている。「議会の権能の大幅な拡充に対応できるよう、発想の転換により調査・立法機能の充実を核にした議会事務局の思い切った拡大・増員を図る」。「事務局職員に対する議長の人事権を実質的に確立し、その処遇面に十分考慮を払いながら有能な人材を確保するよう務める」。「仮に議会事務局の陣容拡大が見込めない場合、次善の対策として以下のような強化策を検討・実施する」とし、具体的には「独自の情報資料の収集能力を高めるため、地域の大学・研究機関や弁護士会などの協力を求める」。また「議員各自の調査・政策立案能力を向上するのに役立つよう、議会関連の資料に特化した図書室の充実を図る」。
この二つの提言は、議会事務局を現状のまま、法律の文言の改正、そして議会事務局の人員の拡充ということである。これでは包括的な改革ができないのではないか。
5.議会事務局の現状と問題点
(1)現状
現在、議員提案条例の作成をサポートする組織として、議会事務局が設置されている。地方自治法第138条で、都道府県は議会に議会事務局に設置することが義務付けられている。市町村に関しては、議会事務局の設置は義務付けられているわけではないが、大部分の市町村で設置されているのが現状である。また、職員の任免権は、制度上議長の権限であるが、首長が行っているのが現状である。職員も執行部からの出向となっている。議会事務局の一般的な機構は、秘書課、総務課、調査課、図書室となっている。
全国都道府県議会議員定数と議会事務局職員の比率は、全国平均で72.6%となっている4)。これは、議会事務局の人員数としては十分な比率といえるだろう。都道府県議会事務局職員の在職年数は、三年未満が63.8%、3年以上5年未満が12.3%、5年以上10年未満が9.9%、10年以上15年未満が3.4%となっている5)。
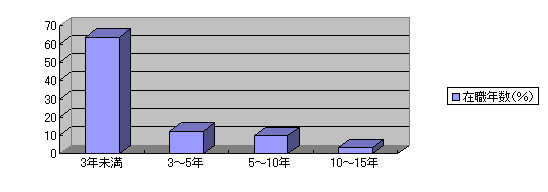
グラフ(都道府県議会事務局職員の在職年数)
(2)問題点
以上が議会事務局の現状である。この問題点として次のことが指摘できるだろう。第1に、議会事務局の職員はその大部分が執行部から出向となっていること。第2に、在職年数が極めて短いことである。
このような人事配置から生じる問題点としては、議会事務局における専門的な職員が育成されない点である。また、議会事務局に出向した職員は、本来執行部の職員でありながら議員のサポートをするため二面性が生じる。その結果、執行部に不利な政策や条例を作成することが困難となるだろう。
このように、議員提案条例や政策形成の向上をはかるためには、議会事務職員の執行部からの独立性の確保と、職員の専門性の強化が必要である。
5.議会事務局改革に関する自治体の取組み
現在、議会事務局の改革に関する取組みが進行している。その中でも注目すべきは宮城県と三重県の取組みである。
宮城県は、議会事務局の調査課を政務調査課に改め、政策法令班を設置した6)。三重県は、政務調査課を設置し、政策法務部門を強化するために政策法務担当を設置した7)。また、議会事務局職員の衆議院・参議院法制局に研修派遣や、図書室改革をおこなった8)。
このような議会事務局改革の注目すべき点は、政策法務機能強化のための担当を設置したことだろう。しかし、議会事務局の独立性を確保するような改革はなされていない。
6.おわりに
地方議会の活性化として議員の政策形成・条例立案の現状と問題点について考察してきた。結論としては、議会事務局改革において、執行部からの議会事務局職員の独立性を確保するような新たな機構の整備が必要であると考える。具体的に、都道府県・市町村ごとにどのような機構を整備するのかについては今後の課題としたい。
(注)
1)秋葉賢也『地方議会における議員立法』(文芸社,2001)P.14〜24参照。
2)詳細については、礒崎初仁「自治体議会の政策法務 第2回 議員提案条例の状況 求められる意識改革」『月刊ガバナンス』(ぎょうせい)参照。
3)詳細については、佐々木信夫『自治体をどう変えるか』(ちくま新書,2006)P.121〜123参照。
4)詳細については、全国都道府県議長会ホームページ「全国都道府県議員定数及び事務局機構一覧表」URL http://www.gichokai.gr.jo/ 2006年10月17日現在
5)藤原範典『自治体経営と議会 改革への理論と実践』(ブレーン出版,2006)P.323参照。
6)前掲注5)P.422参照。
7)前掲注5)P.422参照。
《参考文献》
・佐々木信夫『自治体をどうかえるか』(ちくま新書,2006)
・藤原範典『自治体経営と議会 改革への理論と実践』(ブレーン出版,2006)
・都道府県議会制度研究会『改革地方議会−さらなる前進へ向けて−都道府県議会制度研究会報告 平成18年3月29日』
・全国市議会議長会『平成12年 市議会の活動に関する実態調査』
・全国市議会議長会『平成13年 市議会の活動に関する実態調査』
・全国市議会議長会『平成14年 市議会の活動に関する実態調査』
・全国市議会議長会『平成15年 市議会の活動に関する実態調査』
・全国市議会議長会『市議会の活性化等に関する実態調査結果 平成17年3月1日』
・全国町村議会議長会『分権時代に対応した新たな町村議会の活性化方策−最終報告平成18年5月』