3クール自治制度演習最終レポート
2004.7.23
大平公一
テーマ「地方分権一括法施行後の地方公共団体における条例数の変化−東京都を事例として」
1.はじめに
本レポートの目的は、地方分権一括法が施行された平成12年を中心に、東京都の条例数の変化について、その量的な側面を検討することである。
地方分権一括法の制定は、制度上、地方公共団体の自主性・自立性を向上させた。それは、機関委任事務の廃止、新たな事務区分の創設、条例制定権の拡大等にみられる。このような制度変化は、地方公共団体にどのような影響を与えているのだろうか。すなわち、地方分権一括法の制定により、制度的には、地方公共団体の自主性・自立性は向上したのであるが、実際、地方公共団体は、国から自立しかつ自主的に活動しているのだろうか。そこで、本レポートでは、このような制度変化が、地方公共団体に与える影響を考察するために、条例制定権の拡大に着目する。
2.地方自治法の改正による条例制定権の拡大
地方分権一括法の施行以前は、機関委任事務については、それが国の事務であり、その事務を首長に委任しているため、条例を制定することができなかった。このような機関委任事務は、それが廃止される直前で、561件あった1)。しかし、地方分権一括法の制定により、機関委任事務制度は、全面的に廃止された。この法改正により、これまで機関委任事務とされてきた事務は、地方公共団体の事務である自治事務と法定受託事務に振り分けられたのである。つまり、地方議会は、機関委任事務とされていた事務についても条例を制定することが可能になったのである。これは、地方議会の条例を制定することができる事務の範囲が拡大したことを意味する。
3.地方分権一括法施行後の東京都における条例制定数の変化
(1)はじめに
地方分権一括法の制定により、地方自治法が改正され、条例制定権が拡大した。このような制度の変化に対して、現実はどのように動いているのだろうか。すなわち、地方議会の制定する条例は、どのように変化しているのだろうか。
本章では、地方分権一括法が施行された平成12年4月を中心に、東京都の条例制定数が、どのように変化したのかという量的な側面について検討する。東京都に着目する理由は、日本の首都であり、地方分権一括法がどのような影響を首都に与えていることを検討することは、重要だからである。
条例数の集計方法は、平成16年7月12日現在の東京都庁ホームページ(条例・法規集)に掲載されている条例を、著者が新設条例と改正条例に分類して集計した。
(2)分析結果
平成元年から平成16年5月15日までの東京都の条例制定数と条例改正数を示したのが、表1である2)。はじめに、新たに制定された条例数を見てみると、平成元年から平成11年で最も制定数が多いのは、平成9年の17本である。これと比較して、地方分権一括法が施行された平成12年に制定された条例数は、50本である。平成9年の17本の約3倍もの条例が制定されているのである。しかし、平成13年以降に制定された条例は、11年以前と大きくかわらない。
次に、条例の改正数を見てみると、平成12年の条例改正は189であり、平成11年の123と比べても大きく増加している。そして、平成13年以降も、改正数は、平成11年以前に比べて、多いことがわかる。
条例制定数と条例改正数の合計を見てみると、平成12年に大幅に増加し、その後も高い数値を維持していることがわかる。なお、平成16年のデータは、平成16年5月15日現在のものであるが、5ヶ月間で、103本の条例制定・改正が行われているため、それ以前と比較してみると、大幅に増加していることがわかる。
以上のように、平成11年・12年から条例制定数は、大幅に増加しているといえよう。
表 1
|
|
元年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
6年 |
7年 |
8年 |
9年 |
10年 |
11年 |
12年 |
13年 |
14年 |
15年 |
16年 |
|
新設数 |
6 |
6 |
3 |
8 |
4 |
7 |
7 |
1 |
17 |
3 |
15 |
50 |
11 |
19 |
7 |
5 |
|
改正数 |
90 |
103 |
70 |
119 |
60 |
119 |
107 |
102 |
64 |
100 |
123 |
189 |
140 |
171 |
149 |
98 |
|
合計 |
96 |
109 |
73 |
127 |
64 |
126 |
114 |
103 |
81 |
103 |
138 |
239 |
151 |
191 |
156 |
103 |
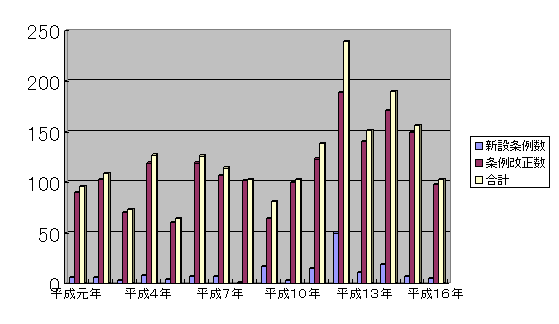
(3)条例数の変化と地方公共団体の自主性向上との関係
このような条例制定数の増加は、地方公共団体の自主性が向上したことによるものなのだろうか。今回のレポートの目的は、条例制定数・改正数がどのように変化したのかという量的な側面について検討することであるが、以下では、その質的な側面に関して若干の考察を加えたい。
東京都は、地方分権一括法の施行に伴う関係法令の改正に対応するための条例制定・改正を、平成11年第4回定例都議会、また平成12年第1回定例都議会において、地方分権一括法関係条例というかたちで行った3)。
例えば、新設条例数は、平成12年に50本となりそれ以前と比較しても大幅に増加している。この新設条例の内容は、その多くが手数料に関する条例である4)。平成12年における、手数料に関する新設条例数は、27本である5)。このような条例は、これまで機関委任事務として都知事が規則で定めていたものを、条例化したものである。つまり、これらの手数料条例は、都が自主的に制定したものではなく、分権改革にともなう法令の改正に対応するために制定された条例である。このような条例を以下では便宜的に対応条例と呼ぶことにしたい。
このような対応条例数の増加は、地方公共団体の自主性・自立性が向上しとことを意味するのだろうか。一見、この対応条例数の増加は、自主性・自立性が向上したと解釈することができないように思われる。なぜならば、この条例は、当然に制定・改正が予定されているからである。
しかし、このような対応条例も、これまでに比べると、地方公共団体の自主性・自立性が向上したと考えることができる。例えば、手数料条例に関して、これまでその値段は、国で基準を決め、それを規則で定めていたのであるが、手数料を条例化することは、その値段は地方公共団体で決定することになる。そこには、地方議会も関与するのである。このような意味では、対応条例の制定・改正の契機は、国から与えられるものであるが、その内容は地方公共団体が決定しているのである。すなわち、この対応条例の増加は、地方公共団体の自主性・自立性が向上したのである。
4.おわりに
以上のように、東京都における条例の制定数と条例の改正数は、平成11年、また地方分権一括法の施行された平成12年以降、増加していることがわかった。その多くが地方分権一括法に対応するための条例であるが、このような条例も、その制定・改正の契機は、国から与えられるのであるが、その内容は、地方公共団地が独自に決めるのであり、地方公共団体の自主性・自立性が向上したことを意味する。
注)
1)新藤宗幸『地方分権 第2版』(岩波書店・2002)215頁参照。
2)東京都庁のホームページ(条例・法規集、http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html)より集計.
3)東京都地方分権推進計画は、次のように述べている。
「国においては、機関委任事務制度を平成12年3月末をもって廃止することとし、地方分権一括法により関連法を改正した。これらの法令改正に対応して、都も条例、規則等の整備を行う必要がある。このため、条例の制定・改廃が必要となるものについては、条例案を平成11年の第4回定例都議会に提出することを目途に準備を進めることとする。規則についても、これに準じたスケジュールで制定・改廃を行うものとする。なお、その際には、機関委任事務制度の廃止前に行われた申請の取扱いなどについての経過措置も必要に応じて定めていくこととする。また、分権改革の成果を積極的に生かし、都独自の施策展開等を行うための条例化を含めた自治立法については、平成12年4月以降も随時行っていく。」
4)手数料に関する新設条例について例えば、租税特別措置法施行令に基づく譲渡予定価額審査に係る手数料に関する条例、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律関係手数料条例、計量法関係手数料条例、旅券法関係手数料条例、旅行業法関係手数料条例、通訳案内業法関係手数料条例、東京都都市計画局関係手数料条例、高圧ガス保安法関係手数料条例、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例、火薬類取締法関係手数料条例、武器等製造法関係手数料条例、電気工事士法関係手数料条例、電気工事業の業務の適正化に関する法律関係手数料条例、東京都保育士試験手数料条例、東京都衛生局関係手数料条例、東京都労働経済局関係手数料条例、宅地建物取引業法等関係手数料条例、東京都河川流水占用料等徴収条例、東京都砂防設備占用料等徴収条例、建設機械の打刻又は検認に関する事務手数料条例、砂利採取法に基づき河川管理者が行う事務に係る手数料に関する条例、介護保険法関係手数料条例、教育職員免許法関係手数料条例、銃砲刀剣類所持等取締法に基づき東京都教育委員会が行う事務に係る手数料に関する条例、東京都消防関係手数料条例.
5)東京都ホームページ(総務局総務部文書課 条例案概要 2004年7月22)より集計.