���݂̎s���������̓����Ɠs���{�����x�ɗ^����e���ɂ���
��w�@�����o�c������
45031034-5�@���@���@�@��
�P�D�͂��߂�
�Q�D���݂̎s���������̓���
�R�D�s���{�����x�ɗ^����e��
�R�D�P�u�{�����_�v
�R�D�Q�u�{�������_�v
�R�D�R�@���_�̍l�@
�S�D����
�P�D�͂��߂�
�����Ȃ̒��ׂɂ��ƁA����16�N7��16�����݁A�@�苦�c���578�ݒu����A�W����s������1,953�ɂ��y��ł���B���N7��1�����݂̎s��������3,099�ł��邪�A�����@�苦�c��A���ׂĊ����ʂ荇���������Ɖ��肷��ƁA�s��������3,099����1,724�ɂ܂Ō������邱�ƂɂȂ�B
�܂��A���N4��1�����݂̐����ł́A�@�苦�c��A�C�Ӌ��c��A����������Ɋւ���@�ւ�ݒu���č������������̒c�̐���2,335�A�@����727�ɂ�����Ă���i�����|�[�g���A�}�\�Q�j�A�����̐�������A��������܂߂��ׂĂ̍��������������Ɖ��肵���ꍇ�ɂ́A�s��������1,500���x�ɂȂ���̂Ɨ\�z�����B
����ɁA���ʂ̒ʏ퍑��ɂ����āA�s���������Ɋւ��鍇���O�@����������Ɏ������B�����O�@�Ƃ́A���Ȃ킿�u�s�����̍����̓��ᓙ�Ɋւ���@���v�A�u�s�����̍����̓���Ɋւ���@���̈ꕔ����������@���v����сu�n�������@�̈ꕔ����������@���v�ł���A����ɂ�蕽��16�N�x���ȍ~���s���������𐄐i����d�g�݂���������邱�ƂƂȂ����B�V���Ȗ@�����̎����ɂ��A������s�����̍����Ɍ����������͑������̂Ǝv����B
���N�[���ɂ����ẮA���ݐi�s���Ă���s���������̍ŐV�̓�����c������ƂƂ��ɁA���ꂪ���s�̓s���{�����x�ɗ^����e���A�Ռ����ɂ��āA��s�������̍l�@�������Ȃ��猟�����邱�ƂƂ������B
���̂����ŁA�s���{�����x���邢�͓��B���Ƃ������A�킪���ɂ����邠��ׂ��L�掩���̐��x�̎p�ɂ��čl����ɂ������Ă̎����������邱�Ƃ����҂�����̂ł���B
�Q�D���݂̎s���������̓���
�܂��A���݂̎s���������̍ŐV�̓����ɂ��ďڍׂ����Ă������Ƃɂ���B
�`���ɂ��q�ׂ����A�����Ȃ̒��ׂɂ��ƁA����16�N4��1�����݁A�@�苦�c���534�ݒu����A�W����s��������1891�ɋy��ł���B�i�ʕ\�P�j
�Ȃ��A�ŐV�����ɂ��āA����16�N7��16�����݂ł݂�ƁA�@�苦�c���578�ݒu����A�W����s������1,953�ɂ��y��ł���B
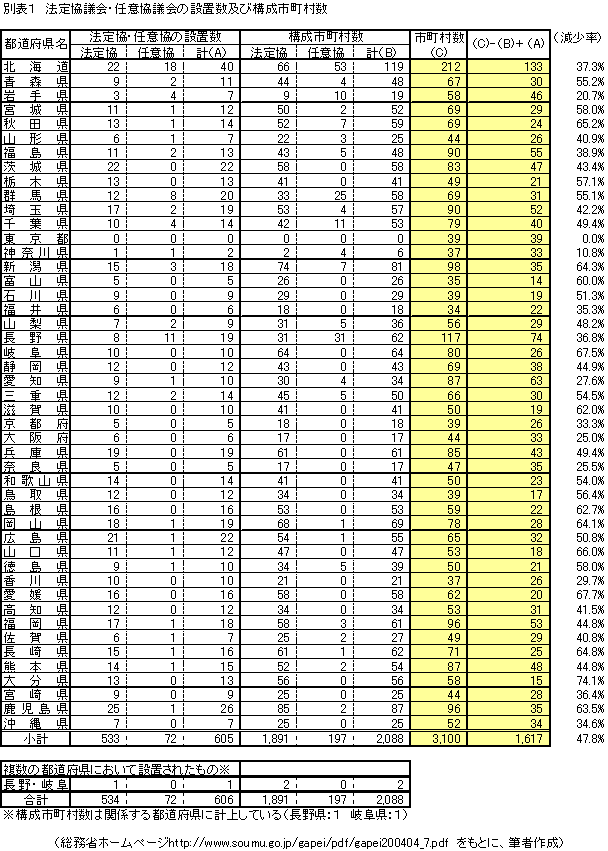
�ȏオ�A�@�苦�c���єC�Ӌ��c��̑S���̐ݒu�ł���B
�܂��A��������܂߂������ł݂�ƁA����ɑ����̎s�������W���Ă��邱�Ƃ��킩��B�i�}�\�Q�j
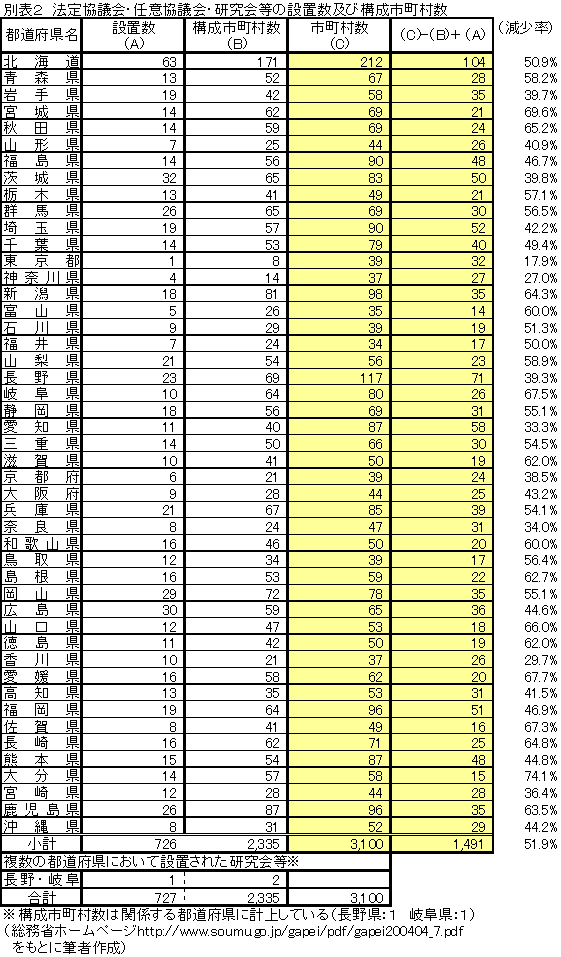
�ȏ�̂悤�Ȏ�������ʊς��Ă݂�ƁA�@�苦�A�C�Ӌ��̐ݒu���Ō����s�������́A�P�j�S�����v�ł́A5����̌����������܂��A�Q�j�s���{���ʂł́A7������s�����̌������N���錧����������i�啪���j�A�R�j5������s�������̌������N����ƌ����܂��s���{����22���ɏ��A�Ƃ��������Ƃ��m�F�ł���B
�R�D�s���{�����x�ɗ^����e��
����ł́A���ݐi��ł���s���������́A�s���{�����x�ɂǂ̂悤�ȉe����^����̂��낤���B
���݂̎s���������Ɠs���{�����x�Ƃ̊W�ɂ��Ę_�����_�l�͂��������邪�A�����ł́A������Ǝv����2�̐�s���������グ�A������Δ䂳���M�҂̌������q�ׂ邱�ƂƂ������B
�܂����グ��̂��A�s�����������i�ނ��Ƃɂ���ĕ{���@�\�̋����i�ނƂ����c�_�ł���B�����ł́A���̂悤�ȋc�_���A�X��A���Ɂu�{�����_�v�ƌĂԂ��Ƃɂ���B
�R�D�P�@�u�{�����_�v
�u�{�����_�v�̗�����Ƃ�_�҂̈�l�́A���X�ؐM�v�ł���B�ނɂ��A�u�{���͂���܂Œ��Ԑ��{�Ƃ��āA�L��I�Ȏd���⍑�Ǝs�����̘A�������A���x�Ő��I�ȋƖ��Ƃ������������ʂ����Ă����B��������͒m���̐����I�|�X�g�̏d�݂������A���v�h�m���̐��_�`���⍑���ւ̉e���͂������Ă���B�Ƃ��낪����A�s�����������i�ނƁA���ΓI�ɕ{���@�\�́w���x���Ă������Ƃ��z�肳���B�v�i���X�@2004�@241�|242�Łj�Ƃ��A�߂������̕{���@�\�̕ω��ɂ��āA���̂Ƃ���܂Ƃ߂Ă���B
�u�@�s�����d���Ɠ�d�s���̉����ŕ{���s���̋����i�ށB
�A�����ł��Ȃ������̐����⊮�@�\�����܂�B
�B�����s�����i�s�s�����́j�ւ̎����E�����Ϗ����i�ށB
�C�{���̍L��s���@�\���d������A�{�����z�����A�g�����܂�i�{���A���j�B
�D������̍X�Ȃ錠���Ϗ��i���������^�̌������ƂȂǁj���i�݁A�L�挠�����g�傷��B�v
�i���X�@�O�f���@242�Łj
�����āA�����T�̗\�z�����ω��̂����A�u�@�ƇB�͕{����������v���ƂȂ�B����������A�C�ƇD�Ƃ����V���ȋ@�\���������낤�B�A�͍���̒������������Ɨ��ނ��A�����̐����⊮�͔����Ēʂ�܂��B�v�i���X�@�O�f���@242�Łj�Ƃ��A���̐�̒������̕ω��Ƃ��āA���̂悤�ȃV�i���I����Ă���B���Ȃ킿�A
�u�@�������̎��升�����i�݁A�V�����������܂��i���A�H�c�A�X�������Ȃǁj�B
�A���B���ւ̈ڍs�i�{�������{���̃u���b�N�@�ւ̓����j���s����B
�B���������A�A�M���ւ̈ڍs�i���@�����B���ɂ̕������Ƃ̊m���j�����肤��B�v
�i���X�@�O�f���@242�Łj
�Ȃ��A���̃��|�[�g�ł͎��܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��������A���ݐi�s���̓����Ƃ��ẮA�����ɂ��s���{������̎��������̈ڏ����邱�Ƃ��ł��鐭�ߎw��s�s�⒆�j�s�A����s�Ƃ�������s�s���x�̓K�p��ڎw���č������u�����铮�����S���I�Ɍ�����Ƃ���ł���i���ߎw��s�s��ڎw����Ƃ��āA�l���s�𒆐S�Ƃ����V����E�l���Βn�捇�����c��≪�R�s�𒆐S�Ƃ������R���쐭�ߎs�\�z�������c��j�B
�܂��A���Ð�s�E�R�����������c��̂悤�ɓs���{�������z���Đݒu����Ă��鍇�����c������邪�A���̂悤�ȓ����͓��ɁA�s���{���̋�̓I�ȁu�������v��ς��铮���Ƃ��ĕ��ɂ�蒍�ڂ���Ă���Ƃ���ł���B
����ɂ́A�s���������̓����܂��āA������s�����ɗ��悵�Ď����Ϗ��𐄐i����\�z����N����Ă���B�É����̗Ⴊ����ł���B�i�ȉ��A�É����@2003�j
�É����̍\�z�ɂ��A
�u������̎s�������A���̋K�͓��ɂ��A�����I�Ȑ���̂ق��A�Ⴆ�A���I�Ȑl�ނ̊m�ۂ�����ł��铙�̗��R����A�ی������A�܂��Â���A���瓙�̕���ŏZ���̃j�[�Y�ɑΉ������T�[�r�X���\���ɒł��Ȃ��\��������B���ɁA�w��s�s�Ƃ���ȊO�̎s�����Ƃ̊Ԃł́A�s������ՂƎ����\�͂ɑ傫�Ȋi���������鋰�ꂪ����B�܂��A�������Ă���T�[�r�X�̒��ɂ́A�Z���ɐg�߂ȂƂ���ő����I�ɒ���邱�Ƃ��]�܂������̂�����B
���̂悤�Ȋϓ_����A�����̏Z���ɐg�߂ȍs���T�[�r�X�����Ȋ����I�Ɏ��{���邱�Ƃ��\�ȑg�D�̐����\�z���Ă������Ƃ��d�v�ł���B�v
�Ƃ��A��̓I�ȍ\�z�Ƃ��āA
�u�E�V���ɒa������w��s�s�i���|�[�g�M�Ғ��F�V�u�É��s�v������l���s�𒆐S�Ƃ����u�V����E�l���Βn�捇�����c���v�j�́A�n��̉ۑ�ɑ����I�ɑΉ��ł���悤�A���̎�����啝�Ɉڏ�����V�^�w��s�s���`������B
�E�V�^�w��s�s�ȊO�̒n��́A�L��A����ݒu���āA�L��A���Ƌ����̎s�����Ō����Ƃ��ĐV�^�w��s�s�Ɠ��l�̋@�\��S�����ƂƂ���v
�Ƃ��A�������̋@�\�����w��s�s�ƍL��A���ɍĕ҂��邱�Ƃ���Ă���̂ł���B
���̂悤�Ȓ́A���̑�����̐ϋɓI�ȓ����Ƃ��č���̓W�J�����ڂ����Ƃ���ł���B
�R�D�Q�@�u�{�������_�v
�����A�s�����������i�ꍇ�ł��A���ΓI�ɂ͂��̖����͒ቺ������̂́A�{�����̂̑��݈Ӌ`�͖����قǂ̉e���͂Ȃ��A�{���@�\�͏����̕����Ɍ������Ƃ��邱�Ƃ�O��Ƃ��āA���݂̎s���������̓�����s���{���̂������₤�^���Ƃ��ĂƂ炦��^���Ƃ��ׂ��Ƃ������ꂪ�\������Ă���B���̂悤�ȗ�����A�����ł͉��Ɂu�{�������_�v�ƌĂсA��ɏq�ׂ��u�{�����_�v�̋c�_�ƑΔ䂷�邱�ƂƂ������B
�u�{�������_�v�̂悤�ȋc�_�͑����̘_�҂������Ă��邪�A�����ł͌��c�W���̋c�_�����グ�邱�ƂƂ������B
���c�ɂ��A�s�����������i�W���钆�ł̓s���{���ɂ��āA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u���݂̎s�����������i�W����ƁA�s�����Ԃ̋K�́E�\�͂̍��͈�w�g�債�A�s���{���Ɋ��҂��������̑傫���́A�n��ɂ���ĔZ�W�����܂����̂ƌ����܂��B�������A�s���{���̖����͑��̂Ƃ��Ēቺ�̕����Ɍ��������̂́A����͎�ɓ���s�ȏ�̎s�ɑ��Ăł���A�������K�������\���Ȏ��������̈ڏ��͊��҂ł��Ȃ��B�s���������̐i�W��҂����ł́A�s���{���̎����ʂ̍팸��֗^�̑啝�ȏk���ɂ͂Ȃ���ɂ����A�s���{���̑��݈Ӌ`�������قǂ̉e���͐����Ȃ��\���������̂ł���B�v�i�؍��ďC�A����ҁ@2003�@217�Łj
�Ƃ��A�����
�u�S���I�Ȏs���������̓����Ɍĉ����āA���B���Ȃǂ̓s���{���ĕҘ_���ɂ킩�ɒ�N�������B�������A�܂��n�������ꊇ�@�̎�|�ɉ����悤�Ȍ`�œs���{���Ǝs������Γ��E���͂̊W�ɉ��P���A�s���{���̖��������߂Č��������v�𐄂��i�߂邱�Ƃ��挈�ł���i�ȉ����j�v�i�؍��ďC�A����ҁ@�O�f���@217�Łj
�Əq�ׂĂ���̂ł���B�����āA�s���{���̏������ɂ��ẮA�ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u������G�c�ɂƂ炦��A�s���{���̋@�\�͏����̕����Ɍ��������Ƃ�O��ɁA�s���{���̎����̂����S���I�ɑΉ����ׂ����̂�{���@�\�Ƃ��A����ȊO�̌����n��P�ʂőΉ����邱�Ƃ��]�܂������̂�s���{���̒n��@�ւ�s�����Ԃ̐����⊮�̋@�\�Ɉς˂�Ƃ������ƂɂȂ낤�B
���̂����A�{���@�\�������I�ȈӖ��ōL�掩���̂ƌĂԂɂӂ��킵���@�\�ł���B���B���ȂǓs���{���ĕҘ_�́A���̋@�\�̊g�[�����߂���̂ł���B�v�i�؍��ďC�A����ҁ@�O�f���@222�Łj
�R�D�R�@���_�̍l�@
�ȏ�A�i�W����s�����������A�s���{�����x�ɗ^����e���ɂ��Ę_������\�I�Ș_�l���݂Ă����B
�����Ŏ��ɁA�����̋c�_�ɂ��Ď�̍l�@���s���A�����_�ł̕M�҂̌������q�ׂ邱�ƂƂ������B
���_����ŏ��ɏq�ׂ�A�M�҂́A����̓s���{���́A�����ނˁu�{�����_�v���q�ׂĂ���悤�ȕ����ɐi�ނ̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B
���̗��R�Ƃ��ẮA�P�j�s�����������A�����_�ł́A���{�^�}�̖ڕW�Ƃ���1000�i����16�N�x���j�ɂ͓��B���Ȃ��Ɨ\�z�������̂́A�����|�[�g�̖`���Ŏ������@�苦�c��A�C�Ӌ��c����̎�������A2000�͑傫������邱�Ƃ��\�z����邱�ƁB�Q�j���̂��Ƃ܂��A�啪���Ȃnj����̎s���������������錧���o�Ă���Ɨ\�z�����Ɠ����ɁA�s���{���̎��������̈ڏ��ΏۂƂȂ�A��s�s���x�K�p�̒c�́i���ߎw��s�s�A���j�s�A����s���j�̑������\�z����邱�ƁB�R�j���X�ؐM�v���w�E����悤�ȁu�{���̍L��s���@�\���d������A�{�����z�����A�g�����܂�v�i���X�@�O�f�j�Ɨ\�z����邱�ƁA����������B
�Ƃ���ŁA�{������z����L��s���@�\�Ɋւ��āA��Ɏ��グ�����c�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B���Ȃ킿�A�u������������A�s���{�����ɕύX�������Ă܂ŁA���̋��⌠�����g�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǂ̍����������L��s�����v�͑��݂��Ȃ��B�i�����j�L��s�����v�́i���j�A���̏o��@�ւ̋����A���H�@�E�͐�@���̉����ɂ�鍑�̎����ւ̈����グ�A����@�l�̐ݒu�Ȃǂɂ���Ă�����x��������āv�i�؍��ďC�A����ҁ@2003�@217���j����Ƃ��Ă���̂ł���B
�������Ȃ���A���̓_�ɂ��ĕM�҂́A�ɂ킩�ɓ��ӂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
���̓_�ɂ��āA��Ɉ��p���������ŁA���c�����݂�����x�������Ă���Ƃ������H�@�E�͐�@��̎����Ȃǂ��ɍl����B
���Ȃ킿�A�����̎����ɂ��ẮA���݂ł́A�n��̎��Ȍ���̊ϓ_����́A�ނ���L�掩���̂��S���ׂ������Ƃ�����̂ł͂Ȃ����B�����Ă��̍ۂɂ́A���Ƃ��A�ꋉ�͐�ł́A�����̌��ɂ܂����闬���L�����K�͂ȉ͐�̏ꍇ�A���i�e�n�������ǁj�Ɠs���{���������ĊǗ����Ă��錻������߁A�s���{���̉�������L��A���i�n�������@��291���̂Q�j��A�n�������ǂ��܂߂������I�ȊǗ��̕��@���͍������ׂ��ł͂Ȃ����ƍl���邩��ł���B�͐�Ɠ��l�A�Ǘ��������Ă��铹�H�̏ꍇ�����l�̂��Ƃ�������̂ł͂Ȃ����B
���{�̑�27���n�����x������\�ł��A�u�s���{�������������L�掩���̂Ƃ��āA���E�I�Ȏ���������ϋɉʊ��ɂ��̖������ʂ����Ă������߂ɂ́A���x�ȃC���t���̐����A�o�ϊ����̊������A�ٗp�̊m�ہA���y�̕ۑS�A�L��h�Б�A���̕ۑS�A���ʐM�̍��x���Ȃǂ̍L��I�ȉۑ�ɑΉ�����\�͂����߂Ă������Ƃ����߂���B�s���{���ɂ͍�����ڏ�����錠���̎M�Ƃ��Ă̖����������������҂���Ă���A�y�n���p�A�n���ʁA�Y�ƐU���A���y�ۑS�Ȃǂ𒆐S�ɁA������s���{���ֈ�w�̎��������̈ڏ����i�߂���ׂ��ł���B�v�i��27���n�����x������@2003�@21�|22�Łj�Əq�ׂ��Ă���̂ł���B
�S�D����
���݂̓s���{�����Ƃ�܂����ɂ��ẮA�O���ł݂��Ƃ���A�s���������̐i�W�ɂ�茧���s�������������߂��ɂȂ錧�̏o�����\�z�����B���̂悤�Ȓ��ŁA�É����̎��g�݂̂悤�Ɍ��̑�����ϋɓI�Ɏ����ڏ��𐄐i���悤�Ƃ��铮�����o�Ă����B
�s����������̕{���̋@�\�ɂ��ẮA�����i�s����Ƃ����c�_���������ŁA�{���@�\�͏������ׂ������ɐi�ނׂ����Ƃ���c�_������B
�s���������̓�����É����̎��g�݂��݂�A�{���@�\�̋��ɂ��Ă͂�����x�����̂��̂ƂȂ�Ɨ\�z�����B
�����A�����^�Љ�̐i�s�ɂ��n��̎��Ȍ���̗v�����邢�́A�����I�Ȍ���̌`���Ƃ������ϓ_����A�s���{���̋@�\�g��̗v�����܂�����Ƃ�����̂ł���B
�i�ȁ@��j
���Q�l������
�E �؍��Βj�ďC�E����W�ҁw�����̂̑n���Ǝs���������x�i2003�N�@���@�K�o�Łj
�E ���X�ؐM�v�w�n���͕ς��邩�|�|�X�g�s���������x�i2004�N�@�}�����[�j
�E �����������v������w�����������v��������x�i2003�N�@�����j
���Q�lWEB�T�C�g��
�E �����Ȏ����s���Ǎ������i�ہ@http://www.soumu.go.jp/gapei/index.html
�E ��27���n�����x������\
�i2003�N�@�����ȁ@http://www.soumu.go.jp/singi/pdf/No27_sokai_7_4.pdf�j