2005年度演習2ndセメスター2ndクール
外国人労働者の年金に関する二国間協定について
公共経営研究科修士課程2年
1.問題意識
日本の外国人労働者が社会保険に加入しない主な要因に、わが国では社会保険加入と同時に年金と介護保険に加入しなければならない点が挙げられる。「できる限り短期間で、できる限り多くの金額を稼いで帰国したい」という意識を持ち、将来母国への帰国を念頭に置いている外国人労働者にとって、日本の年金や介護保険への掛け金負担は「払い損」になる。外国人が社会保険に加入する際に、そのような年金や介護保険への加入が義務付けられているために、外国人の社会保険加入率が低くなっているのである。その結果、外国人未払い医療費問題が発生し、自治体財政および地域の病院経営に少なからず影響を与えている。
2.わが国における年金制度の概要
現行の年金制度では、わが国に居住する20歳以上の成人は、全員、国民年金に加入するよう義務付けている。国籍による区別は設けられていない。外国人といえども、わが国に居住する以上、国民年金に入ることが原則である。さらに、厚生年金保険の適用事業所(一般的には、常時5人以上の従業員を使用する事業所)に勤めている場合は、厚生年金保険の被保険者となる。ここでも、外国人と日本人の区別はない。
現在の年金制度では、年齢による特例はあるものの、原則として65歳に達した時に最低25年の加入期間がないと、老齢給付を受けられないことになっている。外国人といっても、その例外ではない。仮に、外国人がわが国に永住するつもりで働き、転職を続けたとしても、わが国で働き続ければ、やがて25年の加入期間を超え、老齢給付の受給資格ができる。受給資格さえできれば、外国(母国)で給付を受け取ることも可能である。その面では、国境を越えた給付は、現行制度で十分実現されている。しかし、加入年数が25年に達する前に、なんらかの理由で日本を去らなければならないとしたらどうなるか。あるいは、日本に永住するつもりがない外国人の年金はどうなるのか。ここで、本研究で扱う新来外国人の滞在期間を以下に示す。
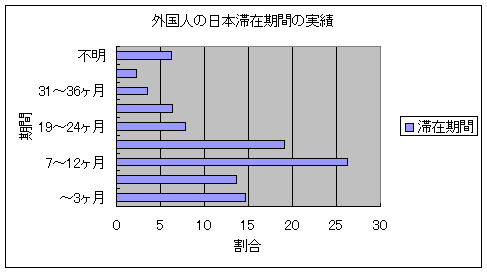
出所:労務行政研究所「外国人労働者受入れの現状と社会的費用」より作成
新来外国人は、1年程度日本で働き、帰国し、しばらくして再度来日し出稼ぎに従事するといわれている。仮に、外国人がトータル10年間わが国で働き、母国に帰国したとする。現行制度で老齢給付をもらえるようにするには、再度日本に来て15年働き、加入期間を25年にしなければならない。仮に25年に達しないと、それまでの掛け金は、完全に「掛け捨て」、つまり「払い損」となる。脱退一時金の制度もないので、掛け金の一部を回収することさえできない。日本の社会保険に加入する際は、このような年金制度とセットとなっているため、外国人が社会保険の加入に抵抗感を感じることはやむを得ないといえる。
このように、将来わが国を離れる(将来母国への帰国を考えている)外国人に対して、現行年金制度は、はなはだ冷たいといわざるを得ない。そして、問題はこれだけでは終わらない。わが国に定住し、将来帰国を考えている外国人は、母国でも加入期間不足から老齢給付を受けられない可能性が出てくるからである。どの国でも年金制度は、長期の加入期間を前提に組み立てられている。わが国と外国人労働者の出身国での年金加入期間が分断されている限り、加入年数不足の問題は常についてまわる。このような状況では、わが国で働くことのリスクがあまりにも大きく、優秀な労働力が集まりにくくなるだろう。何より、こうした情報を知らずに、祖先の祖国日本で働きたいと来日する外国人の老後の人生を不安定な状態にしている現実がある。
このような問題を解決するために、西欧諸国では、「年金保険加入期間の通算」という措置がとられている。具体的にどのように取り決められているかは、ドイツとセルビア・モンテネグロ[1]の年金に関する二国間協定を例に論じていきたい。
3.ドイツを取り上げる意義[2]
ドイツの外国人をめぐる歴史は、その地政学的な位置の他、ドイツ特有の諸条件によって規制されており、わが国にとって直接の参考になるわけではない。ただ、仮にドイツから学ぶべきものがあるとすれば、それは何よりもその周到な法制度とその運用の内容であり、また、特に現在のドイツの新しい政策に顕著な、「基本姿勢」であると、東京外芸大学教授野川忍氏は著書「外国人労働者法」の中で述べている。明治時代に制定された行旅病人及び行旅死亡人取扱法を根拠に、外国人未払い医療費を補填しているような日本の外国人法制は、実定法の体系としても、運用の実態としても、必ずしも十分に機能しているとは言い難い。そうした日本の現状にとって、日本と同様に敗戦の荒廃から出発し、勤勉な国民性と経済力とで戦後の高度成長を成し遂げ、しかも、外国人についても、移民ではなく、一時的滞在を基本とするという点でも類似するドイツの、様々な試行錯誤から発展してきた法と行政および民間の外国人への対応は、貴重な参考となり得よう。
また、ドイツの経験が痛みを伴うことであったことは間違いないのであって、現在の政府も、開放的な政策の方が国益をより高めると考えているのではない。ただ、戦後のドイツは、ナチの悪夢に鑑みて、世界の中で圧政に苦しむ者の味方であることを常にアピールし続ける必要があった。世界で最も寛容と言われる難民の庇護規定を、憲法たる「ボン基本法」に置いているのもそのためである[3]。そして、この原則的立場を支えているのが、ドイツ語に頻繁に登場する「ゾチアール(Sozial)」という理念である。通常「社会的」などと訳されるが正確ではない。それは、日本語の「共生」に近く、しかしより積極的な内容を有する概念であって、強者の自由を、虐げられた者を生む限りにおいて制約するという意味合いが強い。
つまり、ドイツが歩もうとしているのは、リスクの増大を覚悟の上での、ゾチアール(Sozial)の理念の国際的な拡大の道であるともいえよう。言い換えれば、東西対立の終焉の陰で、ますます深刻化するドイツ南部の困窮と、ドイツ東部の混乱を前にして、ドイツの国家百年の大計をいかに現実のものとしていくか、東欧の人々や世界中からの難民の受け入れを通じて、ドイツは一つの解決の試みを提示しているともいえる。外国人労働者受け入れの様々な具体的な法制度、行政の対応に並んで、日本がドイツから学ぶべきものは、まさにこうした基本姿勢と、その構築の方法であるといえるのではないだろうか。
4.二国間協定の実際−ドイツとセルビア・モンテネグロを事例として[4]
これまでの考察から、わが国の年金保険は加入期間の問題で何らかの調整が必要なことが明らかになった。そこで、次に、出稼ぎ外国人労働者の受け入れ国であるドイツと送り出し国であるセルビア・モンテネグロを取り上げ、年金加入期間の通算の問題が二国間協定でどう処理されているかを見ていきたい。
ドイツで働いている外国人労働者は、2003年には485万6000人に至った。出身国別にみて、最も多いのがトルコ人で約187万8000人、イタリア人が60万1000人、セルビア・モンテネグロ人はそれに続く約56万8000人であった。
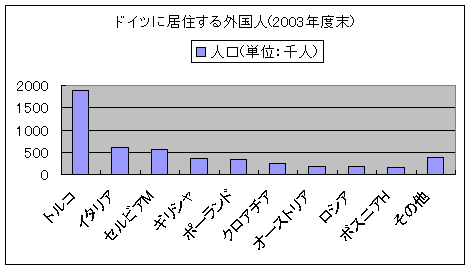
出所:ドイツ連邦統計庁HP(http://www.destatis.de)
セルビアMはセルビア・モンテネグロ、ボスニアHはボスニア・ヘルツェゴビナを示す。
セルビア・モンテネグロの前身、ユーゴスラヴィアにとって西ドイツは重要な労働市場であった。外国で働いているユーゴスラヴィア人のうち、半数強が西ドイツで職を得ていた。両国の関係は、68年の職業紹介協定締結以後強まったが、それ以前から労働者の移動があった。そのため、社会保障に関する国際協定は、すでに1956年に結ばれている。先進国と後進国の協定としては、最も長い歴史を持つものの一つであるため、ドイツとユーゴスラヴィアを事例として取り上げていきたい。なお、ユーゴスラヴィアが崩壊し、セルビア・モンテネグロとなった今でも、ドイツとセルビア・モンテネグロ両国間の社会保障に関する国際協定は、56年に締結された協定がベースとなっている。以下の表にドイツとセルビア・モンテネグロの老齢年金制度をまとめる。
ドイツとセルビア・モンテネグロの老齢年金制度
|
|
ドイツ |
セルビア・モンテネグロ |
|
受給資格 |
加入期間35年以上で63歳から、15年以上で65歳から受給資格ができる。ただし、多くの例外規定あり。 |
年齢要件:男65歳、女60歳 加入年数:男40年、女35年 最低加入期間は15年。 |
|
年金額 |
R=(P*B/100) *(J*St) R:年金、P=個人算定基礎の一般算定基礎に対する比率 B:一般算定基礎(過去3年間の全被保険者の平均賃金) J:加入期間(年数) St:加入期間に対する加算率(年金の種類に応じて1.0−1.5) |
加入年数15年の場合、男は基準額の35%、女は40%支払われる。その後は、1年増えるごとに2%が加算されていく。ただし、85%は超えない。基準額は、過去10年間の所得を基に計算される。 |
|
年金水準 |
総報酬額(税引き前の報酬額)の46.0% |
資格要件をすべて満たした場合、平均賃金の60%前後の水準になる。 |
|
掛金 |
基本賃金の18%で労使が折半する |
企業負担分:「収益」の9.5%。労働者分担分:個人所得の14.7%。 |
上の表は、ドイツとセルビア・モンテネグロの老齢年金制度を、受給資格要件、年金額、年金水準、掛金の四点についてまとめたものである。両国とも、基本的には同じ制度だといえる。ドイツもセルビア・モンテネグロも、最低加入年数を15年としている。この点が、年金加入期間の通算制度と大きく関わってくる。
ドイツとセルビア・モンテネグロの間で結ばれている社会保障に関する協定のうち、年金分野での基本的内容は、両国で働いた期間を通算して年金の加入期間とすることである。例えば、セルビア・モンテネグロで10年働いたのち、ドイツで職をみつけて25年働いた人がいたとする。もし、加入期間の通算がなければ、彼はセルビア・モンテネグロの年金をもらう資格がないことになる。一方、ドイツの年金はもらえるが、その額も相当少なくなる。期間通算定式は、セルビア・モンテネグロでは次のようになっている。
M=(MO*%UMS) * (MSY/UMS)
M:年金額、MO:年金基準額、%UMS:加算加入総年数に基づく比率、
MSY:セルビア・モンテネグロでの加入年数、UMS:加算した総年数
具体的な数値を当てはめて考えてみたい。彼の年金基準額を15,000ディナール[5]とすると、彼がセルビア・モンテネグロの年金財団から受け取る額は、次のようになる。
M= (15,000*75%) * (10/35)
=3214,29ディナール
仮に、通算の規定がなければセルビア・モンテネグロから受け取る年金はゼロになるのだから、彼は協定の恩恵をこうむっているといえよう。ドイツから受け取る年金も、これとほぼ同じ方法で計算される。
このように、セルビア・モンテネグロからドイツに出稼ぎに来ている外国人は、ドイツで働き、ドイツの年金制度に加入している限り、母国に帰国してもセルビア・モンテネグロの年金を受け取ることができる。
一方、わが国では、先に述べたとおり、外国人労働者が日本の年金制度に加入していても、加入期間が25年に満たなければ、母国に帰国した際、日本の年金に納めた額は掛け捨てとなる。外国人が社会保険に加入する際、このような年金制度とセットで加入しなければならないため、社会保険の加入率が低くなる。その結果、自治体財政が影響を受けていることは先に述べたとおりである。従って、ドイツとセルビア・モンテネグロに見られるような年金の二国間協定を締結すれば、わが国における外国人労働者の社会保険加入率は向上するものと思われる。また、二国間協定の問題は、わが国で働く外国人労働者のみの問題ではなく、海外で働く日本国民にとっても重要な問題であるという点も付け加えておきたい。
5.二国間協定締結に関する留意点
日本がブラジル等と年金に関する二国間協定を締結する際、留意すべき点もあるように思われる。ユーゴスラヴィア(現セルビア・モンテネグロ)人の西ドイツ(現ドイツ)への出稼ぎは、両国の間で職業紹介協定が結ばれた1968年を境に、飛躍的に増大した点を忘れてはならない。それまで10万人に達しなかったユーゴスラヴィア人出稼ぎ労働者は、69年に22万人、70年に37万人、71年に45万人と増加し73年には53万人に至った。
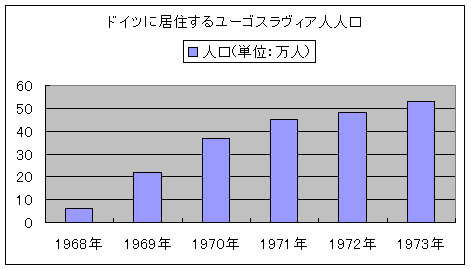
出所:ドイツ連邦統計庁HP(http://www.destatis.de)
また、オランダでも、1969年にモロッコと年金に関する二国間協定を締結したことで、以降オランダにおけるモロッコ人労働者が加速的に増加している。
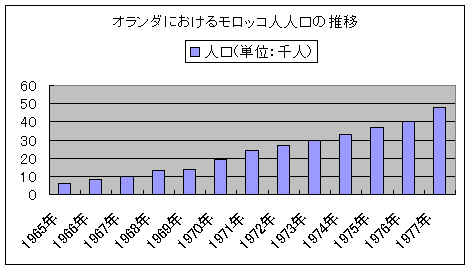
出所:WRR(1979), Ethnic minorities, Table4-1, p.93, Table404, p.94, より作成
日本が、ブラジルと年金に関する二国間協定を締結した場合、ドイツにおけるユーゴスラヴィア(現セルビア・モンテネグロ)人、オランダにおけるモロッコ人と同様に、日系ブラジル人が大量に日本に訪れることも想定される。大量の外国人労働者の入国は、日本の社会・経済に大きな影響と混乱を与えかねない。二国間協定を締結する際には、入国する外国人労働者の数をコントロールできる措置を検討する必要があるだろう。
参考.国会議員(民主党衆議院議員藤村代議士)との議論
2005年11月30日16時より、本学公共経営研究科修士課程1年に在籍し、藤村修衆議院議員の政策秘書を務められておられる江口和美氏の紹介で、民主党藤村修衆議院議員と衆議院第2議員会館324号室にて面会し、同議員にヒアリング調査を行った。藤村修議員は、現在、衆議院懲罰委員会理事、政治倫理審査会委員を務められている[6]。同氏は1976年に日本ブラジル青年協会を設立し、現在日本ブラジル協会の理事長を務めており、古くから日系ブラジル人問題に関わってこられた国会議員の一人である。以下は、当日のやり取りを一問一答形式で示したものである。
Q:日系ブラジル人と接していて、彼らにどのような印象を抱くようになったか。
藤村氏:日系ブラジル人といっても、外見は日本人に似ているが、内面はブラジル人だ。ブラジル人と言えば陽気で明るい、のんびりしているというイメージが強いが、そういう意味で、日系ブラジル人はまさにブラジル人だといえる。だが、日系ブラジル人はそれだけではない。日系ブラジル人というのは、ブラジル国内において社会的に地位が高い。それは日本の文化や技術をブラジルに持ち込んだことと、教育熱心だったことによる。地球の裏側にある国と交流があるのも、彼らの存在があったからだ。彼ら(日系ブラジル人)は、日本人の血を引いているからだと思うが、非常に教育熱心だ。日本の文化も継承し、ブラジルにも溶け込んでいる。彼らこそ、多様な価値観を自分のものとして受け入れている、新しいコスモポリタン(地球市民)といえるのではないだろうか。
Q:1990年の入国管理法の改正で、なぜ日系ブラジル人に限って、事実上就労制限のない「定住資格」を与えることになったのか。
藤村氏:これは、知る人ぞ知ることなのだが、実は90年以前も、法運用で日系ブラジル人には定住を認めていた。当時は、中小企業を中心に人手不足が深刻だった。そうした時代背景に合わせて、1990年の法改正で(日系ブラジル人の定住を)明記しただけだ。
Q:では、日系ブラジル人は当時の日本の労働力不足が引き金となって、定住が認められたということか。
藤村氏:それ(当時の労働力不足)も当然あるが、それ以上に、1908年に日本政府が国策として多くの日本人をブラジルに移民として送り出したという事実がある。国策としてブラジルに送り出した同胞の日本人の子孫が、日本に来たいと言っている。それで受け入れないという訳にはいかない。日本の産業社会で労働力不足というのは確かにあったのだが、当時の国会議員の間では、そのような(国策としてブラジルに送り出した)背景があったのだからという訳で、日系ブラジル人には比較的寛容な姿勢を持つ人が多かったように思う。
Q:当時(1990年当時)の日本は確かに労働力不足ということもあったが、当時のブラジルにも労働者の送り出しの圧力が高かったのではないか。
藤村氏:当時のブラジル側の送り出し圧力は特に高かったということはなかった。でも、(当時のブラジルに)職不足というのはあったと思う。外貨獲得というのはブラジルにとって大きいかった。
Q:では、そのようにして日本にやって来ることとなった日系ブラジル人が、日本で働くことについては賛成か、反対か。
藤村氏:賛成だ。まず労働力として重要だ。その際、日本人の血が流れているため安全だろうという面も確かにある。(日系ブラジル人は)外見も日本人に似てるし、勤勉な人が多い。加えて、忘れられがちなのだが、距離的に非常に遠い国、地球の裏側にある国と人間の交流があることを忘れてはならない。(日本は)島国であるからこそ、こうした人間を通じた交流を行って、相互に刺激し合う関係を築くことはとても大切なことだと思う。
Q:でも、日系ブラジル人が日本で働くことのデメリットもあると思うが。
藤村氏:確かにある。犯罪などだ。教育も大変だ。彼ら(日系ブラジル人)の子供達が心配だ。今後、子供のアイデンティティが問題になると思う。
Q:日系ブラジル人の教育問題の根幹には、日本では外国人の子弟の教育は義務ではないことが挙げられる。外国人の子弟の教育も義務とすべきではないか。
藤村氏:それは、憲法に関わる問題だから難しい。今の段階では、義務とするよりも、彼らの民族学校のようなものを充実させることの方が現実的だ。アメラジアンというのをご存知か。沖縄の米軍兵士と日本人女性の間にできた子供をアメラジアンという。彼らはアメラジアン専用に民族学校のような形で学校を作っている。アイデンティティの問題もクリアできる。日系ブラジル人も民族学校のようなものを作って、それをサポートしていくのが良いのではないか。
Q:先ほどの日系ブラジル人が日本で働くことのデメリットは、どのようにしたら小さくすることができると思うか。
藤村氏:日本ブラジル協会では、日本人の青年をブラジルに送り出している。昔は国策で、移民として日本人をブラジルに送り出してきたが、今はそれがない。移民というチャンネルがなくなってしまった時、せっかくの交流が途絶えてしまう。そこで、ブラジルに関心のある日本の若者をブラジルに研修に送り出している。それこそ、言葉を学びに行く人もいれば、サッカーや音楽を学びに行く人もいる。そして、彼ら(日本ブラジル協会がブラジルに派遣した日本人青年)が、日本に帰ってきたら、日本とブラジルの交流に尽力してくれているケースが多い。今まで派遣した人数の合計は700人以上いるが、外務省や新聞社に就職した人もいる。今の朝日新聞のサンパウロ支局長も日本ブラジル協会が派遣した人だ。他にもボランティアとして日系ブラジル人のケアを行っている人もいる。このように、人を育てていくことが大切だろう。
Q:ドイツやフランスでは、外国人労働者の受け入れ人数、受け入れ期間を行政が管理しているが、日系ブラジル人に関しては、そのような管理が行われていない。このことが、少なからず社会に混乱を与えている面もあると思うが、経団連の提言のように外国人の受け入れ人数や受け入れ期間を一元的に管理する「外国人庁」の創設は考えていないのか。
藤村氏:時期尚早だ。(外国人庁の創設は)国民のコンセンサスを得てからだ。今はまだそんな段階にはない。現実的な方法は、FTAを締結する時、それ(FTA)の枠内で外国人労働者の数や期間を決めて、管理していくことだろう。
Q:国民のコンセンサスという話が出たが、女性や高齢者の労働力をもっと活用すれば、外国人労働者は必要ないと考えている人も多いが、この点どうお考えか。
藤村氏:日本はモノ作りの国だ。これからどんなに技術革新が進んでも、工場のラインが無人化したり、全く力や肉体的な負担がかからない工場ができるとはちょっと考えにくい。特に外国人労働者は大手メーカーの下請けの中小企業に雇用されていることが多い。そんな中小企業の工場のラインは、あと20年30年たっても、やはり立ちっぱなしで、重い工具を扱うといったように、ある程度は力仕事だろうし、(日本の工場で働く労働者に)肉体的な負担がかかることは変わらないだろう。そんな職場(工場)で、果たして女性や高齢者が働くということが正しいのか、適切なのか。女性や高齢者はもっと活躍すべき仕事があると思う。そして、肉体的な負担がかかる工場のラインなどは、やはり外国人に任せるというのが一つの考え方だと思う。
Q:だとすれば、今後外国人労働者に関わる課題として藤村先生は、何があるとお考えか。
藤村氏:もちろん法的な制度の見直しは課題としてある。その他には、やはり国民のメンタリティだろう。日本は日本だけでは成り立たなくなってきていることを、いかに国民一人一人が真剣に考えるようになるかだろう。あまり注目されていないが、移民を通じて地球の裏側と交流できるという意義も忘れてはならない。
以上が、当日行ったヒアリング調査の内容である。全ての国会議員が藤村議員のような考えを持っているとはいえないが、10年以上国会議員として選出され続けている議員の言葉には、ある種の重みがあることも確かだろう。藤村代議士は、来たるべき外国人労働者受け入れ時に向けて着々と準備を続けている、話を伺っていて、そのように感じられた。
参考文献・URL
日本労働研究機構「欧米諸国における外国人労働者等への社会保険の適用」1995 第1章
総合研究開発機構「外国人労働者の社会的需要システムに関する研究」1990 第1章
野川忍「外国人労働者法」信山社1993 第2章第3節
萩野芳夫「外国人と法」明石書店2000
高藤昭「外国人と社会保障法 : 生存権の国際的保障法理の構築に向けて」明石書店2001
犬塚先,星直樹「日本の制度改革 : その理念と新しいモデルの構想」
社会保障研究所「外国人労働者と社会保障」東京大学出版会1991
ドイツ連邦統計庁ホームページ URL: http://www.destatis.de
藤村修衆議院議員ホームページ URL:http://www.o-fujimura.com/