04/07/28 自治制度演習
45031025 増井 舞
公立文化施設へのPFI導入の可能性に関して
1.はじめに
公立文化施設と民間の文化施設との最も大きな違いは、前者が「地域住民のための公共空間」であるべきという点と考える。民間施設はあくまで市場の原理の中に存在するから、いくらチケット代を高額にしても、どんなソフトをかけようと、どんな運営をしようと、それが自分の趣味・嗜好にあう顧客がいる限り基本的には構わない。しかし公立文化施設の場合は、あくまでも公共のための空間である。住民が税金を拠出して建設・運営されている施設であるのだから、彼らのニーズに最大限応えるべきであるし、彼らが利用しやすいように運営されなければならない。またここでいう「住民」とは、文化に関心があり、文化施設に足しげく通う人々だけを指すのではなく、施設近隣に住んでいながら施設に訪れたことがない人、また訪れることのできない人も当然含めるものである。公立文化施設においては、地域に住む全住民を潜在的な顧客として考える必要がある。
また前クールでは、公立文化施設の現状から、その収益基盤の脆弱さを指摘した。文化芸術は本来安定した収益を確保することが難しい領域であることを考慮すると、独立採算で運営を行うところまで収益を引き上げることは不可能に近い。また、収益力のなさは、ひいては稼働率の低さとも関連している。施設が利用されれば管理費と共に利用収入が見込まれるが、利用されなければ管理費のみが支出される。従って、前述のように住民ニーズに即し、頻繁に利用される施設であることは、収益基盤の安定化にもつながる。住民にしてみても、自分達の税金が効果的に利用され、ソフトとして自らに跳ね返ってくるのが最も望ましいということになる。
しかし現状では、公立文化施設は住民サービスという意味ではほとんど機能していないと考えられる。例えば現在、自治体の芸術文化関係経費のうち約7割が施設建設費及び施設経費に用いられていて、肝心の芸術文化事業、すなわちソフトには1割しか割くことができない(図1)。本来公立文化施設が行うべき事業が実施できないのは、予算的な制約も大きいと想定できる。もちろん自治体が芸術文化予算を増加すれば問題は解決するが、近年の地方公共団体の財政難は芸術文化関係経費にも当然及んでおり、現状以上の予算増加は現実的には難しいと思われる(表1)。
従って、自治体は現在の文化関連経費の上でソフトである芸術文化経費により予算を割かなければならないという前提に立つと、それ以外の項目、すなわち施設建設費や施設経費を削る必要が生じるだろう。そのためのひとつの手段として、本演習ではPFI事業の導入可能性について検討したい。従来、自治体文化施設の運営は「普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの叉は公共団体若しくは公共的団体」(旧地方自治法第242条の2)が行うことしかできなかった。しかし地方自治法改正により、「法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(指定管理者)」(第242条の2)に運営を委託することが可能になった。PFIは、この地方自治法改正により文化施設に開かれた民間活力の導入手法のひとつとして捉えることができる。PFI導入により、民間企業等が安価で施設運営を行うようになったら、自治体は本来の業務であるソフト面からの「地域住民のための公共空間」づくりに集中できるのではないか。以下では、実際に文化施設にPFIが活用された事例を通じて、その可能性を検証したい。
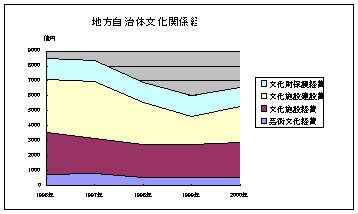
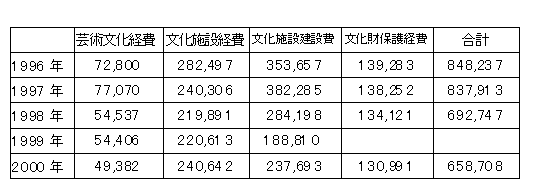
(図1 地方自治体文化関連経費(出典:平成14年度 文化庁地方文化行政状況調査報書))
(表1 地方自治体文化関連経費(単位:100万円)(出典:同上)
2.公立文化施設運営管理へのPFI導入について
PFIは本来、「低廉かつ良質な公共サービスの提供」が目的であり、冒頭に述べた「地域住民のための公共空間」づくりとは、一見したところ関連性が見られないようにも思われる。しかし前述のように、民間事業者による一般サービス(すなわち基本的な運営管理)が公共によるものよりも低コストで抑えられるのであれば、自治体による財源はその他のところ、つまり住民ニーズの汲み取りや自主事業の実施といった箇所に用いることが可能となるため、PFI事業の導入が公共文化施設の活性化につながるのではないかと考えることができる。
<県立神奈川近代美術館のケース>
平成13年から、神奈川県立美術館葉山館(新館)建築工事が行われているが、本件は新館の建築・維持管理・備品等整備業務及び旧館(本館及び別館)の維持管理業務、美術館支援業務をPFI手法により民間委託したものである。本来対象としていた公立文化ホールとは若干PFI導入の背景等は異なるが、同じ文化施設ということ、そして同美術館が「生涯学習時代にふさわしい機能を備えた美術館」を目標としているという点から、やはり地域住民のための施設を想定していることから参考にしたい。
事業範囲:
「事業者が新たに県立近代美術館葉山新館を建設・所有し、維持管理業務・美術館支援業務・備品等整備業務を遂行し、また、既存の鎌倉館についても維持管理業務を遂行すること」。「なお、展覧会の企画・開催、美術作品の収集・保管等の公立美術館としての運営業務は、従来通り県が行う」
維持管理業務の具体的範囲:
・ 建築物保守管理業務
・ 建築設備保存管理業務
・ 外溝施設保守管理業務
・ 清掃業務
・ 植栽維持管理業務
・ 警備業務
・ 入館者受付・展示作品監視業務
・ 環境管理業務
美術館支援業務の範囲:
・ 喫茶・レストラン運営業務
・ ミュージアムショップ運営業務
・ 駐車場管理運営業務
・ 美術情報システム整備及び運用支援業務
(喫茶・レストラン、ショップ、駐車場は事業者が当該収益により運営する独立採算)
本事業で県が民間事業者に委託したのは、基本的な運営業務のみであり、企画等ソフト面まではコミットさせていない。「美術館支援業務」として付帯施設(レストラン等)の運営を委託したのは、民間のノウハウが活かされる部分であると考えたからとされる。しかし独立採算でありながら撤退は認めないとしたために、民間事業者側は、期待した収益が確保されなかった場合の保証が不安要素になっていたようだ。また、美術館の来館者(すなわち付帯施設の潜在的顧客)の客層や予想される人数が不確定な点も、民間事業者にとってはリスクであると思われたらしい。しかしながら付帯施設の母体となる美術館事業そのものが必ずしも安定した来館者を見込むことができるものではないということを考えると、民間事業者もそのようなリスクを背負った上で入札に参加すべきであると思われる。その点、美術館にどの程度の来館者が来るのか、どのような客層なのかを理解しやすく、当初から付帯施設の黒字経営を必須のものとしない非営利団体や市民団体の方が委託先として望ましいようにも考えられる。
本事業では入札した民間事業者が実施した場合の公共負担額は、県が直接事業を実施する場合の負担額に比べ2710百万円減額される(独立採算部門の収支を除いた場合)。ただし、減額された金額がそのままソフト費用(この場合企画費等)に支出されるであれば、文化施設の全般的なサービスの質が向上すると思われるが、運営を民間に任せたことにより県が美術館にかける費用そのものが減額された場合、結局運営の効率化のみがはかられ、本来の目的である「生涯学習時代にふさわしい」ソフト内容がおろそかになってしまう危険性もある。
<いわき市文化交流施設整備のケース>
福島県いわき市では、平成6年2月に「いわき21世紀プラザ」「いわき市民文化ホール」(ともに仮称)等を整備しようとする『文化コア構想』を策定していた。その後市民ニーズの把握等と共に、本計画は平成13年に策定された「新・市総合計画基本構想」の中における文化交流基盤の要施設として再構築された。その際、旧来の市民会館の改修、文化センターの調査・設計、文化交流施設(本施設)の調査・設計・建築・維持管理・テナント運営等一部事業をPFI事業によって行った。
事業範囲:
「いわき市文化交流施設(以下「本施設」という)の設計、建設」「本施設に近接する既存のいわき市音楽館(以下「音楽館」という)、平中央公園、いわき市文化センター(以下「文化センター」という)、平市民会館に係わる改修設計及び工事管理業務、並びに音楽館の維持管理を併せて実施」
|
|
調査 |
設計・管理 |
建設 |
改修 |
維持管理 |
事業運営 |
テナント運営 |
|
本施設 |
PFI |
PFI |
PFI |
別途発注 |
PFI |
市 |
PFI |
|
音楽館 |
PFI |
PFI |
|
別途発注 |
|
|
|
|
平中央公園 |
|
PFI |
|
別途発注 |
市 |
|
|
|
文化センター |
PFI |
PFI |
|
別途発注 |
市 |
|
|
|
市民会館改修 |
PFI |
PFI |
|
PFI |
|
|
|
(テナント運営業務は独立採算)
設計・建築といった業務の契約関係に関しては、他の公立施設とほとんど変わりはない。しかし、いくつもの施設のいくつもの業務が含まれているために、事業者側にもどこまでが事業範囲なのか混乱があったようだ(例えば市民会館の改修はPFI事業なのに、その他の施設の改修事業は市が別途発注する形になっている等。ちなみにこの分離の理由は、「厳しい地域経済状況を踏まえ、地元企業の受注機会に配慮」したためとされる)。また、文化施設特有の事業を見ると、事業者にとっては厳しい条件であることがわかる。例えば市民会館の利用実績は公表されているものの、本施設において市の予想する年間入場者数及び稼働率が不明確なままである、独立採算となっているテナント部分にはモニタリングが入り、一定期間空きテナントになっていると使用料相当額をペナルティとして課すことが規定されている等の事項は、事業者にはいささか酷な内容とも思われる。
本事業についてはまだ契約が締結されていないため、最終的にどのくらいのVFMが算定されたかは不明である(事業者の決定は今年8月、仮契約の締結は同年10月の予定)。
神奈川県立美術館の事例と比較すると、事業範囲が建設段階まで(あるいはそれ以前)と非常に狭く設定されている。確かに施設建設費は莫大な予算がかかるため、PFIによるコストカットは効率的であると考えられる。しかし真にコストがかかるのは開館後の維持管理運営段階であり、なぜその部分でPFI事業を導入しなかったのか疑問も残る。
3. 結論
文化施設に対する PFI導入におけるメリットは、やはり施設建設費・維持管理費の大幅な削減であると考えられる。しかし一方で、実際に施設に来館する地域住民の動向やニーズに左右される事業—具体的には運営や付帯施設事業等—を行うにおいては、ハードルが高いとも思われる。施設計画自体は自治体側が行っているため、文化施設への来館者数は民間事業者側にとっては極めて予想し難いものであり、それ故に来館者の動向と大きく関わる事業を行うのは民間事業者にはリスクが高く、かつ民間事業者が行う事業が住民ニーズに即したものになる可能性も不明であるからだ。従って、PFI導入により確実に意義があると言えるのは、利用する住民には直接コミットしない事業、すなわち施設建設や施設の維持管理であると考えられる。それ以外の事業、例えば運営や付帯施設運営に関しては、地域住民により近く、営利を第一義目的としない市民団体やNPOによる事業実施の方が成功する可能性は高いのではないか。
また、PFI導入が実際に自治体の芸術文化事業経費の増加につながるか否かについて確証は持てない。今回検証した2つの事例についても、その後の自治体文化経費がどのように利用されたのかはまだわかっていない。冒頭で指摘したように、削減された予算を、自治体が芸術文化関連経費へ回していくことによりはじめて、PFI導入の本来の意義が見出せる。自治体がPFI導入をどのように捉えているかについては、今後も検証を重ねて調べていく必要がある。
参考HP
PFIインフォメーション http://www.pfinet.jp/(2004年7月23日参照)
神奈川県立美術館 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/zaisan/pfi.kinbi.htm
(2004年7月23日参照)