はじめに
日本全国における劇場・ホール機能のある公立芸術文化施設(以下、劇場・ホール)は、1998年現在で2481館ある。指定都市(人口50万人以上)から中核都市(人口30万人以上)であれば1都市に約3〜4施設、特例市(人口20万人以上)以下の小規模都市であっても2都市に1つは文化施設があるという計算になる。一方、内閣府の「地域の文化活動の振興に関する要望」(平成13年度)によれば、国民が国や地方公共団体に第一に求めているのは「文化施設の整備・充実」であるという[i]。この調査における「充実」が、施設建設に対する要望なのか、あるいはソフト(演目、運営等)に対する要望なのかは定かではないが、少なくとも約3000の施設が有効に活用されていないか、もしくは住民ニーズと相反する運営が行われていることがわかる。あるいは、3000近い施設があってもまだ住民には不足と捉えられている可能性もある。この場合、新たな施設を建設することが必要とされると思われるが、その際にも住民ニーズに適応し、更にできるだけ財政負担が少なくなるような施設運営を行うことは不可欠であると考えられる。
本演習では、公立劇場・ホールの機能という観点に着目し、施設の現状と照らし合わせた上で、公立文化施設の持つ問題点を概観する。
第1章 公立芸術文化施設の現状
|
|
施設数 |
ホール数 |
|
都道府県 |
147 |
157 |
|
政令市 |
137 |
225 |
|
市町村 |
2197 |
2659 |
|
合計 |
2481 |
3041 |
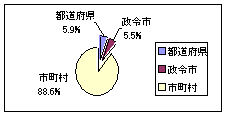
財団法人地域創造による『「地域文化施設に関する調査」分析報告書』によると、劇場・ホール機能を持つ公立文化施設は2481、ホール数は3041館とされる((財)地域創造、1998)。これらの施設の設置主体を団体別に見ると、都道府県147(6%)、政令市137(5.5%)、市区町村2197(88.5%)となっている(表1)。更に人口規模別に施設数を見ると、市区町村数に比例して施設数も多くなっている、すなわち人口規模に関わらず、どの都市にも一律に施設が存在していることがわかる(図1)。
(表1 設置主体別施設数・ホール数 (図1 地域別設置主体割合
(財)地域創造、1998より) (財)地域創造、1998より)
|
|
施設数 |
ホール数 |
市区町村数 |
|
50万人以上 |
57 |
72 |
11 |
|
40万人以上 |
60 |
80 |
20 |
|
30万人以上 |
98 |
130 |
33 |
|
20万人以上 |
99 |
142 |
49 |
|
10万人以上 |
229 |
305 |
126 |
|
5万人以上 |
276 |
381 |
230 |
|
1万人以上 |
851 |
988 |
1246 |
|
1万人未満 |
520 |
548 |
1528 |
|
合計 |
2190 |
2646 |
3243 |
(表2 人口規模別施設数 (財)地域創造、1998より)
また設置者を性格別に見ると、直営の施設、すなわち都道府県知事部局、同教育委員会、市町村長部局、同教育委員会などの公的機関が運営を行っている施設は70.8%、財団法人、第3セクターなどに委託して運営している施設が29.2%という結果が出ている。この委託先は従来、管理受託者制度の規制の下、ほとんどが自治体の外郭団体であった(枝川、2001)。しかし2000年度の地方自治法改正により、委託団体の幅が広がり、法令で管理主体が限定されているものを除き、民間事業者に委託することも可能となったため、今後は民間の非営利団体(NPO)等が運営に参入する施設が出現することも考えられる。
施設がどのように使われているかを、その目的別に調べると、多目的施設が97.0%、専用劇場・ホールが3.0%となっている。このうち専用劇場・ホールを芸術ジャンル別に分類すると、音楽専用76.1%、演劇・舞踊専用15.9%、オペラ専用1.1%、能専用6.8%となっている。ほとんどの劇場・ホールが多目的であるのは、施設設置者が施設の個性化よりもオールマイティさを追求した結果であると推測できるが、またこれは、そもそも現在の公立劇場・ホールの発祥は公民館であり、その時点である特定の芸術ジャンルのために作られたものではなかったためであるとの議論もある(清水、1999)。
また、劇場・ホールの事業を機能別に見ると、大きく分けて自主事業と貸し館事業に分けることができる。立木の定義によると、自主事業とは「館自体が企画し実施する事業」であり、その目的は、「優れた芸術の上演や講演会、展示会や研修会などを開き、その人や作品に触れる機会を地域住民に提供すること」「さらにこの事業を通じて地域の文化を創造し蓄積し、さらに積極的にその成果を地域に発信する事業」である(立木、1999、p.292)。この場合のポイントとなるものは「地域」であり、すなわち、自主事業には「地域の独自性・主体性・自律性を重視した情報発信」が期待されている(高木他、2001、p.15)[ii]。従って「地域における住民の文化活動拠点」として公立劇場・ホールを見た場合、この自主事業が公立劇場・ホールの果たすべき中心的機能であるとする意見も多い(枝川、2001、伊藤他、2001等)。一方貸し館事業とは、「市民や市民文化団体および芸術団体や興業団体の文化芸術活動に館のスペースと時間を貸す事業」であり、その目的は主に、地域住民に対し「中央の優れた舞台芸術の鑑賞機会を充実」させることとされる(立木、1999、p.293)。従来、日本の公立劇場・ホールの普遍的事業形態はこの貸し館事業であるとされてきた。現在でも全体で見ると、自主事業型、特に年に10本以上自主事業を行っている施設は36.4%、貸し館運営のみを行っている施設が63.6%とされる。貸し館事業の意義は前述した通りであるが、この種の事業形態が多い要因の1つとして、劇場・ホールのマネジメントを専門に行う職員の不足が挙げられている。つまり、「住民の文化的刺激への強い要請が生まれ、いいものを見たい、聞きたいといった期待は高まってくる」が、「公立文化施設には舞台芸術に熟知する専門家はおらず、外部の芸術組織やプロモーターに作品制作を依存する」貸し館事業が普及する、という流れである(衛・本杉編、2000、p.23)。
また運営状況に関しては、高木他の調査によれば、公立劇場・ホールの平均予算構造は、以下のようになっている。
年間支出:全体平均2億1千万円(単位 上段は金額(百万円)、下段は%)
|
支出 |
人件費 |
委託費 |
需要費 |
自主事業費 |
その他 |
年間支出総計 |
|
自主事業あり |
58.7 |
56.4 |
53.4 |
42.3 |
17.7 |
228.5 |
|
|
25.7% |
24.7% |
23.4% |
18.5% |
7.7% |
100.0% |
|
自主事業なし |
44.8 |
37.3 |
42.4 |
0.3 |
11.3 |
136.1 |
|
|
32.9% |
27.4% |
31.2% |
0.2% |
8.3% |
100.0% |
|
全体 |
56 |
52.7 |
51.3 |
34.1 |
16.4 |
210.5 |
|
|
26.6% |
25.0% |
24.4% |
16.2% |
7.8% |
100.0% |
年間収入:全体平均2億1千万円(単位 上段は金額(百万円)、下段は%)
|
収入 |
事業受託収入 |
使用料収入 |
自主事業収入 |
その他 |
年間収入総計 |
|
自主事業あり |
166.3 |
27.6 |
26 |
8.6 |
228.5 |
|
|
72.8% |
12.1% |
11.4% |
3.7% |
100.0% |
|
自主事業なし |
103.8 |
23.1 |
0.3 |
9 |
136.2 |
|
|
76.3% |
16.9% |
0.2% |
6.6% |
100.0% |
|
全体 |
154.1 |
26.7 |
21 |
8.7 |
210.5 |
|
|
73.2% |
12.7% |
10.0% |
4.1% |
100.0% |
(表3 年間支出・年間収入 高木他、2001より)
年間収入のうち、事業受託収入とは「母体からの補助」、すなわち自治体からの補助金を
指し、純粋な施設収入と言えるのは、「使用料収入」であるという。個々の施設で見た場合、複数ホールを持つ施設、客席規模の大きな施設、人口規模の大きな地域にある施設程、年間支出及び使用料収入が多いことが調査から示されている。ここから、人口規模の多い都市部の施設は予算のかかる事業を行い、支出が増加しても、使用料収入により補填することが可能と推測できる。また、赤字補填率は平均77.1%である。更に、稼働率については、以下のような結果が報告されている(表4)。
|
|
ホール数 |
割合 |
|
30%未満 |
547 |
20.18% |
|
50%未満 |
692 |
25.54% |
|
70%未満 |
732 |
27.01% |
|
90%未満 |
540 |
19.93% |
|
90%以上 |
199 |
7.34% |
|
合計 |
2710 |
100.00% |
(表4 稼働率別ホール数・割合 (財)地域創造、1998より)
一方、機能別に見ると、自主事業型の施設は、貸し館型の施設と比較して、年間支出及び赤字補填率が高い。自主事業はコストはかかるが収入には結びつきにくいという点がわかる。
第2章 公立芸術文化施設の意義をめぐる議論
公立劇場・ホールの役割については、大きく分けて2点が挙げられる。1つは、地域における住民の文化活動参加拠点としての役割であり、もう1つは、プロフェッショナルの芸術家の活動の鑑賞の場としての役割である。前述した公立劇場・ホールの機能に照らし合わせてみると、前者が自主事業、後者が貸し館事業に相当する。
従来の文化庁による文化政策は、プロによるメジャーな芸術文化を主流とし、それを全国に普及させることで、全体的な国民の文化レベルを高めようとするところがあった(中川によれば「エクセレンス(優良)主義」)(中川、2001、p.17)。前述したように、そもそも公立文化施設には、企画を行うことのできる専門職員が不足していたという構造的要因もあったが、それ以上にこの視点から、多くの館での「中央のプロの舞台芸術公演を鑑賞する」という機能を持つ貸し館運営の実施に正統性が与えられてきたと考えられる。しかし、前章で軽く触れたように、公立文化施設を地域アイデンティティの形成や、市民文化の活性化のインフラストラクチャーとして見た場合、住民の創造活動参加、あるいはサポートを前提とした自主事業型施設の構築がより望ましいとされる。
とはいえ、自主事業型施設は、貸し館型施設に比べ、採算面で非常に厳しい現状にあるということも既に述べた。前章の表3から、自主事業を行う館は貸し館型よりも支出が多いことがわかっている。加えて自主事業は、地域住民全般を主体として想定されるという側面から、特定の観客層が固定化されているアーティストや劇団等の公演を行う貸し館事業に比べ、公共性が高い。従って、より低廉な料金設定をすることが望ましい。ということは、使用料収入による館の運営は、貸し館運営に比べても、非常に難しいということになる。
一方、貸し館事業の場合、高額な料金設定をしてもある程度の集客が見込まれる事業を行えば、使用料による一定収入が確保できる上、施設職員は事業企画等で頭を悩ませる必要もない。特に大都市であれば、また大都市でなくても周辺地域に競合他者がいない専門的ホールであれば、演目次第である程度の集客は可能となる。安定した収入を確保し、稼働率を上げることを目的とするならば、貸し館型運営はベストな選択肢となり得る。ただしこの場合、ホールの客席数に適し、近隣の施設と演目が重ならない、一定のオリジナリティを持った演目を選択することが必要となると考えられる[iii]。大規模施設であっても、客席数に満たないわずかな集客しか見込めないものであれば、料金収入も期待水準には達することはないためであり、そのような観客ニーズを見込んだ演目選択については、営利を第一目的とする民間劇場・ホールに見習うべきところがあると思われる。
しかし、このような貸し館運営型施設は、民間の劇場・ホールと事業の中身が変わらなくなり、「公立」である必要性がなくなってしまう可能性が非常に高い[iv]。演目以外の点で、民間劇場・ホールといかに違いを持たせるかが問題となる。これに関しては、例えば、施設の管理維持や技術支援等の面でホールボランティアとして市民を運営に参加させていくとか、個別ホールに限らないで文化施設そのものを「人々が集まる場」「人々がくつろぎ、楽しむことができる」場、すなわち市民の交流スペースとする(衛・本杉編、2000、p.204)といった仕組みが考えられる。
また表2で見たように、ほとんどの施設は人口規模1万人前後の小規模都市に集中しており、更に専門性を有した施設も少ない。ここから、以上のような一定の観客動員力を備えた公立劇場・ホールは、大都市にある極一部の施設等に限られると思われる。また、コミュニティ施設としての文化施設の機能を生かす、あるいは、地域振興の要の場として文化施設を利用するならば、近隣住民とのつながりが大都市圏よりも高い、中規模・小規模都市の劇場・ホールは、自主事業型運営を行った方が望ましいということも言える。従って、厳しい採算状況という問題点を除けば、中規模・小規模都市にある劇場・ホールは、自主事業型を選択するべき、あるいは従来よりも自主事業の割合を増やすべきであると考えられる。
次に、自主事業の中身について見ていきたい。貸し館事業は、特に文化芸術に関心があり、高額の料金を払っても施設に足を運ぶと思われる一定の住民のみを対象としているものと想定できるが、これは自主事業にしても同じであるとも言える。自主事業の多くは、市民の文化活動を取り入れた市民参加型のものである(例えば兵庫県尼崎市の青少年創造劇場による県立劇団、沖縄県佐敷町シュガーホールによる市民コンサート等。丹羽・小暮、1992、佐藤、1995、衛・本杉編、2000等)。しかし大抵の場合、「対象はもともとこうしたこと(筆者註:舞台芸術や音楽等を指す)に興味のある市民に限られている」ということが言える(衛・本杉編、2000、p.47)。従って、市民オペラや市民コンサートが結果的に参加者の自己満足に終わってしまい、自主事業の本来の目的の1つである「地域アイデンティティの形成」にまで到達しない可能性も十分にあると言えるだろう。
こうした問題点を解決する1つの方法として、アメリカの公共ホール(正確にはNPOホール)のアウトリーチ活動が挙げられる(衛・本杉編、2000、p.30-47)。アウトリーチ活動とは、学校、福祉施設等劇場・ホールの外において、アーティスト及び職員が、芸術鑑賞プログラムや、芸術を媒介としたディスカッションやレクチャー等を行う教育プログラムを実施するものである。つまりその対象は、「まだホンモノの音楽や演劇を知らない子供たち、一度も劇場に足を運んだことのない市民、芸術とはまったく無縁の生活をする人々、あるいは、障害があったり、病院や老人ホームで生活するためにそもそも劇場に出かけることのできない市民までも」含まれる(同上、2000、p.47)。市民参加のイベント的事業と比較すると、アウトリーチ活動は、「ホールが地域に出ていく」という点、そして「将来の観客育成」という点から、地域における公共文化施設の存在意義が大きいのではないかと考えられる。
またもちろん貸し館事業の箇所で触れたのと同様に、ホールボランティアのように、施設の管理・運営に積極的に市民が参加していける体制を整えていくことも必要だと思われる。これは、施設が地域に溶け込むというだけでなく、コスト削減という観点からも意義のある施策となるのではないか。また、施設空間を地域住民の憩いの場とするという仕組みについては、貸し館運営に比べ市民と施設との距離感が縮みやすい自主事業型の施設の方が行いやすいのではとも思われる。
第3章 結論
以上から考えると、一定の集客数が見込まれる大都市圏の公立劇場・ホール、あるいは周辺に競合他者がいない専門機能を持った劇場・ホールは、貸し館運営によっても十分に収益を得ることが可能であると思われる。しかしそうでない地域にある他目的な施設であれば、地域におけるアイデンティティ形成の拠点、そして市民文化活動の拠点としての機能を果たすために自主事業型の運営を行うべきであると考える。ただし、前者の場合は、機能面で民間施設と競合する可能性が高いため、いかに公立施設としての特色を出すかという点に留意する必要があり、後者の場合は、特定の住民だけでなく、いかにして地域全体を巻き込んだ事業を行っていくか、そして収益をどのように確保するかという問題がある。今後はこの3点について、更に考察を進めていく必要がある。
参考文献
伊藤裕夫、中川幾郎、片山泰輔、山崎稔恵、小林真理『アーツマネジメント概論』水曜社、2001
衛紀生、本杉省三編『地域に生きる劇場』芸団協出版部、2000
枝川昭敬「全国的に見た文化施設と活動に関する調査研究」『文化経済学』2(3)(通号10)、
2001、3
財団法人地域創造『「地域文化施設に関する調査」分析報告書』1998
佐藤一子「地域文化の創造と公立文化ホール」『社会教育』39(2)、1995、2
清水裕之『21世紀の地域劇場』鹿島出版会、1999
清水裕之「日本における公立文化施設の現状と課題」『文化経済学』3(3)(通号14)、2003、3
瀬沼克彰『住民参加の文化開発』学文社、S63
高木俊行、守屋秀夫、清水裕之、小野田泰明
「公立文化施設における運営経理の現状と課題」『文化経済学2(3)(通号10)、2001、3
立木定彦『現代の公共ホールと劇場』蒼人社、1999
中川幾郎『分権化時代の自治体文化政策』勁草書房、2001
丹羽弘行、小暮宣夫『地域がつくる文化新時代』ぎょうせい、1992