�����琭�ߎw��s�s�ւ̌����ڏ��ɂ���
�ؑ��F�I
�͂��߂�
�@���ߎw��s�s�i�ȉ����ߎs�Ɨ����j�́A���{���ɋ߂����x���̌������������ʎs�^���̌o�܂����������Ƃ��炵�����̊W���c�_����Ă����B
�@���݁A�����̑升���ɂ�萭�ߎs�̎w��v�����ɘa���ꂽ���ƂŐ��ߎs�̐��������Ă������A��28���n�����x������ł́A���B���̋c�_���Ȃ���Ă���B���܍ĂсA�L��s���Ɛ��ߎs�Ƃ����s�s�̎����͈̔͂��ǂ����Ă����̂��c�_���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����Ƃ�����b�I�����̂̕ω��Ɠ��B���Ƃ��������x�̕ω��Ƃ����n���������x�̕ϊv���ɂ����āA�e���{���Ō����ڏ��v��̌����ψ���ݗ�����������̖͍����s���Ă���B
���ɁA�����ɓ�̐��ߎs������A�l���̔����ȏオ���ߎs�̏Z���ł���_�ސ쌧�A�������A�����č���̍�������ň�x�ɂQ�̐��ߎs���a������É����ł́A���Ƃ��ĉ��̋Ɩ������Ă���̂�����Ă���B
���N�[���ł͓��ɁA���̂R���𒆐S�Ɍ����琭�ߎs�ւ̌����ڏ��ɂ��Č������A���Ɛ��ߎs�Ƃ̊W���l����B���͂ł͂܂��A�n�������ꊇ�@�ɂ���Č�����̌����ڏ��ɂǂ̂悤�ȕω��������炵�����ɂ����������A��������������ɂ�錠���ڏ��̊T�v���q�ׁA���͂ł́A�_�ސ쌧�E�É����ł̌����ڏ������S�ɁA��̓I�Ȍ����ڏ����ڂƐl���𗬂̊ϓ_���琭�ߎs�ւ̌����ڏ��ɂ��ďq�ׂ�B
���� �������b�I�����̂ւ̌����ڏ�
��1�߁@����I�����ϔC���狦�c�ɂ�鎖������������̑n�݂�
2000�N�n�������ꊇ�@�̎{�s�ŋ@�ֈϔC�������p�~����A�@���������ƂȂ������ƂŁA���ƒn���̏㉺�W�͂Ȃ��Ȃ�Γ��Ȃ��̂ƂȂ����B�����ɁA���{���Ǝs�����̏㉺�W����������A���{������s�����ւ̌����ڏ���Ǝ��ɏ��ɂ��s�����Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ����i�n�������@��252����17��2�j�B���̌��ʁA�s���{������s�����̌����ڏ��́A�s���{���m������s�����ւ̎����ϔC�Ƃ����`�Ō����Ϗ����s���Ă����̂��A�ȉ��̂悤�ɐ������ω������i�}1-1.�j
�}1-1.�@�����Ϗ����猠���ڏ���
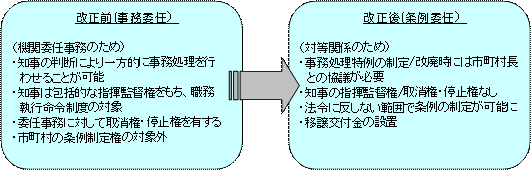
��}�̕ω��ɂ݂�悤�ɁA�n�������@�����O�́A�s���{������s�����ւ̌����͏ォ��́u�Ϗ��v�ł����āA�s�����͗^����ꂽ���������Ȃ����ƂɏI�n���Ă������A������s�����͈ϔC���ꂽ�����ɑ��ď�ᐧ�茠���������̍ٗʌ����t�^���ꂽ�B�܂��A����16�N5���̖@�����Ŏs�����́A���ɑ��Č����ڏ���v���ł���悤�ɂȂ����B
��2��
�����ڏ��̎�g
�O�q�̖@�������Ċe���́A��b�I�����̂ւ̌����ڏ��ɂ��Č�����𗧂��グ���Ɗ�b�I�����̖̂������S�ɂ��Č������s��ꂽ�B�S���m����́A����13 �N7 ���Ɂu�n���������̓s���{���̖����v�j�ɂ����āA�s���{�����s���ׂ������ł��邩�ǂ����f����g�U�̃����N�}�[���h����Ă���B����́A�ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł���B
�y�S���m������������̃����N�}�[���z
�@�Y��(���i�E�T�[�r�X�̐��Y�E����)�ɌW����̂ł��邩�ǂ���
�A�@�l���ɌW����̂ł��邩�ǂ���
�B�s���Ώۂ��L��I�Ɉ�̂̂��̂ł��邩�ǂ���
�C�s�����v�E�s���Ώۂ��L��I�ɎU�݂��Ă�����̂ł��邩�ǂ���
�D�������x�̐�含��K�v�Ƃ�����̂ł��邩�ǂ���
�E�s����������c�̂Ƃ������i�ɂ�������̂ł��邩�ǂ���
�s�����ւ̌����ڏ��ɂ������Č��́A����ɗގ��������Ȃ̖�����O���ɂȂ���Ă���B�������A���̎�@���݂�Ɩ��m�Ȋ��v�搫�͂��܂�Ȃ��A�����̓��{���͌����ڏ�����s�����̏�l�I�����̏Ƃ��������̂����Ă��A���̓s�x�ɉ����Ĉڏ����Ă���ɉ߂��Ȃ��Ƃ�����ۂ���B�@���I�Ȍ����ڏ����\�ł������ŁA���������̑S�̓I�������₱�ꂩ��̌��Ǝs�����̂�����Ƃ������헪�E�v�搫�̂Ȃ������ڏ��ɂȂ��Ă���Ƃ����_�͔ے�ł��Ȃ��B
���������A�_�ސ쌧�������̎s�����ƍ����Ō����ڏ��̂�������������邽�߂ɗ����グ�����E�s�����ԍs�����V�X�e�����v���i���c��́A����15 �N3 �������o��������������̃A���P�[�g�����́A���̂悤�Ȃ��̂ł������B
�܂��u�s�����ւ̈ڏ������̑I��ɂ�����l�����v�Ƃ��������ɑ��Ĕ����̒c�̂��u�s�����̋K�͂�@�茠�����̊֘A���A�����܂ł��X�̎s�����̈ڏ���]���d�����đI��v�Ɖ����B�܂��A�u�������e�̑I��ɂ��āv�Ƃ��������Ɋւ��Ă͂W���̒c�̂��u���̒S�����ǂƎs�����̍��ӂ��������X�̎����̒P�ʂőI�肵�Ă���v�Ɖ����B
�܂�A�����̌��ɂ����Č����ڏ��̎�@�ɖ��m�ȋK���͂Ȃ��s�������ƌ������u���܂��܁v���ӂ������Ƃɂ���Č��肳��A���m�Ȏ�@�̑I���͍s���Ă��Ȃ��B����ɑ��ĐϋɓI�Ȍ����ڏ���@�̍�����s���Ă��錧������B�ȉ��ɂ��̎�����q�ׂ�B
�y����P�F��錧�z
�@��錧�ł͐l��10���l�ȏ�̎s���u�܂��Â������s�v�Ƃ��Ĉʒu�Â��A����ɂ܂Ƃ܂������������낷�Ƃ����p�b�P�[�W���̌����ڏ����s���Ă���B�܂��A�����ɍ����̐��i��Ƃ��āA���������ꍇ��5���l�Ɏw��v�����ɘa����Ƃ������̐���ɗގ�����悤�Ȍ����ڏ�������s���Ă���B���̎w�����ƁA�n��ɖ��������܂��Â���̂��߂̎��Ƃ��܂Ƃ܂��Ĉڏ������d�g�݂ɂȂ��Ă���B
�y����Q�F�L�����z
��̃p�b�P�[�W��p�ӂ��āA�s�����ւ̌����ڏ����e���p�b�P�[�W�����Ă���B
�@�u�X�e�b�v�A�b�v�����v�F���j�s�ɂ͐��ߎs�̌������ڏ��A����s�ɂ͒��j�s�̌������ڏ��A�Ƃ����悤�ɂP�i�K��̌������ڏ�����p�b�P�[�W�B
�A�u���蕪��g�[�����v�F�����E�ی��q���E�܂��Â���̂R�̃p�^���ɕ�����A�������p�b�P�[�W�ňڏ�����B
�����̃P�[�X�̂悤�ȃp�b�P�[�W�ł̌����ڏ��������Ă��錧�͏��Ȃ����A������Ӗ��Ō����ڏ��̓p�b�P�[�W������邱�ƂɂȂ�B�܂茠���ڏ��̍ۂɃq�g�E�J�l���K�v�ɂȂ邽�߁A�����������ڏ�����̂ł͂Ȃ������Ƀq�g�ƃJ�l���Z�b�g�ɂ��Č������ڏ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
��������������ɂ�錠���ڏ�������ɂ������ēs���{���́A�n�������@��28���ɂ������[�u�i�����ڏ���t���j���u���邱�Ƃ��`���t�����Ă���B
�܂��A�������ڏ�����ۂɂ��̎������������Ă����S���҂�h�����������~���Ɉڏ����邱�Ƃ��ł���悤�ɂ���A��劯�̂��Ȃ������̂ւ̌����ڏ����s���ۂɂ͐��m�������E����h������A�Ƃ������K�v������B
���� �����琭�ߎw��s�s�ւ̌����ڏ�
�@���̏͂ł́A�O�͂̌����ڏ����@�̊T�v�܂��āA�����ōő�K�͂̊�b�I�����̂ł��鐭�ߎs�ւ̌����ڏ����ǂ̂悤�ɂȂ��Ă��邩��Nj�����B�Ȃ��ł��A�����ɂQ�̐��ߎs�������_�ސ쌧�E�É����E�������𒆐S�ɁA���̎����̂ւ̌����ڏ��Ɛ��ߎs�ւ̌����ڏ��ɈႢ�����邱�Ƃ��q�ׂ�B
��1�߁@������ɂ݂�e���ߎs�ւ̌����ڏ�
�@�e�������ߎs�ɑ��Ăǂ̒��x�����ڏ����s���Ă���̂��݂邽�߁A������������������ɖ@�����ƂɈڏ��̒��x�ׂ��̂��ȉ��̕\�ł���B�i�e���ɂ���ē��e�̈قȂ���ł́A��r������Ɣ��f�������ߑΏۂ���͏������j
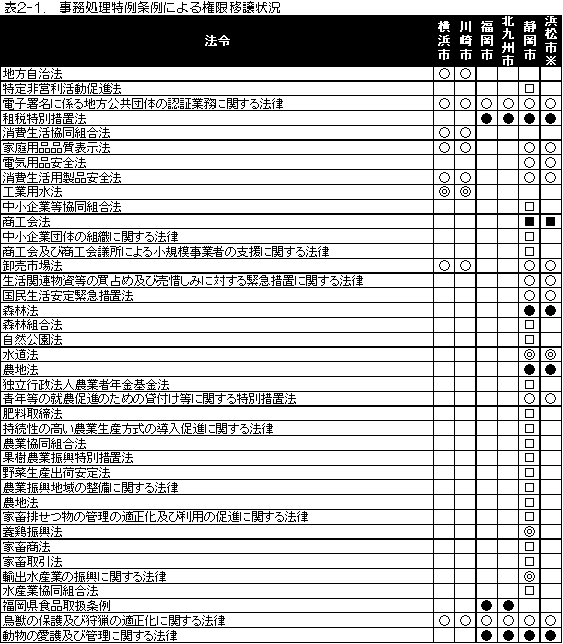
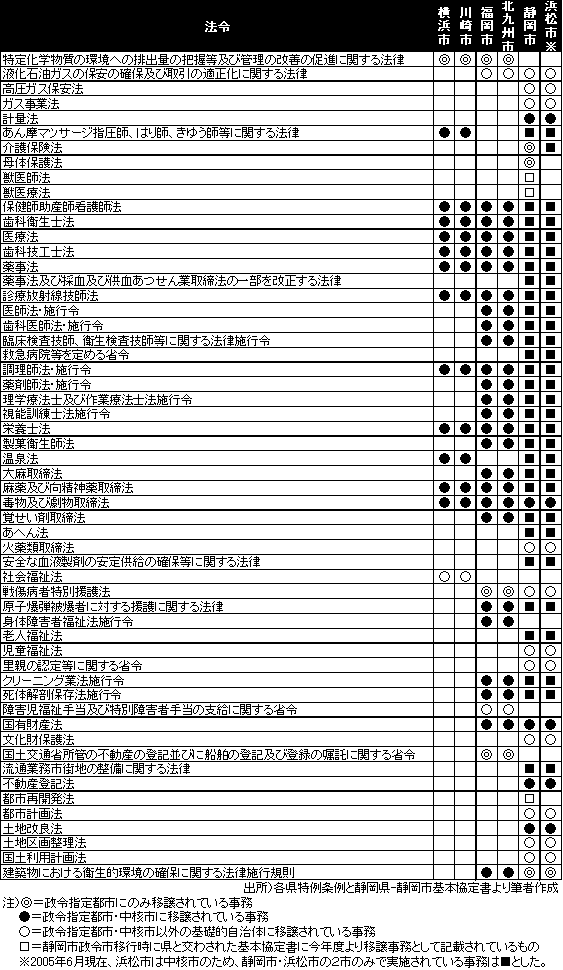
�@���̕\����A�ȉ��̂��Ƃ��l������B
�E �܂��A�É������ϋɓI�Ȍ����ڏ����s���Ă��邱�ƁB�É����ł́A���B�����ł̌������ӎ������ߎs�ɑ��Ă��ϋɓI�Ȍ����ڏ����s���Ă���B�O�q�̑S���m����U�̃����N�}�[���ɑ�\�����悤�ɁA���{���́A�L��s���ɂ������Ă���n��Y�ƐU���Ƃ����������͌��ŒS���ׂ��ƍl����X�����������A�É����ł́A����ɂ�����@������Ɋւ��Ă��ϋɓI�Ɉڏ����Ă��邱�Ƃ��킩��B���ɁA���̌��ł͋ɂȂ��Ă���@���Ō����Ɍ���Ă���B
�E �܂��g���ߎs�݂̂̎����h�����Ȃ����Ƃ��킩��B���j�s���x���ł��ڏ�����遜���������߁A���ߎs�݂̂́��͏��Ȃ��B�v���ɁA���ߎs�ւ̌����ڏ��͂��łɖ@���̎��_�łȂ���Ă��茧����V���Ɍ����ڏ�����K�v���Ȃ��A�܂��A���j�s�܂ł͐ϋɓI�Ȍ����ڏ����\�ł��邪�A���ߎs�ւ̐ϋɓI�Ȍ����ڏ��ƂȂ�Ɓg���̂��ׂ����Ɓh�̃��C�����s���m�ɂȂ��Ă��܂����߁A���j�s�ȉ��ւ̌����ڏ��ɂ͐ϋɓI�ł����Ă��A�É����̂悤�Ɉ�����z���������ڏ��ɂ͏��ɓI�ɂȂ炴��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���ɁA�����ɂQ�̐��ߎs������R���ł͐��ߎs�l�������l���̔����ȏ���߂Ă��邽�߁i�_�ސ쌧59���A������60���A�É���49���i
��2�߁@���{���`���ߎs�̐l����
2000�N�̒n�������ꊇ�@�{�s�ɂ��A�s���{������s�����ւ̌����ڏ����i���Ƃɂ���Đl���𗬂������������B�F�{���ł́A2002�N�ɑS�����̂�����݂Ƃ��Č����E�����E�l�ނ́u�O�_�Z�b�g�v���ڏ�����������Ƃ���[2]�B�����̃p�b�P�[�W�����́A�����̑升���Ō�����b�I�����̂̋K�͂��g�傷�邱�Ƃ��Ĉ�錧[3]�∤�Q��[4]�ɍL������{����Ă���B���Ǝs�����̐l���𗬂ɂ́A�����ڏ��ɔ����Č����s���Ă������Ƃɐ��ʂ����l�ޗ͂̒ƁA�W�̉~�����Ƃ�����̑_��������B
�@�����Ƃ����{���Ɛ��ߎs�Ƃ̌𗬂��A�s���{���Ǝs�����̐l���𗬂Ƃ͂܂��ʂ̈Ӗ��������Ă����B��p�i2000�j�́A�u���ߎw��s�s���x���ɂȂ�ƁA�l�ނ��L�x�Łi�����j�{���̗D�G�Ȑl�ނ��u���v�Ƃ����j�[�Y�͂��܂�Ȃ��v�A���u�������Ⴍ�������Ȑ��ߎw��s�s�ƕ{���̊W��ǍD�Ȃ��̂ɕۂ��߂Ɂi�����j�𗬂��͂��܂�i�����j���ꂪ���݂ł͊��S�ɒ蒅���āA���܂��܂ȍs�����s����ɂ����čD�e���������炵�Ă���v[5]�Əq�ׂĂ���B
�E�e���Ɛ��ߎs�Ƃ̐l���𗬂ɂ���
�@�����ŁA�e���l���ۂɓd�b�ɂ��q�A�����O�����肢���A���̂悤�ȓ��e�邱�Ƃ��ł����B
�y�_�ސ쌧�`
�_�ސ쌧�́A���ߎs�Ƃ̐l���𗬂����{���Ă��邪���̎傽��ړI�͋������Ƃ̎��{��������ł���B
�y�����`
�{�N�x�É����̐l���𗬑��v�́A����57�l�ł��̂���27�l
�y�������`
�������ł́A�s�����Ƃ̋������C�v���O���������{���Ă��萭�ߎs������ɎQ�����Ă������A���݂ł͍s���Ă��Ȃ��B�����ڏ��ɂ��Ă̐l���𗬂́A�s���Ă��炸�������Ƃ̎��{�i��F�˂���s�b�N�̎��{�A��K�͓y�؎��Ƃɂ�����p�n�����j�ɂ��ĕK�v�������������Ƃ��ɂQ�N���x��P�ʂƂ���10����̐l���𗬂��s���Ă���B
�y���{�`
1965�N�̕{�m���Ǝs���̊Ԃō��k����{����i�{�s�����j�A�����̐��i��ړI�ɐl���𗬂�����B�ȍ~���݂ɑΓ��ȃ|�X�g�Ől���𗬂����{���A2000�N�ɂ́A17�l�̌𗬎��т�����B���^�Ɋւ��Ă͔h���������S���A��ʔ�ȂǂɊւ��Ă͎���悪���S�B���s�{�`
����A
�܂�A���{���Ɛ��ߎs�Ԃ̐l���𗬂ɂ́A��̗ތ^������ƍl������B�@�������Ƃ̎��{�ɂ����鋦�͑̐��̂��߂̐l���𗬂Ƃ����^�C�v�ƁA�A�����E���ߎs�ڍs���_�@�Ƃ��������ڏ��̂��߂̐l���𗬂Ƃ����^�C�v�ł���B
�@�������Ƃ̎��{�ɂ����鋦�͑̐��̂��߂̐l���𗬂Ɋւ��ẮA�{���ɂ��s�����ւ̐l�ޒƂ������́A�������Ƃ̑������ߎs�Ɛl���𗬂����邱�Ƃɂ���āA�~���ȑ��ݘA���̐����\�z�ł��A���Ƃ̎��{�����₷���ł���Ƃ������A�g���݂̂Ȃ���h���d���������̂ł���B
����A�A�����E���ߎs�ڍs���_�@�Ƃ��������ڏ��̂��߂̐l���𗬂Ɋւ��ẮA�V�������Ƃ��s�����ƂɂȂ����V�s�ɑ��Ă��̎��Ƃɏ]�����Ă����m�E�n�E�̂���E����h�����邱�ƂŁA���Ƃ̈��p�����s�����Ƃ�ړI�Ƃ����g�l���𗬂ɂ�鎖�Ƃ̈��p���h���d���������̂ł���B
�����ɂ�鐭�ߎs�w��́A����
�@�@
��3��
�܂Ƃ�
�@���ߎs�ƌ��́A�����Γ�d�s���̕��Q�Ƃ��Č���A���̉����́g�L��s�����A��s�s���h�Ƃ��������Ŗ����̎s�������x�{�s������̃e�[�}�ł������B������������肪��������������̂Ȃ��ʼn����ł���Ƃ͍l���ɂ����A�������������肷�鋫�E���̐����������Ǝs�̍��ӂɈˋ�����̂͂�ނ����Ȃ��ƍl����B���j�s�ȉ��ւ̊�b�I�����̂ւ̌����ڏ���ϋɓI�ɍs���Ă������Ƃ͗e�Ղł����Ă��A���ߎs�ւ̌����ڏ��́A�Z�ݕ����ɂ����Ƃ��C���������ł����āA�ŏI�I�ɂ́A���B����n�����x������̓��\���Ɉˋ����邱�ƂɂȂ�ƍl������B��������������̐ݒu�ɂ��A��b�I�����̂̎��ȓ����͈̔͂͑傫���g�債�A��������ł���悤�ɂȂ�ȂǍٗʌ����g�債�����A���Ɗ�b�I�����̂Ƃ�킯�A���ߎs�̖��������߂�ɂ͑傫�Ȍ��͂����Ă���Ƃ͂����Ȃ��B
����𗠕t���錤���Ƃ��āA�_�ސ쌧�̃��[�L���O�O���[�v�́A��������������̖��_���w�E���Ă���B��������������ɂ�錠���ڏ��̐��x�́A�@���̂Ȃ��ň�̓Ɨ����������Ƃ��Ė��L����Ă��Ȃ�����s�����Ɍ����ڏ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł���[8]�B�@�ֈϔC�������p�~����A�������������Ⴊ�{�s���ꂽ���ł��A���������������x���Ǝs�����̊W���߂Ă��邽�߁A���ۂɎ������s�����Ǝs�������ڏ��̍��ӂɒB���Ă��@������{�ł��Ȃ��Ƃ������P�[�X�́A��b�I�����̖̂����𑊌ݎ���I�Ɍ��肷��d�g�݂Ƃ��Ă̎�������������̋@�\�������I�ł��邱�Ƃ��������Ă���B
�@�������A�É����̂悤�ɁA���B���ɐ悪���Đ��ߌ��\�z��ł��o������Ō����ڏ����s�������̂�����B�É����̌����ڏ��́A�\2-1.�ɂ݂��悤�ɑ����Ƃ͈�����悵�Ă���A�������i���s���ӎv���傫���B���̓��\�ɐ���ڏ��v�悪���x�A�ǂ̂悤�ɕ]�������̂��A���ڂ������B