
9月入学ですが、一緒に頑張っていきたいと思っています。
研究テーマは『国会議員・首長の世襲・多選の禁止および制限の可能性について』
です。
よろしくお願いします」
(写真は、特にどこと言うわけではないのですがーーー
アルバイト先(予備校)で撮影したものです。)
公共経営研究科
45032001-7 亀井 琢磨
自治制度演習
「市町村合併にともなう設置選挙における
首長・議員当選者等の実態とその問題点」
1 はじめに ~市町村合併と定数削減~
現在、全国に約3200存在する地方自治体を1000程度に統合しようとする市町村合併が推進されている。我が国の地方自治体は、「明治の大合併」、「昭和の大合併」の2度の合併を経て、ほぼ今日の姿となったのであるが、今、新たに「平成の大合併」が行われようとしているのである。この合併のねらいとして、主に3点が挙げられよう。第一は地方分権の受け皿となるような自治体の基盤作り、第二には、一地方団体で対応できない広域的な行政需要に対し、近隣自治体の合併によって対応していこうとする考え、そして、第三として、重要なのは国、地方の赤字財政構造の改革ということである。現在、国、地方を合わせて約700兆円の債務を抱えており、この改善のためには一般会計を圧迫している地方交付税交付の削減が急務であるとの考えから、この市町村合併が急速に押し進められていると思われる。
特に、昨今では、この財政改革の面から、多くの自治体で合併と同時に、議会定数の削減が行われている。合併を行わない市町村においても、財政上の問題から自主的に議会の定数削減を行う地方自治体が全国的にも増加しているが、市町村合併により、複数の自治体が合併するケースの場合、旧自治体の定数をそのまま維持するのは、不合理であり、また、法律により、議員定数の上限が定められていることから、議会定数の削減がおこなわれているものである。
しかし、一方で、議会というものは、多数の住民の民意を反映すべきものである。価値観が多様化する今日、住民の意見というものも多種多様であり、上限よりも大幅に削減して定数を減らせば、当然、これまでよりも民意が反映されにくくなると思われる。また、選出される首長や議員も大きな組織・集票マシンを持った候補などが当選し、組織のない現職、新人候補の進出は難しくなってしまうことも予想される。そこで、実際に自治体合併を経て、本選挙を行ったいくつかの自治体のケースを取り上げ、選挙によって、どんな候補者が当選したか、選挙戦はどうであったのか等に焦点をあてながら、以下、これらの点について考察を進めたい。
2 昨今の具体的事例から
ここでは、近年行われた個々の具体的な自治体合併を通して、合併に伴う議員の在任特例の適用状況と、その後に行われた選挙の結果から、自治体合併、そしてそれに伴う議員定数の削減が本選挙においてどのような影響をもたらすのかを考察してゆく。
①
西東京市のケース・・・市長選・市議選
2001年1月、東京都の保谷市と田無市が合併し、「西東京市」が誕生した。合併後の西東京市の市長選挙では、旧保谷市長と旧田無市長がそろって立候補し、旧自治体同士の熾烈な選挙戦となった。選挙期間中は、自治体同士のメンツをかけた激しい選挙戦となったと報じられている。結果は、それぞれの候補が地元の票の多くを獲得したが、旧保谷市長の保谷高範氏が旧保谷市地区の票を手堅く固めて当選を果たした。
また、市議選では、条例により新市の議員定数を30に定めたが、条例の中に「合併後初めての選挙に限り、定数を36とする」という条項が盛り込まれたため、今回の選挙は定数36名で行われた。旧保谷市・旧田無市ともに議会定数は24であり、本則では定数が激減することから、この条項は急速な定数削減を避けたいという議員との妥協によるものと考えられる。結局、定数36に39名が立候補し、大半の現職が議席を守る結果となったが、社民・自由両党では1名ずつ落選した。この結果は、両党の党勢が停滞していたことを勘案しても、やはり自民・公明・共産などの組織政党の組織選挙の強さ、複数当選を果たしている現職勢の強さを示している。なお、旧保谷市、旧田無市ともに合併前の選挙はいずれも定数を2~4名超える競争率であり、大幅な競争率の変化は特に見られなかったことを付け加えておきたい。
②
さいたま市のケース・・・市長選・市議選
2001年5月、埼玉県の浦和市、大宮市、与野市の3市が合併し、人口103万人の「さいたま市」が新たに発足した。その後、さいたま市は全国13番目の政令指定都市となり、今日に至っている。合併および政令指定都市になったことにより、これらの3つの旧自治体は、新たに9つの区に改編され、市議会議員選挙も区ごとに行われた。合併に伴う市長選挙は乱立選挙となり、8名が出馬したが、①のケースと同様に、旧浦和市長の相川宗一氏と旧大宮市長の新藤享弘氏がそろって出馬し、旧自治体首長同士の争いとなった。選挙結果は、旧浦和市長の相川氏が浦和地区の票を固めて当選したが、旧大宮市長の新藤氏は大宮地区の票の大半を獲得するなど、地域政争の色も濃い選挙であったと言われている。ここでもやはり有権者の地元重視の傾向がうかがえる。
さいたま市長選挙結果 (表記は名前・年齢・得票・役職)
|
当選 |
相川 宗一 |
58 |
131822 |
旧浦和市長 |
|
落選 |
新藤 享弘 |
68 |
109522 |
旧大宮市長 |
|
落選 |
岡 真智子 |
53 |
49505 |
前県議 |
|
落選 |
高橋 秀明 |
44 |
39323 |
元県知事秘書 |
|
落選 |
沼田 道孝 |
48 |
21662 |
党役員(共産推薦) |
(注・上位5名のみ掲載)
また3市の合併後の初の市議会議員選挙は、2003年4月の統一地方選挙の中で行われた。さいたま市の定数は64とされたが、旧3市の合併前の議会定数は3市計で102名であり、定数は3分の2に削減された。合併前の定数は浦和市が40、大宮市が36であったが、与野市では、合併前は26人の議会定数であったが、合併により、与野市全域が「中央区」という市内の1つの区に改編され、この中央区は定数5とされたのである。
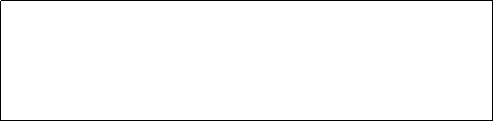 合併前定数 合併後定数
合併前定数 合併後定数
浦和市 40 → 30 (桜区6、浦和区8、南区10、緑区6)
大宮市 36 → 29 (西区5、北区8、大宮区7、見沼区9)
与野市 26 → 5 (中央区5)
合計 102 → 64
これまで26名選出されていた地区から今度は5名しか選出できない状況になったため、
やむなく引退を余儀なくされた議員も多かったとのことである。中央区では、現職9名、新人1名の計10名が出馬し、激戦が展開された。政党別内訳は自民4、民主・公明・共産・社民各1、無所属2であった。結果は、自民2、民主・公明・共産各1のすべて現職が当選し、現職は4名が落選した。
しかし、同区でトップ当選を果たした最大の保守系会派団長の自民現職はその後、公職選挙法違反で逮捕され、定数5の西区でも2位当選を果たした前大宮市議長のベテランの自民現職がやはり買収で逮捕されるという事態に発展したのである。どちらも組織もある大物議員だが、このような事態になったのは、それだけ合併による選挙区の変化、定数減の危機感があったからに他ならないと考える。
また、当選者の当選回数を比較すると、下記の図のとおりになるが、やはり現職の優位を示している。旧大宮市域に限れば、新人の健闘ということも指摘することができるが、逆に旧浦和市域では、新人候補は1名の当選に留まり、定数10の選挙区では現職全員が当選するなど、現職候補の圧倒的な強さを見せつけた。
地区別の当選者の当選回数の内訳
|
|
新人 |
1回 |
2回 |
3回 |
4回 |
5回 |
6回 |
7回 |
計 |
|
旧浦和 |
1 |
11 |
6 |
6 |
1 |
1 |
2 |
2 |
30 |
|
旧大宮 |
8 |
8 |
3 |
4 |
2 |
2 |
2 |
|
29 |
|
旧与野 |
|
2 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
5 |
|
計 |
9 |
21 |
10 |
11 |
3 |
3 |
4 |
3 |
64 |
(注・当選回数は旧自治体における当選回数。今回の選挙の当選回数は含めない)
さいたま市の場合は、選挙区自体は逆に狭くなっているが、この選挙においても、組織をもつ現職、地域密着型の現職の強さがうかがわれる。
③
新潟市のケース・・・市議選
2001年1月、新潟県内の新潟市と西蒲原郡黒埼町が合併した。このケースでは、黒埼町を新潟市に編入する編入合併の形で行われた。黒崎町議会は定数22、新潟市議会は定数48であった。編入合併により、黒崎町議会議員は、そのまま新潟市議会議員として地位を保障されることになった。また「在任特例」により、2003年4月の改選まで、定数はそれぞれの定数の合計の70で維持された。黒崎町議会選挙ではこれまで約400票で当選できたが、合併後の新潟市議会選挙では、最低でも約2500票獲得しなければ当選できないこととなり、大半の議員は引退をしたといわれている。実際の改選選挙でも、黒崎町の議員は4名の当選に留まったのである。このことは、特に、人口規模の小さな市町村が大きな市町村と合併した場合には、地元から送り出すことのできる議員が急減することを示している。
④
野田市のケース・・・特例法による議員の存在
私の住む千葉県においては、県の北西部に位置するしょうゆの町で知られる野田市と東葛飾郡関宿町が2003年6月に合併を果たした。これまで、野田市の議員定数は32、関宿町は20であったが、現在合併特例法により、現在52名の議員を抱えている。野田市議会議員選挙は2002年5月、関宿町は2000年4月に行われた。本来ならば関宿町議は、2004年4月に改選を迎えるはずであったが、特例法により、次回2006年5月の野田市議会改選まで改選を経ずに約2年近く延長してその職を保障されることとなった。昨今では、このような特例措置に対して、住民からは議会不信の声があがっていることも注目する必要があろう。香川県の内海町・土庄町・池田町が合併して誕生した「東かがわ市」では、特例により、上限を超える議員定数の維持を決定したところ、住民がリコール運動を展開していることもここで付け加えておきたい。
しかし、また、③の新潟市のケースで触れたが、合併によって選挙区が広域化すると、小規模自治体の地元議員の選出は難しくなることが予想される。従来、当選ラインが数十票であった自治体も大規模合併をすれば、数千票を取らねば当選できないという事態が起こるのである。その端的な例として、千葉県館山市・鴨川市と安房郡9町村の合併がある。県が示した合併パターンでは、人口15万規模、面積も広大な範囲となる。現在、11市町村の総議員定数は183であるが、合併によって新しい市が誕生した場合、議員定数の上限は34名となり、一気に150名近く定数が減ることになる。このことは、財政の面から見れば、議員報酬の大幅抑制につながり、各自治体の負担を軽減できる効果をもつかもしれない。しかし、図にあるように人口4600人の三芳村ではこれまで100票前後を獲得すれば当選することが可能であったが、この合併パターンに従って合併が行われ、定数34で選挙が行われた場合、最低でも1500票は獲得しなければ当選は難しいと考えられる。また、これまで三芳村では、人口4600人で14名の議員を送り出しており、住民約330人で1名の議員という割合であったが、合併により、議員1名あたりの人口は約4420名となり、約13倍となることから、三芳村住民の地元の意見というものは、新しい市の中では、反映されにくくなることは必至である。また、三芳村以外の自治体のケースにおいても同様に、議員1名あたりの住民の割合は増大するという結果となっている。
主な自治体の合併前・後の選挙の変容
|
旧自治体時 |
旧自治体名 |
田無市 |
保谷市 |
黒崎町 |
関宿町 |
三芳村 |
|
①合併前定数 |
26 |
26 |
22 |
20 |
14 |
|
|
②合併前当選ライン |
700 |
800 |
400 |
500 |
100 |
|
|
③人口数 |
75000 |
98000 |
25900 |
32300 |
4600 |
|
|
④議員1人あたりの人口 (③/①) |
2885 |
3770 |
1177 |
1615 |
329 |
|
|
|
新自治体名 |
西東京市 |
新潟市 |
野田市 |
*安房郡市 |
|
|
合併後 |
⑤合併後定数 |
36 |
52 |
*32 |
*34 |
|
|
⑥合併後当選ライン |
1100 |
2500 |
*1500 |
*1500 |
||
|
⑦人口数 |
173000 |
483500 |
152200 |
150400 |
||
|
⑧議員1人あたりの人口 (⑦/⑤) |
4806 |
9298 |
4756 |
4424 |
||
(注・関宿町、三芳村はまだ選挙が行われていないので数値は概算)
そうしたことから、昨今では、合併後に旧自治体単位で「地域自治組織」なるものを組織することにより、自治体が広域化しても、各自治体の意見を反映できるような仕組みを設けようという動きがあがっている。これについては、今後の研究の中で取り上げていきたいと考えている。
3 まとめ ~今後の展望と理想~
以上のように、昨今の市町村合併に伴う定数削減とその後の自治体議員選挙の個々のケースを見てきた。まだ自治体合併は全国的にはじまったばかりであり、具体的なケースは数的に限られていたが、それでも比較する中で、以下のとおり、いくつかのことが考えられる。
1) これまで見てきたように、合併により議員定数が削減されると、新人候補にとって、当選は合併前よりも厳しいものとなる。それは、多数の自治体の合併によって、選挙区が通常広域化するという事情に加え、合併に伴う定数削減により当選ラインが上昇し、これまでの選挙よりも、さらに多くの得票を必要とするからである。このことは新人のみならず、現職議員であっても、組織のない候補者や地域に強い影響力のない候補者にも言えることである。実際に、上述の例でも明らかなように、新人候補の進出は今のところ目に見える形で結果に表れていない。同時に現職議員であっても、これまでよりも選挙自体への取り組みが困難になることや当選ラインの上昇が引退の原因にもなっていることがうかがえる。選挙自体の取り組みの難しさは、人員不足や資金の問題などが考えられる。現在の小規模の自治体でも、多くの候補は公営掲示板へのポスター掲示が大変と言われている。選挙区が広域化すれば、このポスターの問題や政策ビラの戸別配布など選挙戦術上の問題が発生するために、大きな支援組織のない候補者にとって、立候補のハードルが高くなるということを関連して付け加えておきたい。
2) また、定数削減が新人の立候補の意欲そのものをも失わせる可能性も大いに考えられる。自治体選挙において、有権者は地元重視の傾向が強いことをこれまで見てきた。定数削減と選挙区の広域化のもとで、地元から有力候補が出馬すれば、組織のない候補にとっては、それだけ不利になり、立候補をすることが困難にならざるを得ないと思われる。たしかに、「強力な地域のしがらみの中で立候補すら不可能であった地方において、選挙区が広域化したことで、当落は別として、新人にも門戸が広がったのではないか、有権者にとっても、無風選挙から一転して、選択の幅が広がったとも見ることができるのではないか」との見方もある。 しかし、上記のケースからもわかるように、合併後の本選挙の競争率は、合併以前とそれほど変化はなく、実際には、やはり新人にとっては立候補の門戸が広がったとは言えないのが現状である。
3) さらに、大幅な定数削減が行われると、これまでよりも住民の民意は反映されにくくなるという問題が発生すると思われる。合併によって、住民ひとりあたりの議員の数は確実に減少する。合併による本選挙では、編入合併された黒崎町のケースのように、編入された側の自治体から見ると、当選するには、これまでの数倍の得票を必要とするため、当選することが非常に困難となる。定数が大幅に減ることは、それだけ、地域の有力者やボス的人物、組織政党候補が当選し、議席が固定化する可能性が大きくなると思われる。
私自身は町村部における議会の現状を視察した経験から、地方の議会の刷新ということが必要であることを痛感している次第である。例えば、ある自治体では、4年間で質問ゼロという議員が存在するし、質問が数回という議員も多いことが指摘されている。まさに議員職は名誉職となっていたり、地区での持ち回りというのが、地方の実情であり、議会の形骸化が起きている。そうであるからこそ、私は合併による定数是正は、一定程度は必要であると考える。それは、定数削減がある面では議員に緊張感をもたらし、議会の活性化につながるのではないかと考えるからである。さらに言えば、議員定数の削減ということが、住民の意識を向上させるきっかけにもなりうると考えるし、住民の意識向上がある程度、自治体議員選挙の投票行動に反映されれば、こうした任務を果たしていない議員を減らすことを可能とすると考えているからである。有権者に地域の政治に目を向けさせ、行動させる発端となれば、いわゆる地方に蔓延する金権腐敗や議会の停滞がおのずから改善されていくのではないかと期待を抱いているところである。
しかしながら、合併にともなう定数削減と選挙区の広域化の結果、新人の立候補、当選が困難になる傾向のあることは、以上見てきたとおりであり、今後、多くの優秀な新人議員が立候補し、当選することができるよう、選挙機会の平等の観点から、さらに、制度と運用の改善について検討を進めていく必要があると考える。
【参考文献等】
横田 昌三著 「遠のく住民自治」(現代シリーズ14 2001年)
保母 武彦著 「市町村合併と地域のゆくえ」(岩波ブックレット№560 2002年 )
小原 隆治編著「これでいいのか平成の大合併」(コモンズ 2003年)
高島 茂樹著 「市町村合併のそこが知りたかった」(ぎょうせい 2002年)