�\�[�V�����E�L���s�^���𒆐S�Ƃ����n��Đ��̉\��
�@�����o�c�����ȁ@�א�r�F
�O�D�{���|�[�g�̂˂炢
�@�{���|�[�g�́A�܂��A����܂ł̒n��Đ��̗����v�A���̒��ŁA�����I���W�_�I��������������Ă��邱�Ƃ������B���ɁA�\�[�V�����E�L���s�^���̍l�����Ƃ��̔��W�̕��������������ƂŁA�����I���W�_��ʂ��āA�n��Đ��ɂ����āA�\�[�V�����E�L���s�^���̍l�������ʒu�Â��邱�����\�ł��邱�Ƃ������B�Ō�ɁA���݁A�\�[�V�����E�L���s�^���̂����A�u���b�W���O�@�\�𒆐S�Ƃ����n��Đ��̉^�������Ă��鎖��������A�n��Đ��̉\���������B
�P�D����܂Œn��Đ��̍l�����̂܂Ƃ�
�`�O���I���W��������I�E���l�Ȏ�̂ɂ�锭�W�ց`
1987�N�̑�l���S�������J���v��ɑ�\����邱��܂ł̒n��Đ��Ɋւ���c�_�́A�E�オ��̎���w�i�̒��ōs���Ă����B���̂��߁A�����ɂ���A�Y�Ƃɂ���A�L���Ȓn�悩�炢���Ɏ����Ă��邩���嗬�ł������B�������Ȃ���A�o�u���̕���A���ƒn���̍�������A�n�������ƈڂ�ς�鐢��ɂ������A���̕ω��ɂ��A�n�抈�����������{��́A���Ƃ𒆐S�ɑ�s�s�ɏW�������x��S���̒n���s�s���ɕ��z����Ƃ������̂���A�s�����Ȃǂ���̂ɒn�掑�������p�����n�掩�����������̂ւ��K�v�������܂��Ă����B
�S�������J���v��̍l����������Ɓi�\�P�Q�Ɓj�A���̋c�_�̐��ڂ����m�ł���B�c�_�́A���_�𒆐S�Ƃ����J������A�S���S�́i���ɕ��U�^�j�ւ̊J���ւ̕ω��A�����āA���l�Ȏ�̂̎Q���ɂ�鍑�y�Â���Ƒ傫���ς���Ă��Ă���B
|
�\�P�@�S�������J���v�於�̗��� |
|||||
|
�v�於 |
�S������ �J���v�� |
�V�v�� |
��O�� |
��l�� |
��� |
|
���莞���i�t�c����j |
1962�N |
1969�N |
1977�N |
1987�N |
1998�N |
|
�w�i |
�P���x�������o�ςւ̈ڍs �Q�ߑ�s�s���E�����i�� �R�����{���v�� |
�P���x�����o�� �Q�l���A�Y�Ƃ̑�K�͏W�� 3��A���ۉ��A�Z�p�v�V�̐i�W |
1 ���萬���o�� 2�l���A�Y�Ƃ̒n�����U�̒��� 3���y�����A�G�l���M�[���̗L�����̌��݉� |
1�l���A���@�\�̓�����ɏW�� 2�Y�ƍ\���̋}�ȕω��Ȃǂɂ��n�����ł̌ٗp���̐[���� 3�{�i�I���ۉ��̐i�W |
1 �n������i�n�������A�勣���A�A�W�A�����Ƃ̌𗬁j
2 �l�������E�������
3 ���x����� |
|
��{�ڕW |
�n��Ԃ̋ύt���锭�W |
�J���\���̑S���y�ւ̊g�� |
�l�ԋ��Z�̑����I���̐��� |
���ɕ��U�^�̍\�z |
�����^���y�\���`���̊�b�Â��� |
|
�J������ |
���_�J���\�z |
��K�̓v���W�F�N�g�\�z |
��Z�\�z |
�𗬃l�b�g���[�N�\�z |
���l�Ȏ�̂̎Q���ƒn��A�g�ɂ�鍑�y�Â��� |
�{�{����,
���ɁA���y�R�c��@�v�敔��@�����n��Љ���ψ���ɂ����Ă��A�u�l���������i�W���钆�ŁA�����\�Ŏ����I�Ȓn��Љ�̎p���ǂ��`�����B�v�A�u�n��R�~���j�e�B�̍����I�ȈӋ`�ɂ��Ăǂ��l���邩�B�v�A�u���l�ȎЉ�I�T�[�r�X�i�����֘A�T�[�r�X�j�������I�ɒ��邽�߂̒n��Љ�̌o�c�V�X�e�����ǂ̂悤�ɍ\�z���Ă������B�v�ȂǂƂ������c�_���i�߂��Ă���i�����@�����n��Љ���ψ���i2006�N�U���j�u�����n��Љ�̌`���Ɍ����āv�i����܂ł̌����̐����j�i�āj�j�B�܂��A2004�N�O�ォ��n��̎������L�[���[�h�ɂ��āA���t�{�𒆐S�Ƃ����n��Đ��E�s�s�Đ����Ƃ��i��ł���B�����̒��ŁA�n�掩�������傫���c�_����A�n�悪�ǂ̂悤�ɂ��Ď������邩���c�_�̏œ_�ƂȂ��Ă��Ă���B
���̒n�掩�����ɂ́A1970�N��ȍ~�W�J����Ă����A������u�n���`�v�u�����I���W�_�v�̍Č�����K�v�Ƃ��Ă���B�u�����I���W�_�v�́A�ߌ��a�q�Ȃǂɂ��c�_���͂��܂�A�u�ꏊ�v�A�u���ʂ̕R�сi���ʂ̎Љ�I���l�E�ڕW�E�v�z�j�v�A�u���ݍ�p�i��Z�ҊԂ̑��ݍ�p�E��Z�҂ƒn��O����̕Y���҂Ƃ̑��ݍ�p�j�v�Ȃǂɒ��ڂ��A�n��𒆐S�Ƃ����A�Љ�W���������i�ߌ��a�q�i1996�j. �g�����I���W�_�̓W�J�h, �}�����[�j�B���̍l�����́A���{�ɂ����āA����܂ł̋ߑ㉻�_�E�J���_�I�Ȏ����ɑ��āA�n��̎������Ƃ������߂đR�������������̂ł������B�������A�{��A�n��Â���Ƃ����ʂł́A�l�X�Ȏ���͕���Ă��邪�A�����I���W�_�ɂ���̓I�Ȏ�@�̌����Ƃ����_�ł́A�����A�����ȋc�_�ɂ͎����Ă��Ȃ��B
�Q�D�\�[�V�����E�L���s�^���̍l�����Ɣ��W�̕������ɂ���
�`�����I�Ȕ��W�_�ւ̓W�J
�@�\�[�V�����E�L���s�^���́A���o�[�g�E�p�b�g�i���iRobert Putnam�j�ɂ��A�w�u�\�[�V�����E�L���s�^���v�Ƃ́A�u�Љ�I�Ȍq����i�l�b�g���[�N�j�Ƃ������琶�܂��K�́E�M���v�ł���A���ʂ̖ړI�Ɍ����Č��ʓI�ɋ����s���ւƓ����Љ�g�D�̓����x�ƒ�`���Ă���B
�@���̏�ŁA�p�b�g�i���́A���̂Ȃ���̐������A�u�����v�Ɓu���n���v�Ƃ�����ɕ����A�X�ɂ�����u�`�ԁv�A�u���x�v�A�u�u���v�Ƃ����O���ŕ��ނ��A�ȉ��̕\�Q�̂悤�Ɏ������B���݂́A�\�[�V�����E�L���s�^���̑���̕��@����сA�n����̉����̂��߂ɂ́A�ǂ̂悤�Ȏ{�\�[�V�����E�L���s�^���̌���ɕK�v���Ƃ����c�_����������Ă���B
|
�\�Q�@�p�b�g�i���ɂ��\�[�V�����E�L���s�^���̕��� |
||||
|
�����̌^ |
�����ibonding�j�^�@ex.�����l�b�g���[�N |
���n���ibridging�j�^ex.���c�� |
||
|
�`�@�� |
�t�H�[�}���@ex.PTA�A�J���g�� |
�C���t�H�[�}���@ex.�o�X�P�b�g�{�[���̎��� |
||
|
���@�x |
�����@ex.�Ƒ����J |
�����@ex.�m��Ȃ��l�ɑ��鑊�� |
||
|
���t�{����������,(2003). �g�\�[�V�����E�L���s�^���|�L���Ȑl�ԊW�Ǝs�������̍D�z�����߂ā|�h����쐬 |
�����u���@ex.���H��c�� |
�O���u���@ex.�ԏ\�� |
||
�@���̋c�_�́A����܂ŁA�Љ�w�E�Љ�S���w�ɂ����āA�����W�J����Ă����l�b�g���[�N����ѕR�т̍l�����A���ʂ̖ړI�Ɍ����Č��ʓI�ɋ����s���ւƓ����Љ�g�D�̂�������ѕt�����Ƃ����_���Ӌ`���������B
�@�����c�_���A�O�q�����n��Đ��̍l�����̒��ł����u�����I���W�_�v�́u�ꏊ�v�A�u���ʂ̕R�сi���ʂ̎Љ�I���l�E�ڕW�E�v�z�j�v�A�u���ݍ�p�i��Z�ҊԂ̑��ݍ�p�E��Z�҂ƒn��O����̕Y���҂Ƃ̑��ݍ�p�j�v�Əd�ˍ��킹��ƁA�����̗v�f������̓I�Ɏ����A��̓I�Ȏ{���܂ł̋c�_�������Ƃ��ł����Ƃ����Ӗ��ŁA�����Ӌ`�������B
�R�D �\�[�V�����E�L���s�^���𒆐S�Ƃ����n��Đ��^���̃��f���ɂ���
�@�����ŁA�����ł́A�\�[�V�����E�L���s�^���́u�����^�v�Ɓu���n���^�v�ɕ����A���ꂼ������������A�W�J�̉\����}��B���ۂ́A�����̎�@�͂��ꂼ��̋ǖʂł̗������\�ł��邪�A�����ł����O�^�Ƃ��Ď����B
�@�@�����^�̒n��Đ���@�̃��f��
�@�s���Ȃǂ����S�ƂȂ�A�n����E�ۑ�ւ̋C�Â������߁A��������Z���̈ӎ��̕ϗe�A�����͂����サ�A�������s�����Ƃł̒n��Đ��������^�����s���B
�@���f���Ƃ��ẮA�n�������c�̂Ȃǂ̏�M�̊������A�n��ӎ��̕ϗe�������͂̌��と�n��Đ��ւ̊����Ɣ��W����B���̂��߁A��M���s���c�̂̂������i�l�E�����E�����Ȃǁj�̑召���傫�ȃ|�C���g�ƂȂ�B
�}�P�@�����^�n������f��
�@
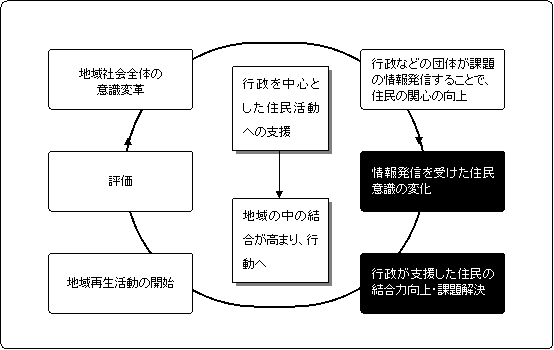
�k�C���m��������,(2005). �g�\�[�V�����L���s�^���̏����ƒn��͂̌����h���Q�l�ɍ쐬
�A ���n���^�̒n��Đ���@�̃��f��
�s���E�t�@�V���e�[�^�[�Ȃǂ����p���Ēn����E�ۑ�ւ̋C�Â������߁A���[�N�V���b�v�Ȃǂɂ��Z���ԁE�g�D�Ԃ̌𗬂ɂ��A�ӎ��̕ω����N����B���̏�ŁA�n����O�̎x�����܂߂��n��S�̂ł̒n��Đ��̉^�����s���B
�@���f���Ƃ��ẮA�n�������c�̂Ȃǂ̏����A�����^�̂悤�ɔ�r�I����I�ɔ��M����̂ł͂Ȃ��A���[�N�V���b�v�Ȃǂ̃t�@�V���e�[�^�[�ȂǂƂ̑Θb�ɂ��ӎ����N���n��ӎ��̕ϗe���ۑ�ɑΉ��������L���g�D�E�l�̂Ȃ���ɂ��n��Đ��ւ̊����Ɣ��W����B���̂��߁A�t�@�V���e�[�^�[�Ȃǂ̊��́E���ӌ`���p�Ȃǂ̒���\�͂��傫�ȃ|�C���g�ƂȂ�B
�}�Q�@���n���^�n������f��
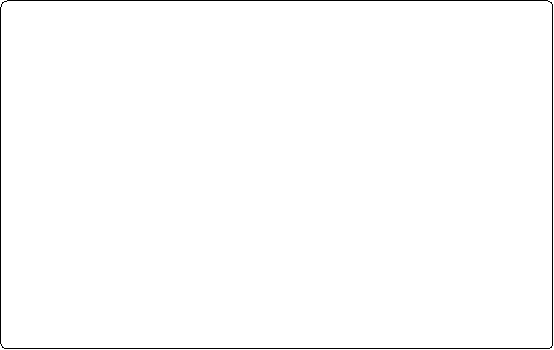 �@
�@
�k�C���m��������,(2005). �g�\�[�V�����L���s�^���̏����ƒn��͂̌����h���Q�l�ɍ쐬
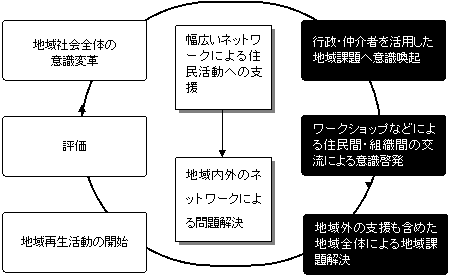
�B
�����^�Ƌ��n���^�̒n��Đ����f���̔�r
�@��L��̒n��Đ��̃��f�����r����ƁA�\3�̂悤�ɂȂ�B�u�����^�v�ł́A���������߂邽�߂̎��������Ȃ��ƌ��������܂��s���Ȃ��\��������B���ɁA���݂̒n��s�����̈����ȂǂŎ������R�����ꍇ�́A�u�����^�v�̃��f�������܂������Ȃ����Ƃ��l������B���āA�u���n���^�v�́A�t�@�V���e�[�V�����Ȃǂ̒���\�͂̍��Ⴊ�����ł��鎑���̑召�Ɍ��т��^���̐��ۂɊւ��\��������B
|
�\�R�@�����^�E���n���^�̒n��Đ���@�̃��f������ |
||
|
�����̌^ |
�����ibonding�j�^�n��� |
���n���ibridging�j�^�n��� |
|
�n����̋C�t���� �������� |
�n��̒c�̂ɂ���M���� |
�n��̓��O�̊W�҂ɂ�郏�[�N�V���b�v�Ȃǂł̈ӎ��W |
|
������ ��@ |
�S�����߂��Z�������������߁A�ۑ�����̎��{ |
�n����O�̃l�b�g���[�N�𒆐S�Ƃ����L����ƈӎ�����̒��ʼnۑ�����̎��{ |
|
�|�C���g |
���������߂邽�߂̎��������Ȃ��ƌ��������܂��s���Ȃ��\������ |
�t�@�V���e�[�V�����Ȃǂ̒���\�͂̍��Ⴊ�^���̐��ۂɊւ��\������ |
�S�D
����ɂ��ā`���n���^�n��Đ����f���ɂ���
�@�u���n���^�v�n��Đ��̃��f���́A���݁A������s�������̒��Ԏx���c�̂̊����Ɍ��邱�Ƃ��ł���B�ȉ��ɑ�\��������B�����̊����̗�́A���ۂ́A�����^�Ƌ��n���^�̗����̐��i�����˔����Ă��邪�A���ɁA�����ł͋��n���^�̋@�\�𒆐S�Ɏ����B
�\�S�@���n���^�n��Đ����f���̎���
|
���� |
�ꏊ |
���� |
|
�����c�������@�l�s���p�[�g�i�[�Y�Z���^�[�i�C���^�[�~�f�B�A���[�j |
�V������D�n�� �i1999�N�ݗ��j |
�Z���A��Ƌy�эs���Ƃ̃p�[�g�i�[�V�b�v�Ɋ�Â��A�O�҂̒��Ԃɗ����ėl�X�ȃR�[�f�B�l�[�g��v�����j���O�A���T�[�`�Ȃǂ��s���A�n������C�ɂ���s���N�ƉƂ�NPO �����������Ă���B |
|
�����c�������@�l�����E�݂€�m�o�n�Z���^�[ |
�{�錧���s �i1999�N�ݗ��j |
�m�o�n�Ƃm�o�n�A�m�o�n�Ǝ����́E��ƂƂ��������L���c�̂�ړI�ɍ��킹�ăR�[�f�B�l�C�g���Ă���B�s�����A�������z�������L���l�b�g���[�L���O���s���Ă���B |
�ȏ�