�������x���K�i�Ж؏~�����j
����c��w��w�@�����o�c������
���������b�i45031003-8�j
�ۑ�
����̓s�搧�x���v�ɂ��s������ʋ�ւ̐��|���ƈڊǂ̊T�v�Ɩ��_
���ڎ���
�P�D
�͂��߂Ɂ\�s�搧�x���v�ɂ�鐴�|���ƈڊǂ̊T�v�\
�Q�D
�u���ݐ푈�v�ɂ��u����������̌����v�̉萶��
�R�D�@�@�u����������̌����v�̂�炬
�S�D
���ʋ搴�|���Ƃ̌���
�T�D
�u����������̌����v�̓]���_
�U�D
���_�\���|�����ڊǂɂ����ʂƍ���̉ۑ�\
�P�D
�͂��߂Ɂ\�s�搧�x���v�ɂ�鐴�|���ƈڊǂ̊T�v�\
2000�N4��1���Ɏ{�s���ꂽ�u�n�������@�̈ꕔ����������@���v�ł́A�@���ʋ�́u��b�I�Ȓn�������c�́v�ւ̖@���㖾�m�Ȉʒu�Â��A�A��s�s�n��̍s���̈�̐��E���ꐫ�ɔz���������ʋ�̎��含�E�������̋����A�B�s������ʋ�ւ̎����̈ڏ��A�����������B���̉����͔����I���̊ԑ������Ă������ʋ�̎������g�[�^���̏W�听�Ƃ��Ăׂ���̂ł���A���ʋ�ɂƂ��Ă͔ߊ�̒B���ł������ƌ����Ă���B
���ʋ�́A���N�u�s�̓����I�c�́v�Ƃ��Ĉ����Ă���A�s�͓��ʋ�̑�������ɂ����āA�{���Ƃ��Ắu�L��̒n�������c�́v�ƁA�s�Ƃ��Ắu��b�I�Ȓn�������c�́v�Ƃ����Q�̐��i�������Ă����B�������A����̓s�搧�x���v�ɂ��A���ʋ�́u��b�I�Ȓn�������c�́v�Ƃ��Ēn�������@�ɖ��L���ꂽ�B����A�s�͓��ʋ�̑�������ɂ����āA�u���ʋ������L��̒n�������c�́v�Ƃ��āA�@�s���{��������������̂Ƃ���Ă��鎖���y�ѓ��ʋ�Ɋւ���A�������Ɋւ��鎖���A�A�s����������������̂Ƃ���Ă��鎖���̂�����s�s�n��ɂ�����s���̈�̐��y�ѓ��ꐫ�̊m�ۂ̊ϓ_����s����̓I�ɏ������邱�Ƃ��K�v�ł���ƔF�߂��鎖���A����������Ƃ��ꂽ�B
����ɂ��A���ʋ�Ɠs�́A��s�s�n��ɂ����āu��b�ƍL��v�Ƃ��������S���邱�ƂɂȂ�A���ʋ�ɂ͂���܂ňȏ�ɂ��ꂼ��̒n��Z���̈ӌ��ɍ��������搭��W�J���A�n��ɂ��������I�Ȑ�������s���邱�Ƃ����҂��ꂽ�B�������Ċ�b�I�����̂Ƃ��ďZ���ɑ��đ��`�I�ɐӔC�����ƂƂȂ������ʋ�́A�s�������|���Ƃ��͂��߂Ƃ���Z���ɐg�߂Ȏ������Ƃ��ڏ����ꂽ�B
2000�N4��1������͂���܂�
|
���ʋ�̎�Ȑ��|���Ƃɂ�����������S |
||
|
���ʋ� |
|
|
|
�e���ʋ� |
����23�搴�|�ꕔ�����g�� |
|
|
�E��ʔp�����̏����v��̍��� |
�E���|�H��Ȃǂ̐����E�Ǘ��E�^�c |
�E�Y�Ɣp�����Ɋւ��鎖�� |
|
�E���݁A���A�̎��W�E�^���E���p��� |
�E�s�R���݁E�e�傲�ݏ����{�݂̐����E�Ǘ��E�^�c |
�E�V�C�ʏ�����̐ݒu�E�Ǘ��E�^�c |
|
�E���݂̌��ʉ��A�ė��p�A�������̑��i |
�E��ʔp���������Ƃ̋��Ɋւ�鎖�� |
�E��s�����̔p���������Ɋւ���x�� |
|
�E���ʎ��W�v��̍��� |
�E���A�����{�݂̐����E�Ǘ��E�^�c |
|
|
����23�搴�|���c�� |
|
|
|
�E�e��̂��ݏ����v��쐬�̒��� |
�@ |
|
�i�����P�j�F�w������\�O�搴�|�ꕔ�����g�����ƊT�v�x����сw���|�ƃ��T�C�N���x���쐬
�Q�D
�u���ݐ푈�v�ɂ��u����������̌����v�̉萶��
����̓s�搧�x���v�ɂ����鐴�|���ƈڊǂɎ���o�܂́A1971�N�ɋN�������u���ݐ푈�v�ɂ܂ők���čl����K�v������B���������邲�ݗʂɑ��āA���ʋ���̏ċp�{�݂�����Ȃ������ŊJ���悤�Ƃ���
�R�D�@�@�u����������̌����v�̂�炬
�������Ċe��ɒ蒅���Ă����u����������̌����v���������A����܂ő��������Ă������݂���������Ƃ������Ԃɒ��ʂ��A���̌����͂�炬�n�߂Ă����B�S���̂��ݗʂ������ł���̂ɑ��A���ʋ���̂��ݗʂ́A�s���uTOKYO SLIM�v�Ɩ��t���Ă��݂̌��ʂ�T�C�N���̐��i�̃L�����y�[�����͂��߂�89�N���s�[�N�Ɍ������������i�����Q�j�B
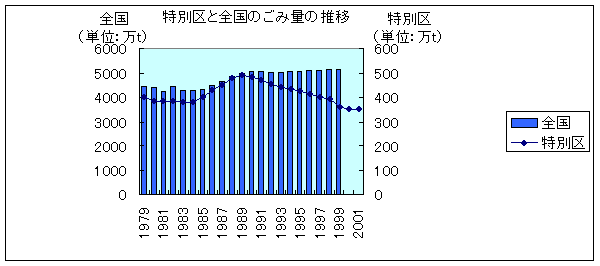 �i�����Q�j�F�w23�搴�|�ƃ��T�C�N���x���쐬
�i�����Q�j�F�w23�搴�|�ƃ��T�C�N���x���쐬
���݂̌����Ƃ��������ɂ�������炸�A1994�N9���ɓs�Ɠ��ʋ悪���ӂ����u�s�搧�x���v�Ɋւ���܂Ƃ߁i���c�āj�v�ł́A���ʋ悪�u���|���Ƃ̂��ׂĂɐӔC�������Ƃ���{�v�Ƃ��A�u����������̎����Ɍ����A�s�̌��s���|�H�ꌚ�v����p�������̔��W�E�W�J��}��v�Ƃ��ꂽ�B�����āA��ʔp�����̏����́A���ʋ悪�u���W�E�^���E���ԏ����E�ŏI�����Ɋւ��鎖�����̂��ׂĂɐӔC���A���Ȋ����I�Ȏ��Ƃ��s���v�Ƃ����O�ꂵ���u����������̌����v��ł��o�����B�܂��A���|�H�ꂪ�������̓��ʋ�ł́A������ɍH�ꂪ���������܂�23����u���b�N�������āA�H��\�͂ɗ]�T�̂���אڋ�ƈϑ�������������ԂƂ�����������́u�n�揈���v���s���Ƃ���Ă����B���́u�n�揈���v�́A�����܂ł���������������{���邽�߂̌o�ߑ[�u�ɉ߂��Ȃ������B
���̂悤�ɁA���c�Ă̎��_�ł͎��W�E�^���E���ԏ����E�ŏI�����܂Ŏ��Ȋ����I�Ȏ��Ƃ��s�����Ƃ�ڎw���Ƃ���Ă������A���̌�́u��C�����h�~�@�v��u�p���������@�v�̎{�s�߉����ɂ��A���̏��ς���Ă����B���̉����ł́A�_�C�I�L�V���ނ̔r�o��ɂ��Ă̋K�����������ꂽ�B�ꕔ�̐��|�H��͂��̊�ɓK�����Ă��炸�A�����x�~���ĉ��C���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B���̂��ߓ����̕��j��ύX���A1998�N�̋撷��ɂ����āA�u��ʔp�����̒��ԏ����ɂ��Ă͈����ԋ�����������v���Ƃ���{���j�Ƃ��č��ӂ���A2005�N�x�܂ł͎b��I�ɓ��ʋ悩��̔h���E������Ȃ�u����23�搴�|�ꕔ�����g���v�������������s�����ƂƂȂ����B2006�N�x�ȍ~�͋��c�ĂɊ�Â��A����������̌o�ߑ[�u�Ƃ��Ă̒n�揈���Ɉڍs��������Řb��������������ꂽ�B
�S�D�@�@���ʋ搴�|���Ƃ̌���
���ݓ��ʋ���ɂ́A�v�����g���X�V���Ă���Œ��̂��̂��܂߂�ƁA�R���݂�����21�̐��|�H�ꂠ�邪�A��r�I�傫�ȋ�ł���
���݂̊e��̏́A�傫��3�ɕ�������B���ɁA�u����������v���قڒB�����Ă����ŁA
�T�D
�u����������̌����v�̓]���_
�������A�����ɂ��āu����������̌����v���������傫�ȓ]���_���K�ꂽ�B2003�N7��16���A���ʋ撷��͑���ɂ����āA23��S�̂̐ӔC�Ƃ��đ��݂ɋ��́E�A�g���Ă��݂̒��ԏ����̐����m�ۂ���ƂƂ��ɁA�V���Ȑ��|�H��̕K�v���Ȃ����Ƃ��m�F���A�H�ꌚ�݂����߂Ă���
����́A30�N�����Ă����u����������̌����v����傫�ȓ]����}�錈�f�ł������B
�U�D
�@���_�\���|�����ڊǂɂ����ʂƍ���̉ۑ�\
�@�����������f�́A
�@���݂̐��|�ꕔ�����g���ɂ�钆�ԏ����̐��̂܂܂ł́A�Z���̈ӌ����@����A������M����@����قƂ�ǂȂ��B���Ƃ��Z�������|�H��Ɋւ��ċ�����ɑi�����Ƃ��Ă��A��Ɛ��|�ꕔ�����g���͏\���ɘA�g���Ƃ�Ă��Ȃ����߁A���̐��͑S���Ƃ����Ă����قǓ͂��Ȃ��܂܂ł���B����܂ł̕��j��]����������ɂ́A�����I�A����I�ł���Ȃ���A�Z���̐����ő�����f���邽�߂�23��S�̂Ƃ��Ăǂ����������x���̗p���邱�Ƃ����������̂��A���������T�d�Ɍ������Ă����K�v������B
�u����������̌����v���ł��o���ꂽ30�N�O�Ƃ́A�����₲�ݗʂȂǁA���|�s������芪���w�i�͑傫���قȂ��Ă���B�܂��A�e��̋K�́A�l���A���j�A�Z���ӎ��Ȃǂɂ͑傫�Ȋi�������邽�߁A����̓��ʋ搴�|���Ƃ́A�n��̎���ɉ������I��������ׂ��ł���B������������u�����A���ꂪ�\��
�����ꗗ
�ꎟ����
�o�ώY�Əȁw�����z�n���h�u�b�N�\�@���x�ƂRR�̓����\�x�i�o�ώY�ƏȋZ�p���ǃ��T�C�N�����i�ǁ@2003�j
������\�O�搴�|�ꕔ�����g���w���ƊT�v�x�i������\�O�搴�|�ꕔ�����g���@2002�j
������\�O�搴�|���c��w23�搴�|�ƃ��T�C�N���x�i������\�O�搴�|���c��@2002�j
���ʋ�E�����C���ҁw���ʋ�E���K�C�h�u�b�N�x�i���傤�����@2002�j
������\�O�搴�|�ꕔ�����g���z�[���y�[�W�@http://tokyo23.seisou.or.jp/
����
���{�T���u����23��̂��ݏ����v�w�����K�o�i���X�T����No.25/2003�x�Fpp.90-92�i���傤�����@2003�j
��{�����w���݂ƃ��T�C�N���x�i��g�V���@1990�j
�u���|���Ƃ̓]�������f�v�s���V��i2003�N7��18���jp.6
�u���|�H�ꌚ�ݒ��~�ցv���{�o�ϐV���i�����j�i2003�N7��19���jp.31